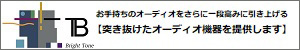【連載】PIT INNその歴史とミュージシャン − 第6回:日野皓正さんが語る「ピットイン」の真の姿<前編>
今回は特別ゲストとして、ピットインの開店直後からステージに立ち、今なお精力的に演奏活動を行うジャズ界の大物トランペッター、日野皓正さんに登場していただく。雪の降りしきる「岩原ピットイン」(新宿ピットインの姉妹店)にて佐藤良武さんとの対談形式で、ピットインとの深い関わりと思い出を語ってもらおう。(日野さんとの対談は、次回を含め2回構成となります)
ピットイン創世記に知り合い、それ以来出演が続く
初めてのアメリカ渡航により考え方が大きく変化した
スキーも楽しめる岩原ピットインでの冬のライブはもう、14年連続になる
佐藤良武(以下佐藤):日野さんのスキー腕前は、ジャズの世界では有名です。5年前にスキー検定一級をとりましたよね。
日野皓正(以下日野):スキーはトランペットにも関係しているんですよ。足腰がしっかりしていると、息が長く続く。特にハイノート(高音)は大腿筋で出すんだからね。
佐藤:え、そうなんですか?それは初めて聞きました。
日野:運動不足の時に、ステージへ上がると、太腿が疲れて疲れて。だからといって、大腿筋だけ鍛えても音が出るはずはないけどね(笑)。
佐藤:ところで日野さん、ここ「岩原ピットイン」の「ジャズ・イン・スノウ」には毎年出演していただいていますが、今年でもう14年連続ですよ。
日野:へえ、もうそんなになるの。なにしろ演奏機材は、全部ここへ置きっぱなしだから新幹線にぱっと乗れば、すぐ出演できるからね。スキーももっとうまくなりたいから、時間がちょっとでもあれば来たいと思っているんですよ。それに良武さんはスキー指導員の免許を持っているでしょう。いろいろ教わりたいんですよ。
佐藤:ゲレンデで「ここをこうやって」と身振り手振りで説明していると、たいてい途中でどこかに行っちゃうんだから(笑)。
日野:「もうそんなの500回聞いたよ」って感じでね(笑)。いや、でも最近はおとなしく話を聞いているよ。
佐藤:日野さんがスキーを始めたのは、いつ頃ですか。
日野:64年に白木秀雄さんのクインテットに加入してから、テナーサックスの稲垣次郎さんが、「日野君、スキーやらないの?」て、誘われたのがきっかけだね。稲垣さんが、岩原に通っていたこともあって、僕がスキーを始めたのがこの場所。もちろん「岩原ピットイン」はまだできていないから、不思議な縁があったんだよ。まあ、でもずっと自己流でいい加減な滑り方だった。
佐藤:95年に「ジャズ・イン・スノウ」へ出演してもらうようになってから、本格的に滑りだしたんですよね。
日野:そう、良武さんから「滑り方が滅茶苦茶だ」と指摘されてから(笑)。
佐藤:ところで「岩原ピットイン」とほかのライブハウスでは、演奏する気分は違うものですか。
日野:それは、違いますよ。特に「新宿ピットイン」は、いまも昔も好きな演奏をやらせてもらえるから、自分たちの本領を発揮しないといけない。客層もマニアックで、食い入るように見つめている。シリアスなムードだね。そこへいくと、こちらは、ジャズをよく知らない人も聴きにくるので、ジャズ入門編的な演奏もやる。皆さん、スキーという遊びに来ているわけですから、ハッピーに楽しめるジャズをやります。
シリアスなムードで真剣勝負の「新宿ピットイン」とは異なり
「岩原ピットイン」での演奏はハッピーで楽しめるジャズをやる
新宿には66年から週1度の出演をしエルヴィン・ジョーンズとも競演した
佐藤:昔を振り返りますけど、初めて日野さんに会ったのは、「ピットイン」をオープンしたての頃で、私がまだ学生でしたね。
日野:僕が白木クインテットを辞めるか辞めないかぐらいの頃かな。自分のレギュラー・クインテットでもう出始めていたね。村岡建(サックス)、大野雄二(ピアノ)、稲葉国光(ベース)、弟の元彦(ドラム)がメンバー。のちにピアノはコルゲン(鈴木宏昌)に替わった。良武さんとの初対面の印象ってあんまりないんだよね。いつも店にいるので、なんとなく知り合ったなあという感じで。
佐藤:66年ぐらいから週1回のペースで出演してもらっていましたね。当時は歌舞伎町の「タロ−」、銀座の「ジャンク」、あと「ピットイン」ぐらいしか演奏できる場所がなかったんですよね。66年の暮れ、エルヴィン・ジョーンズが麻薬不法所持の容疑で勾留されたとき、「ピットイン」で日本人ミュージシャンと共演しましたが、日野さん出ていましたね。
日野:あれは信じられなかった。世界のトッププレーヤー、エルヴィンと共演できるわけだから。ステージに立っていると、ビートがグワーってやってくる。ビートの大海原がうねっている感じだった。凄いな、これほどのドラマーはどこにもいないなって思った。エルヴィンは静寂から大爆音まで、自在にコントロールできるんだけど、あの時は、勾留されて怒っていたから、最初からガンガン飛ばす感じだった。ものすごいパワーでね。ドラムの皮は破るわ、ペダルは折っちゃうわで大変だった。その時、一緒に地方巡業にも行ったんだよ。
菊地雅章とのクインテットを結成
実はレコーディングも行っている
佐藤:日野さんは、その翌年にタクトで初リーダー作『アローン・アローン・アンド・アローン』を録音して、69年にはプーさん(菊地雅章)と菊地=日野クインテットを結成しましたね。ピットインにはそのバンドで毎週定期的に出演してもらっていました。
日野:そう、あれは僕のバンドにプーさんが、「入れろよ」って言ってきたのが始まり。あの人からそう言われたら仕方ないなと思って(笑)、ピアニストに辞めてもらった。プーさんが、秋にバークリー音楽大学に留学するまでね。
佐藤:プーさんとのつきあいは、それよりずっと前からですよね。
日野:二十歳そこそこの頃かな。プーさんからいきなり電話がかかってきた。「あ、日野君、いま新世紀音楽研究所というところにミュージシャンが集まっているんだ。遊びにおいでよ」とね。高柳昌行さんや金井英人さん、富樫雅彦、ほか当時の新人ジャズマンがセッションをやっていると言うんですよ。僕には無理だと思ったけど、いいからいいからという感じでね。そこが始まりだったね。
佐藤:ということは、プーさんは日野さんのことをすでに知っていた?
日野:スイングジャーナルなどの雑誌で「トランペットの新星現わる」みたいに書かれていたからね。まだ、スタジオ・ミュージシャンとしてセッションをこなしていただけなんだけど、ちょっと人気が出始めていた。日野皓正とロイヤルポップスオーケストラという具合に、こっちが知らないうちにレコードへ名前をフィーチャーされていたこともあったよ。印税は入ってこないけど(笑)。
佐藤:その新世紀音楽研究所の演奏が録音されて、『銀巴里セッション』というタイトルでリリースされています。
日野:シャンソン喫茶として有名だった銀座の「銀巴里」が金曜日の午後だけ場所を貸してくれてね。そこでセッションをしたな。僕なんか新人は、午後すぐに始まった頃の出番で、プーさんはトリをやっていた。演奏している途中で、プーさんが店に入ってくると、急にシャキッとして、張り切って吹いたね。終演後には、いろいろと演奏の感想を聞かせてもらった。あの頃から恐いけど凄い人という感じだったね。
佐藤:「新宿ピットイン」(晶文社)という本があって、その年表に書いてあるんだけど、プーさんが渡米後の69年に、日野クインテットはピットインでライブレコーディングを行っている。レコード会社はタクト。これは未発表のままなんだけど、なにか憶えてますか?実は私も記憶にないんだけど。
日野:あ、そうなの。いやあ、すっかり忘れた。どこかに音が残っているのかなあ。僕が死んでから出そうとしているのかなあ(笑)。
佐藤:あの頃は安保闘争の学生運動が盛んな時代でね。
日野:学園祭で呼ばれて演奏していると、学生はみんな過激になっているから、石やビールの缶が飛んでくる。僕や渡辺貞夫さんは、平凡パンチで取り上げられて有名になっていたから、彼らにしてみると僕らは体制側に映るのね。そこへいくと山下洋輔や沖至たちは、抵抗の音楽だったから受け入れられていたね。「ピットイン」では「なんだぁ、オマエ達には負けられないぞ」みたいな意識で、内面ではケンカして演奏していた。
佐藤:あの頃の日野さんは、恐かったですよ。ピリピリしていた。一言もしゃべらないし。逆にそれがひとつの日野さんのイメージを作った。
日野:いまみたいにオヤジギャグは言わないしね(笑)。でも本質的に、僕はアグレッシブなファイターだから、まったく変わっていない。僕のバンド連中はみんな恐れているよ。厳しくしごくからね。でもそれは愛情。こいつはダメだなと思ったら絶対に何も言わないから。
「新宿ジャズ賞」をもらって米国へ
多くの出会いにより生き様が変わった
佐藤:日野さんの人生を大きく変えたのが、69年にアメリカへ渡ったことですよね。
日野:弟と一緒にね。初めてのアメリカでしたね。第1回の「新宿ジャズ賞」で最優秀賞をもらって、その賞品がアメリカ往復チケット。航路はハワイ経由だった。なんで、こんなジャズに関係ないところに寄るんだよって思っていたら、後藤芳子さんがハワイで歌っていて、食事に連れて行ってもらった。次にサンフランシスコに入って、小澤征爾さんからの招待で、特等席でマーラーを聴かせてもらった。けれど、時差の関係でもう眠くて仕方がない。突然、オーケストラがガガーンと来るので目を覚ました(笑)。やっぱりアメリカならジャズだと思ってクラブを探したら、シスコの郊外のサウスアリートというところにあるというので、行ってみた。ぜひステージに飛び入りさせてくれと言ったら、店の主人が、朝の6時に来いというんだよ。
佐藤:えっ、朝の!?
日野:これは適当にあしらわれているなと思って行かなかった。だけど後でわかったんだけど本当にやっていたんだよ。ミュージシャン・ユニオンの決まりでよそから来た人は簡単には演奏ができなかったみたいなんだよね。それで、ようやく西海岸から、ニューヨークに渡った。当時はヒッピーの時代だから、男の人は上半身裸で、もじゃもじゃの長髪で、赤ちゃんとか抱いているんだよ。なんか恐いよなあ、って思った記憶があるね。ライブハウスもリー・モーガンが殺された「スラッグス」とか「イーストビレッジイン」とかたくさんあって、ハーレムの「バロン」でマイルス・デイヴィスを見ることができた。メンバーは、ウェイン・ショーター(サックス)にチック・コリア(ピアノ)、デイヴ・ホランド(ベース)、ジャック・デジョネット(ドラムス)、それにアイアート・モレイラだったな。「うわあ、なにこれ、凄い」というステージだった。ステージの後ろが鏡になっていて、マイルスはソロを吹かない時、後ろをみながら、シャドー・ボクシングやっているんだよ。それが最高にかっこよくてね。
佐藤:その渡米中に、いきなり現地ミュージシャンを集めてレコーディングをしていますよね。
日野:『ジャーニー・トゥ・エアー』だね。ベースが中村照夫にデイヴ・ホランド 、ラリー・フィールズの3人で、スティーブ・グロスマンやら何人もサックスを入れてね。フリージャズだった。
佐藤:そういう時代でした。そして日野さんは帰国するわけだけど、びっくりするくらい変わりましたよね。
(第7回に続く)
インタビュー・文 田中伊佐資
写真 君嶋寛慶
日野皓正さん Terumasa Hino(ジャズ・トランペッター) プロフィール
1942年10月25日東京生まれ。タップダンサー兼トランペッターであった父親より、4歳からタップダンス、9歳からトランペットを学び始め、13歳の頃には米軍キャンプのダンス・バンドで活動を始める。1964年、白木秀雄クインテットに参加し、65年ベルリン・ジャズ・フェスティバルに出演し喝采を浴びる。67年、初リーダー・アルバム『アローン・アローン・アンド・アローン』をリリース。69年には『ハイノロジー』をリリース後、マスコミに“ヒノテル・ブーム”と騒がれるほどの絶大な注目を集める。72年、ニューポート・ジャズ・フェスティバルに出演。75年、ニューヨークに渡って居を構え、ジャッキー・マクリーン、ギル・エバンス、ホレス・シルバー、ラリー・コリエルなどと活動を重ねる。
79年に『シティー・コネクション』、81年に『ダブル・レインボー』、とたて続けに大ヒットアルバムをリリースした。その後82年には『ピラミッド』をリリースし、武道館を含む全国ツアーを行う。
89年にはジャズの名門レーベル“ブルー・ノート”と日本人初の契約アーティストとなり、第1弾アルバム『ブルーストラック』は、日本はもとより、アメリカでも大好評を博した。90年以降は自身の夢である「アジアを1つに」という願いを込め、アジア各国を渡り歩き、探し集めたミュージシャンたちと結成した<日野皓正&ASIAN JAZZ ALLSTARS>で、1995〜96年に北米〜アジアツアーを行う。
2000年に、大阪音楽大学短期大学部客員教授に就任(現在に至る)。01年春にはインド、パキスタンにて公演の他、西インド地震災害チャリティコンサート行う。そしてカンボジアでも子供たちのためのチャリティコンサートを行い、6月にアルバム『D・N・A』をリリースし、10月にはそのレコーディング・メンバーにて全国ツアーを行う。このD・N・Aプロジェクトは芸術選奨文部科学大臣賞(大衆芸能部門)受賞した。
2004年紫綬褒章を受章。また約20年ぶりに映画音楽を手掛け、(「透光の樹」主演:秋吉久美子、監督:根岸吉太郎)サウンド・トラックは文化庁芸術祭 レコード部門の優秀賞、毎日映画コンクールの音楽賞を受賞。
最新アルバムは菊地雅章(p)との双頭ユニット、日野=菊地クインテット「カウンターカレント」と、菊地とのデュオ・アルバム「エッジス」。この「エッジス」は2007年度日本ジャズディスク大賞「銀賞」を受賞した。
本記事は「季刊・analog」にて好評連載中です。「analog」の購入はこちらから
ピットイン創世記に知り合い、それ以来出演が続く
初めてのアメリカ渡航により考え方が大きく変化した
スキーも楽しめる岩原ピットインでの冬のライブはもう、14年連続になる
佐藤良武(以下佐藤):日野さんのスキー腕前は、ジャズの世界では有名です。5年前にスキー検定一級をとりましたよね。
日野皓正(以下日野):スキーはトランペットにも関係しているんですよ。足腰がしっかりしていると、息が長く続く。特にハイノート(高音)は大腿筋で出すんだからね。
佐藤:え、そうなんですか?それは初めて聞きました。
日野:運動不足の時に、ステージへ上がると、太腿が疲れて疲れて。だからといって、大腿筋だけ鍛えても音が出るはずはないけどね(笑)。
佐藤:ところで日野さん、ここ「岩原ピットイン」の「ジャズ・イン・スノウ」には毎年出演していただいていますが、今年でもう14年連続ですよ。
日野:へえ、もうそんなになるの。なにしろ演奏機材は、全部ここへ置きっぱなしだから新幹線にぱっと乗れば、すぐ出演できるからね。スキーももっとうまくなりたいから、時間がちょっとでもあれば来たいと思っているんですよ。それに良武さんはスキー指導員の免許を持っているでしょう。いろいろ教わりたいんですよ。
佐藤:ゲレンデで「ここをこうやって」と身振り手振りで説明していると、たいてい途中でどこかに行っちゃうんだから(笑)。
日野:「もうそんなの500回聞いたよ」って感じでね(笑)。いや、でも最近はおとなしく話を聞いているよ。
佐藤:日野さんがスキーを始めたのは、いつ頃ですか。
日野:64年に白木秀雄さんのクインテットに加入してから、テナーサックスの稲垣次郎さんが、「日野君、スキーやらないの?」て、誘われたのがきっかけだね。稲垣さんが、岩原に通っていたこともあって、僕がスキーを始めたのがこの場所。もちろん「岩原ピットイン」はまだできていないから、不思議な縁があったんだよ。まあ、でもずっと自己流でいい加減な滑り方だった。
佐藤:95年に「ジャズ・イン・スノウ」へ出演してもらうようになってから、本格的に滑りだしたんですよね。
日野:そう、良武さんから「滑り方が滅茶苦茶だ」と指摘されてから(笑)。
佐藤:ところで「岩原ピットイン」とほかのライブハウスでは、演奏する気分は違うものですか。
日野:それは、違いますよ。特に「新宿ピットイン」は、いまも昔も好きな演奏をやらせてもらえるから、自分たちの本領を発揮しないといけない。客層もマニアックで、食い入るように見つめている。シリアスなムードだね。そこへいくと、こちらは、ジャズをよく知らない人も聴きにくるので、ジャズ入門編的な演奏もやる。皆さん、スキーという遊びに来ているわけですから、ハッピーに楽しめるジャズをやります。
シリアスなムードで真剣勝負の「新宿ピットイン」とは異なり
「岩原ピットイン」での演奏はハッピーで楽しめるジャズをやる
新宿には66年から週1度の出演をしエルヴィン・ジョーンズとも競演した
佐藤:昔を振り返りますけど、初めて日野さんに会ったのは、「ピットイン」をオープンしたての頃で、私がまだ学生でしたね。
日野:僕が白木クインテットを辞めるか辞めないかぐらいの頃かな。自分のレギュラー・クインテットでもう出始めていたね。村岡建(サックス)、大野雄二(ピアノ)、稲葉国光(ベース)、弟の元彦(ドラム)がメンバー。のちにピアノはコルゲン(鈴木宏昌)に替わった。良武さんとの初対面の印象ってあんまりないんだよね。いつも店にいるので、なんとなく知り合ったなあという感じで。
佐藤:66年ぐらいから週1回のペースで出演してもらっていましたね。当時は歌舞伎町の「タロ−」、銀座の「ジャンク」、あと「ピットイン」ぐらいしか演奏できる場所がなかったんですよね。66年の暮れ、エルヴィン・ジョーンズが麻薬不法所持の容疑で勾留されたとき、「ピットイン」で日本人ミュージシャンと共演しましたが、日野さん出ていましたね。
日野:あれは信じられなかった。世界のトッププレーヤー、エルヴィンと共演できるわけだから。ステージに立っていると、ビートがグワーってやってくる。ビートの大海原がうねっている感じだった。凄いな、これほどのドラマーはどこにもいないなって思った。エルヴィンは静寂から大爆音まで、自在にコントロールできるんだけど、あの時は、勾留されて怒っていたから、最初からガンガン飛ばす感じだった。ものすごいパワーでね。ドラムの皮は破るわ、ペダルは折っちゃうわで大変だった。その時、一緒に地方巡業にも行ったんだよ。
菊地雅章とのクインテットを結成
実はレコーディングも行っている
佐藤:日野さんは、その翌年にタクトで初リーダー作『アローン・アローン・アンド・アローン』を録音して、69年にはプーさん(菊地雅章)と菊地=日野クインテットを結成しましたね。ピットインにはそのバンドで毎週定期的に出演してもらっていました。
日野:そう、あれは僕のバンドにプーさんが、「入れろよ」って言ってきたのが始まり。あの人からそう言われたら仕方ないなと思って(笑)、ピアニストに辞めてもらった。プーさんが、秋にバークリー音楽大学に留学するまでね。
佐藤:プーさんとのつきあいは、それよりずっと前からですよね。
日野:二十歳そこそこの頃かな。プーさんからいきなり電話がかかってきた。「あ、日野君、いま新世紀音楽研究所というところにミュージシャンが集まっているんだ。遊びにおいでよ」とね。高柳昌行さんや金井英人さん、富樫雅彦、ほか当時の新人ジャズマンがセッションをやっていると言うんですよ。僕には無理だと思ったけど、いいからいいからという感じでね。そこが始まりだったね。
佐藤:ということは、プーさんは日野さんのことをすでに知っていた?
日野:スイングジャーナルなどの雑誌で「トランペットの新星現わる」みたいに書かれていたからね。まだ、スタジオ・ミュージシャンとしてセッションをこなしていただけなんだけど、ちょっと人気が出始めていた。日野皓正とロイヤルポップスオーケストラという具合に、こっちが知らないうちにレコードへ名前をフィーチャーされていたこともあったよ。印税は入ってこないけど(笑)。
佐藤:その新世紀音楽研究所の演奏が録音されて、『銀巴里セッション』というタイトルでリリースされています。
日野:シャンソン喫茶として有名だった銀座の「銀巴里」が金曜日の午後だけ場所を貸してくれてね。そこでセッションをしたな。僕なんか新人は、午後すぐに始まった頃の出番で、プーさんはトリをやっていた。演奏している途中で、プーさんが店に入ってくると、急にシャキッとして、張り切って吹いたね。終演後には、いろいろと演奏の感想を聞かせてもらった。あの頃から恐いけど凄い人という感じだったね。
佐藤:「新宿ピットイン」(晶文社)という本があって、その年表に書いてあるんだけど、プーさんが渡米後の69年に、日野クインテットはピットインでライブレコーディングを行っている。レコード会社はタクト。これは未発表のままなんだけど、なにか憶えてますか?実は私も記憶にないんだけど。
日野:あ、そうなの。いやあ、すっかり忘れた。どこかに音が残っているのかなあ。僕が死んでから出そうとしているのかなあ(笑)。
佐藤:あの頃は安保闘争の学生運動が盛んな時代でね。
日野:学園祭で呼ばれて演奏していると、学生はみんな過激になっているから、石やビールの缶が飛んでくる。僕や渡辺貞夫さんは、平凡パンチで取り上げられて有名になっていたから、彼らにしてみると僕らは体制側に映るのね。そこへいくと山下洋輔や沖至たちは、抵抗の音楽だったから受け入れられていたね。「ピットイン」では「なんだぁ、オマエ達には負けられないぞ」みたいな意識で、内面ではケンカして演奏していた。
佐藤:あの頃の日野さんは、恐かったですよ。ピリピリしていた。一言もしゃべらないし。逆にそれがひとつの日野さんのイメージを作った。
日野:いまみたいにオヤジギャグは言わないしね(笑)。でも本質的に、僕はアグレッシブなファイターだから、まったく変わっていない。僕のバンド連中はみんな恐れているよ。厳しくしごくからね。でもそれは愛情。こいつはダメだなと思ったら絶対に何も言わないから。
「新宿ジャズ賞」をもらって米国へ
多くの出会いにより生き様が変わった
佐藤:日野さんの人生を大きく変えたのが、69年にアメリカへ渡ったことですよね。
日野:弟と一緒にね。初めてのアメリカでしたね。第1回の「新宿ジャズ賞」で最優秀賞をもらって、その賞品がアメリカ往復チケット。航路はハワイ経由だった。なんで、こんなジャズに関係ないところに寄るんだよって思っていたら、後藤芳子さんがハワイで歌っていて、食事に連れて行ってもらった。次にサンフランシスコに入って、小澤征爾さんからの招待で、特等席でマーラーを聴かせてもらった。けれど、時差の関係でもう眠くて仕方がない。突然、オーケストラがガガーンと来るので目を覚ました(笑)。やっぱりアメリカならジャズだと思ってクラブを探したら、シスコの郊外のサウスアリートというところにあるというので、行ってみた。ぜひステージに飛び入りさせてくれと言ったら、店の主人が、朝の6時に来いというんだよ。
佐藤:えっ、朝の!?
日野:これは適当にあしらわれているなと思って行かなかった。だけど後でわかったんだけど本当にやっていたんだよ。ミュージシャン・ユニオンの決まりでよそから来た人は簡単には演奏ができなかったみたいなんだよね。それで、ようやく西海岸から、ニューヨークに渡った。当時はヒッピーの時代だから、男の人は上半身裸で、もじゃもじゃの長髪で、赤ちゃんとか抱いているんだよ。なんか恐いよなあ、って思った記憶があるね。ライブハウスもリー・モーガンが殺された「スラッグス」とか「イーストビレッジイン」とかたくさんあって、ハーレムの「バロン」でマイルス・デイヴィスを見ることができた。メンバーは、ウェイン・ショーター(サックス)にチック・コリア(ピアノ)、デイヴ・ホランド(ベース)、ジャック・デジョネット(ドラムス)、それにアイアート・モレイラだったな。「うわあ、なにこれ、凄い」というステージだった。ステージの後ろが鏡になっていて、マイルスはソロを吹かない時、後ろをみながら、シャドー・ボクシングやっているんだよ。それが最高にかっこよくてね。
佐藤:その渡米中に、いきなり現地ミュージシャンを集めてレコーディングをしていますよね。
日野:『ジャーニー・トゥ・エアー』だね。ベースが中村照夫にデイヴ・ホランド 、ラリー・フィールズの3人で、スティーブ・グロスマンやら何人もサックスを入れてね。フリージャズだった。
佐藤:そういう時代でした。そして日野さんは帰国するわけだけど、びっくりするくらい変わりましたよね。
(第7回に続く)
インタビュー・文 田中伊佐資
写真 君嶋寛慶
日野皓正さん Terumasa Hino(ジャズ・トランペッター) プロフィール
1942年10月25日東京生まれ。タップダンサー兼トランペッターであった父親より、4歳からタップダンス、9歳からトランペットを学び始め、13歳の頃には米軍キャンプのダンス・バンドで活動を始める。1964年、白木秀雄クインテットに参加し、65年ベルリン・ジャズ・フェスティバルに出演し喝采を浴びる。67年、初リーダー・アルバム『アローン・アローン・アンド・アローン』をリリース。69年には『ハイノロジー』をリリース後、マスコミに“ヒノテル・ブーム”と騒がれるほどの絶大な注目を集める。72年、ニューポート・ジャズ・フェスティバルに出演。75年、ニューヨークに渡って居を構え、ジャッキー・マクリーン、ギル・エバンス、ホレス・シルバー、ラリー・コリエルなどと活動を重ねる。
79年に『シティー・コネクション』、81年に『ダブル・レインボー』、とたて続けに大ヒットアルバムをリリースした。その後82年には『ピラミッド』をリリースし、武道館を含む全国ツアーを行う。
89年にはジャズの名門レーベル“ブルー・ノート”と日本人初の契約アーティストとなり、第1弾アルバム『ブルーストラック』は、日本はもとより、アメリカでも大好評を博した。90年以降は自身の夢である「アジアを1つに」という願いを込め、アジア各国を渡り歩き、探し集めたミュージシャンたちと結成した<日野皓正&ASIAN JAZZ ALLSTARS>で、1995〜96年に北米〜アジアツアーを行う。
2000年に、大阪音楽大学短期大学部客員教授に就任(現在に至る)。01年春にはインド、パキスタンにて公演の他、西インド地震災害チャリティコンサート行う。そしてカンボジアでも子供たちのためのチャリティコンサートを行い、6月にアルバム『D・N・A』をリリースし、10月にはそのレコーディング・メンバーにて全国ツアーを行う。このD・N・Aプロジェクトは芸術選奨文部科学大臣賞(大衆芸能部門)受賞した。
2004年紫綬褒章を受章。また約20年ぶりに映画音楽を手掛け、(「透光の樹」主演:秋吉久美子、監督:根岸吉太郎)サウンド・トラックは文化庁芸術祭 レコード部門の優秀賞、毎日映画コンクールの音楽賞を受賞。
最新アルバムは菊地雅章(p)との双頭ユニット、日野=菊地クインテット「カウンターカレント」と、菊地とのデュオ・アルバム「エッジス」。この「エッジス」は2007年度日本ジャズディスク大賞「銀賞」を受賞した。
本記事は「季刊・analog」にて好評連載中です。「analog」の購入はこちらから
関連リンク