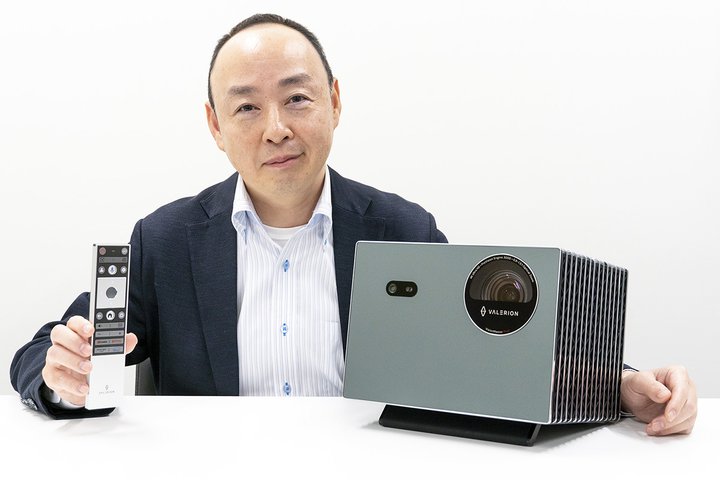HOME > ニュース > AV&ホームシアターニュース
公開日 2017/09/03 08:16
<IFA>「HDR10+」とは何か、パナソニックがなぜ推進するのか。サムスンと手を組んだねらい
HDRの美しい映像を中下位機でも
パナソニックが「HDR10+」を推進すると聞いたときには驚いた。同社とサムスン、20世紀FOXの3社が共同で規格を推進し、18年1月には同規格のライセンス供与を行う団体を設立するというのだ。
HDR映像に関わる他社も、HDR10+にパナソニックが加わることを知る人はほとんどいなかっただろうと、パナソニックの小塚雅之氏は笑う。「なんとなくパナソニックが動いている感触を持っているメーカーはあったかもしれませんが、ほとんどのメーカーは今回のIFAで初めて知ったはずです」。
今回、パナソニックの小塚雅之氏と森瀬真琴氏に、なぜパナソニックがHDR10+を推進するのか、その規格の詳細や技術的メリットなどをくわしく聞いた。
■シーンごとに輝度情報を持たせるダイナミックメタデータ
HDR10+はその名の通り、現在のHDR10の拡張規格である。ちなみにHDR10+という名称はまだ仮称であり、今後わかりやすい名称やロゴが制定される予定だ。
現行のHDR10規格は、Ultra HD Blu-ray(UHD BD)のマンダトリー(必須)規格で、HDR映像が収録されているUHD BDには、必ずHDR10の情報が記録されている。このためHDR10は業界標準規格となっており、HDR対応テレビといえば、まず間違いなくHDR10に対応している。
HDR10では、一つのコンテンツに対して一つのコンテンツ最大輝度(Maximum Content Light Level=Max CLL)データが記録されている。このスタティックメタデータ(静的メタデータ)をもとにテレビ側でトーンマッピングを行い、最終的な映像として出力するわけだ。
ただし、これでは不十分という声もある。たとえば、全体的に非常に明るい映画ではMax CLLが高くなるため、これをメタデータとして記録する。だがそのコンテンツに薄暗いシーンがあった場合、全体を通したMax CLLをもとにトーンマッピングすると、これらの薄暗いシーンが制作者の意図より暗く見えることがある。これはローカルディミング機能を持たないテレビで、特に顕著に表れる。
この問題を解決するのが、フレームごと、あるいはシーンごとにMax CLLデータをメタ情報として記録する、ダイナミックメタデータ(動的メタデータ)という考え方だ。ドルビービジョンは当初からダイナミックメタデータを特徴としており、シーン、あるいはフレームごとに輝度レベルが調整される。これによって、どのような映像でも制作者の意図通りに映像を再現できるとアピールしている。
HDR10+は、HDR10をベースとしながら、このダイナミックメタデータを組み込むことを提案する新技術だ。今年4月にサムスンとAmazon Videoが発表した。
なお、HDR10+のもとになった技術はSMPTE(米国映画テレビ技術者協会)の「SMPTE 2094-40」として規格化されており、その内容が公開されている(SMPTEの説明資料)。
さらに、サムスンはすでにBDA(Blu-ray Disc Association)に対してもHDR10+規格を申請しており、今年11月の総会で無事受理されたら、正式にUHD BDのオプション規格として認定される見込みだ。
■Ultra HD Premium規格は「超ハイエンド過ぎた」
小塚氏は、このHDR10+規格にパナソニックが合流した背景として、パナソニックをはじめとしたメーカーやコンテンツ各社、配信各社がはじめた「Ultra HD Premium」規格が、あまり一般に普及していないことを挙げる。
小塚氏はその最大の理由として、Ultra HD Premium規格が「超ハイエンドであり、これに対応できるテレビが限定的」だったため、と振り返る。
Ultra HD Premiumの認証を受けるには、液晶テレビは1,000nit以上の輝度が必要となる。「当初は数年も経てば多くのモデルがこの程度の明るさを実現すると予想していたが、コストや電力消費の問題もあり、現実的には普及価格帯では困難だった」(小塚氏)。結果的には、4Kテレビ全体のうち2-3%程度しか、この基準をクリアしていないという。
小塚氏はUltra HD Premiumについて「このロゴが付いた製品やコンテンツを組み合わせたら、4K/HDRの良さが十分伝わる体験ができる、ということをお客様にわかりやすく伝えるために作ったもの」と、改めて当初の理念を説明する。
「その考え方自体は良かったが、対応しているのが超ハイエンドモデルばかりだと、より良いHDR視聴体験が広がらない。そうするとソフトが売れず、コンテンツが広がらない。これはソフトメーカー、ハードメーカーともに死活問題になる」と小塚氏は述べ、「ハリウッドが求める画質レベルを維持したまま、より多くのテレビで体験できるようにするため、HDR10+を推進することに決めた」という。実際に、20世紀FOXが規格に賛同したことも、HDR10+をパナソニックが推進する大きな後押しになったという。
■オープン規格、ライセンス料不要、HDR10との再生互換性もあり
さて、ここからはHDR10+の特徴について紹介していこう。
HDR10+はオープン規格であり、特許ライセンス料も不要。技術ライセンス料として年会費が必要だが、ユニットごとのロイヤリティーは発生せず、大手メーカーが1台ごとにコストをならすと「ほとんどゼロに近くなるのでは」というのが小塚氏の説明だ。
技術の所有者はサムスン、パナソニック、20世紀FOXの3社だが、規格そのものは前述のとおり、SMPTE 2094-40に準拠している。
HDR10+は、従来のHDR10との再生互換性も備えている。たとえばHDR10+で記録されたUHD BDを、HDR10対応テレビでも視聴できることになる。ただしこの例の場合、もちろんHDR10+のダイナミックメタデータは利用されない。
なおHDR10+の映像はHDR10と同様、10bitで記録される。この点は12bit記録が可能なドルビービジョンと異なるところだ。
また、実装を各社独自に行えるのも特徴。このため各社が独自のノウハウを蓄えられる。ただしこれだけだと互換性が取りづらいので、テストセンターでテストして認証することで互換性を確保する。
フレーム、もしくはシーンごとにメタデータが付与されると聞いて、データ量が増えるのではと心配する方もいるだろう。ただし小塚氏によれば、増えるのはMPEGのSEIに格納する情報のみで、データ増加は0.1%以下に抑えられるという。
なおメタデータとして、各フレームやシーンの最大輝度だけでなく、輝度分布のヒストグラムも送ることができる。これによって、最も明るい部分の輝度=Max CLLだけでなく、中間調や低輝度部がどうなっているかを知ることもでき、メーカーはこれを画作りに役立てられる。
さらには、たとえば「ディスプレイが○nitsだったときのカーブ」などのデータをあらかじめ用意しておき送ることも、規格の仕様上は可能という。ただしこれについては「あまり使われないのではないか」というのが小塚氏の意見だ。
データを送る際のHDMIの仕様については、HDMI 2.1ではなく、現行のHDMI 2.0aで対応できる。このため、現在販売されているテレビでもHDR10+に対応できる可能性がある。
事実、サムスンは2016年モデルの4Kテレビについて、2017年下半期のファームウェアアップデートでHDR10+に対応させるとアナウンスしている。
また、パナソニックのテレビも2017年モデルのいくつかはアップデートで対応する予定で、2018年に販売するテレビは、ほとんどのモデルがあらかじめHDR10+に対応する見込みという。
気になるのはプレーヤー側の対応だ。今後HDR10+が規格化され、これに対応したUHD BDプレーヤーが登場してくればもちろん再生できるわけだが、現在のプレーヤーがファームウェアアップデートなどで対応できるかどうかは、各社の実装次第という。
HDR10+では、UHD BDが「ベンダー特定情報」をフレームごとに1パケット分送れることを利用するのだが、これを最高60フレーム/秒で、きちんと同期を取りながら行えるかどうかが鍵になる。
さて、技術的によい規格でも、ソフト制作側に負担がかかってしまっては普及しない。これについても、HDR10+を推進する3社が制作ツールを提供。DAVINCIのプラグインなどで、ほぼオートマティックに作ることができるようになるという。
コンテンツは規格を推進する20世紀FOXが積極的に展開していくほか、規格をサムスンとともに提唱したAmazonも採用する見込み。そのほかのメジャースタジオやNetflixなどへも、今後採用を働きかけていく。
ここまでをまとめると、HDR10+はオープン規格で、ライセンス料は年会費のみ、実装は自分たちでできるので画作りの裁量も確保でき、さらに実装の互換性も確保される。現行のHDR10との再生互換性もあるうえ、データ量はほとんど増えず、コンテンツ制作ツールも提供される。これらの特徴から小塚氏は、急速な普及を想定していると胸を張る。
■最高輝度500nits程度のテレビで最も大きな効果
さて、このHDR10+がどのように映像に「効く」のか。パナソニックのブースでは、HDR10とHDR10+の比較デモが行われており、非常に大きな画質の差を実感できた。
小塚氏によれば、HDR10+では様々なデータを送っているが、最大輝度という観点に限定して説明した場合、HDR10+の効果は、最高輝度が500nits程度のテレビで最も大きくなるとのこと。逆に言うと、1,000nits程度ある高級テレビで、さらにローカルディミングが適切に行われた場合、HDR10+の効果はあるものの、限定的なレベルにとどまるという。
下の画像を見て頂くと、その意味がわかる。グラフの青い点線がもとのコンテンツの輝度を表している。たとえばMax CLLが4,000nitsの映像を最大輝度1,000nitsのテレビに入力し、ピーク輝度が100nitだった場合、見え方はHDR10とHDR10+とでほとんど変わらない(黄色が実際にテレビで表示できる輝度範囲を示す)。
今度はもっと最高輝度が暗いテレビの例を見てみよう。Max CLLが4,000nitsの映像を、最高輝度350nitsのテレビに入力し、オリジナル映像のシーン最高輝度が1,000nitsだった場合。これはHDR10でもHDR10+でも、テレビの性能が足らず、高輝度部が表現できない。
では、同じMax CLLが4,000nitsの映像を最高輝度350nitsのテレビで見て、シーン最高輝度が500nitsだった場合はどうか。HDR10ではオリジナル映像より暗くなってしまうが、HDR10+ではもとの映像に近い輝度カーブを描き、オリジナル映像に近くなる。
◇
当サイトでHDR10+をニュースにした際、SNSでの反応として多かったのが「また規格が増えるのか」という嘆きの声だった。
たしかに規格の乱立は、ユーザーの混乱や疲弊を招きかねない。だがHDR10+はHDR10との互換性を備えている。また最大輝度1,000nits程度+ローカルディミング可能な上位機であれば、HDR10でも十分な画質が得られるという小塚氏の見解も、あわせてお伝えしておきたい。
HDR10+に関する次の情報が明かされるのは、おそらく来年初めのCESだろう。同じ1月には早くもライセンスが始まる。早期にBDAでの承認が行われ、対応機器やコンテンツが揃うことを期待したい。
HDR映像に関わる他社も、HDR10+にパナソニックが加わることを知る人はほとんどいなかっただろうと、パナソニックの小塚雅之氏は笑う。「なんとなくパナソニックが動いている感触を持っているメーカーはあったかもしれませんが、ほとんどのメーカーは今回のIFAで初めて知ったはずです」。
今回、パナソニックの小塚雅之氏と森瀬真琴氏に、なぜパナソニックがHDR10+を推進するのか、その規格の詳細や技術的メリットなどをくわしく聞いた。
■シーンごとに輝度情報を持たせるダイナミックメタデータ
HDR10+はその名の通り、現在のHDR10の拡張規格である。ちなみにHDR10+という名称はまだ仮称であり、今後わかりやすい名称やロゴが制定される予定だ。
現行のHDR10規格は、Ultra HD Blu-ray(UHD BD)のマンダトリー(必須)規格で、HDR映像が収録されているUHD BDには、必ずHDR10の情報が記録されている。このためHDR10は業界標準規格となっており、HDR対応テレビといえば、まず間違いなくHDR10に対応している。
HDR10では、一つのコンテンツに対して一つのコンテンツ最大輝度(Maximum Content Light Level=Max CLL)データが記録されている。このスタティックメタデータ(静的メタデータ)をもとにテレビ側でトーンマッピングを行い、最終的な映像として出力するわけだ。
ただし、これでは不十分という声もある。たとえば、全体的に非常に明るい映画ではMax CLLが高くなるため、これをメタデータとして記録する。だがそのコンテンツに薄暗いシーンがあった場合、全体を通したMax CLLをもとにトーンマッピングすると、これらの薄暗いシーンが制作者の意図より暗く見えることがある。これはローカルディミング機能を持たないテレビで、特に顕著に表れる。
この問題を解決するのが、フレームごと、あるいはシーンごとにMax CLLデータをメタ情報として記録する、ダイナミックメタデータ(動的メタデータ)という考え方だ。ドルビービジョンは当初からダイナミックメタデータを特徴としており、シーン、あるいはフレームごとに輝度レベルが調整される。これによって、どのような映像でも制作者の意図通りに映像を再現できるとアピールしている。
HDR10+は、HDR10をベースとしながら、このダイナミックメタデータを組み込むことを提案する新技術だ。今年4月にサムスンとAmazon Videoが発表した。
なお、HDR10+のもとになった技術はSMPTE(米国映画テレビ技術者協会)の「SMPTE 2094-40」として規格化されており、その内容が公開されている(SMPTEの説明資料)。
さらに、サムスンはすでにBDA(Blu-ray Disc Association)に対してもHDR10+規格を申請しており、今年11月の総会で無事受理されたら、正式にUHD BDのオプション規格として認定される見込みだ。
■Ultra HD Premium規格は「超ハイエンド過ぎた」
小塚氏は、このHDR10+規格にパナソニックが合流した背景として、パナソニックをはじめとしたメーカーやコンテンツ各社、配信各社がはじめた「Ultra HD Premium」規格が、あまり一般に普及していないことを挙げる。
小塚氏はその最大の理由として、Ultra HD Premium規格が「超ハイエンドであり、これに対応できるテレビが限定的」だったため、と振り返る。
Ultra HD Premiumの認証を受けるには、液晶テレビは1,000nit以上の輝度が必要となる。「当初は数年も経てば多くのモデルがこの程度の明るさを実現すると予想していたが、コストや電力消費の問題もあり、現実的には普及価格帯では困難だった」(小塚氏)。結果的には、4Kテレビ全体のうち2-3%程度しか、この基準をクリアしていないという。
小塚氏はUltra HD Premiumについて「このロゴが付いた製品やコンテンツを組み合わせたら、4K/HDRの良さが十分伝わる体験ができる、ということをお客様にわかりやすく伝えるために作ったもの」と、改めて当初の理念を説明する。
「その考え方自体は良かったが、対応しているのが超ハイエンドモデルばかりだと、より良いHDR視聴体験が広がらない。そうするとソフトが売れず、コンテンツが広がらない。これはソフトメーカー、ハードメーカーともに死活問題になる」と小塚氏は述べ、「ハリウッドが求める画質レベルを維持したまま、より多くのテレビで体験できるようにするため、HDR10+を推進することに決めた」という。実際に、20世紀FOXが規格に賛同したことも、HDR10+をパナソニックが推進する大きな後押しになったという。
■オープン規格、ライセンス料不要、HDR10との再生互換性もあり
さて、ここからはHDR10+の特徴について紹介していこう。
HDR10+はオープン規格であり、特許ライセンス料も不要。技術ライセンス料として年会費が必要だが、ユニットごとのロイヤリティーは発生せず、大手メーカーが1台ごとにコストをならすと「ほとんどゼロに近くなるのでは」というのが小塚氏の説明だ。
技術の所有者はサムスン、パナソニック、20世紀FOXの3社だが、規格そのものは前述のとおり、SMPTE 2094-40に準拠している。
HDR10+は、従来のHDR10との再生互換性も備えている。たとえばHDR10+で記録されたUHD BDを、HDR10対応テレビでも視聴できることになる。ただしこの例の場合、もちろんHDR10+のダイナミックメタデータは利用されない。
なおHDR10+の映像はHDR10と同様、10bitで記録される。この点は12bit記録が可能なドルビービジョンと異なるところだ。
また、実装を各社独自に行えるのも特徴。このため各社が独自のノウハウを蓄えられる。ただしこれだけだと互換性が取りづらいので、テストセンターでテストして認証することで互換性を確保する。
フレーム、もしくはシーンごとにメタデータが付与されると聞いて、データ量が増えるのではと心配する方もいるだろう。ただし小塚氏によれば、増えるのはMPEGのSEIに格納する情報のみで、データ増加は0.1%以下に抑えられるという。
なおメタデータとして、各フレームやシーンの最大輝度だけでなく、輝度分布のヒストグラムも送ることができる。これによって、最も明るい部分の輝度=Max CLLだけでなく、中間調や低輝度部がどうなっているかを知ることもでき、メーカーはこれを画作りに役立てられる。
さらには、たとえば「ディスプレイが○nitsだったときのカーブ」などのデータをあらかじめ用意しておき送ることも、規格の仕様上は可能という。ただしこれについては「あまり使われないのではないか」というのが小塚氏の意見だ。
データを送る際のHDMIの仕様については、HDMI 2.1ではなく、現行のHDMI 2.0aで対応できる。このため、現在販売されているテレビでもHDR10+に対応できる可能性がある。
事実、サムスンは2016年モデルの4Kテレビについて、2017年下半期のファームウェアアップデートでHDR10+に対応させるとアナウンスしている。
また、パナソニックのテレビも2017年モデルのいくつかはアップデートで対応する予定で、2018年に販売するテレビは、ほとんどのモデルがあらかじめHDR10+に対応する見込みという。
気になるのはプレーヤー側の対応だ。今後HDR10+が規格化され、これに対応したUHD BDプレーヤーが登場してくればもちろん再生できるわけだが、現在のプレーヤーがファームウェアアップデートなどで対応できるかどうかは、各社の実装次第という。
HDR10+では、UHD BDが「ベンダー特定情報」をフレームごとに1パケット分送れることを利用するのだが、これを最高60フレーム/秒で、きちんと同期を取りながら行えるかどうかが鍵になる。
さて、技術的によい規格でも、ソフト制作側に負担がかかってしまっては普及しない。これについても、HDR10+を推進する3社が制作ツールを提供。DAVINCIのプラグインなどで、ほぼオートマティックに作ることができるようになるという。
コンテンツは規格を推進する20世紀FOXが積極的に展開していくほか、規格をサムスンとともに提唱したAmazonも採用する見込み。そのほかのメジャースタジオやNetflixなどへも、今後採用を働きかけていく。
ここまでをまとめると、HDR10+はオープン規格で、ライセンス料は年会費のみ、実装は自分たちでできるので画作りの裁量も確保でき、さらに実装の互換性も確保される。現行のHDR10との再生互換性もあるうえ、データ量はほとんど増えず、コンテンツ制作ツールも提供される。これらの特徴から小塚氏は、急速な普及を想定していると胸を張る。
■最高輝度500nits程度のテレビで最も大きな効果
さて、このHDR10+がどのように映像に「効く」のか。パナソニックのブースでは、HDR10とHDR10+の比較デモが行われており、非常に大きな画質の差を実感できた。
小塚氏によれば、HDR10+では様々なデータを送っているが、最大輝度という観点に限定して説明した場合、HDR10+の効果は、最高輝度が500nits程度のテレビで最も大きくなるとのこと。逆に言うと、1,000nits程度ある高級テレビで、さらにローカルディミングが適切に行われた場合、HDR10+の効果はあるものの、限定的なレベルにとどまるという。
下の画像を見て頂くと、その意味がわかる。グラフの青い点線がもとのコンテンツの輝度を表している。たとえばMax CLLが4,000nitsの映像を最大輝度1,000nitsのテレビに入力し、ピーク輝度が100nitだった場合、見え方はHDR10とHDR10+とでほとんど変わらない(黄色が実際にテレビで表示できる輝度範囲を示す)。
今度はもっと最高輝度が暗いテレビの例を見てみよう。Max CLLが4,000nitsの映像を、最高輝度350nitsのテレビに入力し、オリジナル映像のシーン最高輝度が1,000nitsだった場合。これはHDR10でもHDR10+でも、テレビの性能が足らず、高輝度部が表現できない。
では、同じMax CLLが4,000nitsの映像を最高輝度350nitsのテレビで見て、シーン最高輝度が500nitsだった場合はどうか。HDR10ではオリジナル映像より暗くなってしまうが、HDR10+ではもとの映像に近い輝度カーブを描き、オリジナル映像に近くなる。
当サイトでHDR10+をニュースにした際、SNSでの反応として多かったのが「また規格が増えるのか」という嘆きの声だった。
たしかに規格の乱立は、ユーザーの混乱や疲弊を招きかねない。だがHDR10+はHDR10との互換性を備えている。また最大輝度1,000nits程度+ローカルディミング可能な上位機であれば、HDR10でも十分な画質が得られるという小塚氏の見解も、あわせてお伝えしておきたい。
HDR10+に関する次の情報が明かされるのは、おそらく来年初めのCESだろう。同じ1月には早くもライセンスが始まる。早期にBDAでの承認が行われ、対応機器やコンテンツが揃うことを期待したい。