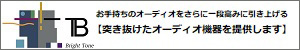【連載】PIT INNその歴史とミュージシャン − 第5回:「ピットイン」と佐藤允彦さんとの長い関係から生まれたもの
今回は特別ゲストとして、ピットインの創世期からステージに立ち、多彩な活動を行うジャズピアニストの佐藤允彦さんに登場していただき、佐藤良武さんとの対談形式で、ピットインとの深い関わりと思い出を語っていただくことにする。
秋吉敏子さんの渡米のニュースでジャズピアノをはじめ
フリージャズで、音楽への広い間口を得ることができた
オープン当初に出演する機会があり その後、バークリー音楽院に行く
佐藤良武(以下佐藤):佐藤允彦さんとは、本当に長い付き合いになりますね。
佐藤允彦(以下允彦):そうですね新宿ピットインが開店してすぐに出演しましたから。
佐藤:僕は允彦さんの4つも下ですよ。大学でいうと1年と4年。神様と下僕みたいなもんです(笑)
允彦:何言っているんですか。クラブのオーナーとプレーヤーというのは、やっぱり神様と……。最近のクラブのオーナーは、みんなそのノリ。新人が出たいというと、音楽の内容は関係なく、客を何人以上呼べるなら、出してやると。ほとんどそうです。
佐藤:ひとバンドを10人ノルマで、3つ出すと30人くらい集まる。まず売り上げありきなんですよ。でもほんとうは逆ですよ。そんなことはピットインは一切やっていない。あくまでミュージシャンにお任せするというのが私の理念。ステージはミュージシャンにまかせて、客を入れるのは私の仕事です。
允彦:今どき、そんな人はいないですよ。それを40年間やってきたということが凄いです。
佐藤:ミュージシャンのやることは尊敬もしているし、何をおやりになろうが、“どうぞやってください”という姿勢でやってきました。僕は一切何も言わなかったです(笑)。允彦さんは、ピットインへの出演は早かったですよね?
允彦:出演したのは本当に最初の頃ですよ。サックスは宮沢昭さん、ベースは寺川正興さん。僕はバークリーに66年に行きましたから、その前です。オープンしてすぐですね。
佐藤:ちょうど新宿にジャズがやってきた時ですね。66年になりますね。ところで、ピアノはいくつくらいからはじめたんですか?
允彦:ピアノは5歳から。たまたま家にピアノがあって、それを弾かされていました。先生についてレッスンもやっていましたね。ジャズピアノは高校1年の時くらいからかな。我が家は終戦になって没落が始まる。それでいよいよどん底になったのは高校1年の時です。その、3、4年前に秋吉敏子さんがアメリカに行ったという記事が出ていて。お袋がジャズっていうのをやると、アメリカにも行けるのね、と。ジャズのピアノをやっていれば食えるな、という発想(笑)。それでジャズをやれっ、てことになって……。それまで、ジャズのジャの字も知らなかった。
佐藤:バークリー音楽院に行ったのは秋吉さんが最初ですよね。その後に渡辺貞夫さん。
允彦:そうですね。その次が荒川康男さん。その次の年に僕が行ったんです。荒川さんは、はスタジオミュージシャンをやっていて、当時スタジオ界の売れっ子だった。テレビコマーシャルとか、いろんなレコード会社の録音とか、荒川さん、僕、それにドラムの原田寛治さんのトリオで回っていて、けっこうお金を稼いでいて、お金が貯まったから、行くよって……。僕は66年8月に渡米しましたから、その間にピットインには何回か出ています。
佐藤:当時の印象は覚えてますか?
允彦:景色は覚えています。部屋は縦型で、アップライトのピアノで……。
佐藤:そうそう。40席しかなかった。その後、貞夫さんが帰国して66年から出演しはじめた。貞夫さんが、アップライトじゃだめだよ、グランドピアノじゃなきゃ、って。このエピソードは前に話しましたね。
当時のジャズの状況と情勢と合致しニュージャズホールでフリーを展開
允彦:それと、ピットインとは別に開店した新宿ニュージャズホールにはずいぶんお世話になりました。アメリカから帰ってきてからですから69年です。あそこは、何で始まったんですか?
佐藤:中華屋さんが入っていたんですけど、経営ができなってくて出て行ったんです。その後に、スペースが空いていて、なんかやろうと。商売じゃなくて、ミュージシャンに演奏できる場所を提供した。その頃フリージャズはあまりやっていなくて、そういう意味では允彦さんが走りですね。
允彦:僕より富樫雅彦さんでしょう。あとは高柳昌行さん。富樫さんは、前から知っていました。僕がアメリカから帰ってきて、歌舞伎町の「タロー」で、荒川さんとデュオの演奏をしていた。そこに富樫さんがふらっと入ってきて、俺もやらせてくれよと。それでトリオになったんです。富樫さんがふた言目には、「ねえ、フリーやろうよ」って言うんですよ。そして、フリーを始めた頃に、富樫さんが事故で、入院しちゃった。
佐藤:富樫さんとやる前はフリーをやっていなかったんですか?
允彦:曲をやる時、その中のあるパートでフリーをやって、またなんかのきっかけで元に戻る、って感じのことはやっていました。富樫さんが倒れてしまって、トリオはなくなった。一人でやっていた時に、ニュージャズホールができて、そこで実験的なことをやりました。そのころは高木元輝とか沖至とか……。
佐藤:僕は、沖さんがバケツに水を張って、トランペットをブクブクやっているのを若い時に見て、ああジャズって芸術なんだと思いましたよ(笑)。その頃から、ミュージシャンのやることは、尊敬していますし、決して間違いじゃないと思っています。
允彦:佐藤さんは心が広いんですよ。
佐藤:パラジウムを作ったのはいつですか?
允彦:69年ですね。アメリカから帰ってきてトリオになってすぐ。タローで声がかかって演奏をするようになってから、当時スイングジャーナルの編集長だった児山紀芳さんが“録音しないか”っていって、東芝でレコードを作りました。当時、ニュージャズホールではタージ・マハル旅行団とか、生活向上委員会とか演っていて。裸になって水をぶちまけたり……。
佐藤:その時代の新宿は熱かった。1966年から69年あたりは、エネルギーが貯まっていた。それが爆発したのが69年の秋の新宿騒乱です。
允彦:山下洋輔さんのトリオは、支持されていた。あれは凄かった。
佐藤:山下さんがフリーをはじめたきっかけは当日にベースがいなくなって、しょうがないので二人でやろうと。やったら本人が一番面白くて。ちょうど、安保の学生がピットインにどさっと来た時期です。「体制をぶっ壊せ」という山下さんの言葉に合ったんでしょう。
允彦:ちょうど社会的なうねりとぴったり合ったんです。音楽と社会情勢、世界情勢は合致することが多いんです。
佐藤:音楽というのはそういう運命のものなんですよ。
「ピットイン」ではいつも真剣勝負。
ここでしかできない音楽もあり 新しいものにもチャレンジできる。
僕のホームグランドと呼べる場所
ピットインは厳しく心構えが違う まさに真剣勝負の場で甘くはない
允彦:僕らがフリーをやろうというのは、あの頃、ジャズのピークが過ぎて、世界中でちょうど変わり目だった。そんなことを感じて、いまさらビ・バップやってどうなのか、とか。僕らも、富樫さんが復帰した後に、高木元輝とか沖至とか入れて、ピットインに出演するでしょう。今では考えられないほど満タンなんですよ。今日は休憩を入れないで、全部ブッ通しでやるので、好きなときに出入りしてください、とか言って7時から11時くらいまで……。そんなこともやりました。富樫さんとやる場合、最初は試行錯誤の連続でしたね。必死に、あっちは何を考えているんだろう、どうなっているだろう、とかいつも壁にぶち当たる状態でした。そういう中から、お互いの方法論とか、どうやったら呼吸が読めるかとか、自分が閃いたモチーフをどうやって発展していくかとか、どこで切るかとか。そんな経験をお互いしたんじゃないのかな。
ようやく入り口がみえてきたかな、と思ったのは1980年くらい。そういうのが見えてくると、いろんなミュージシャンが来て、いろんなことをやっても、けっこう交流ができる。ある種、完全即興の自分なりの方法論が見つかってきた。音楽の考えの経路がいっぱい見えるようになってきた。そうすると、普通のアレンジするにしても作曲の時にも、ものすごく役に立つ。この広い引き出しはフリーからもらったものです。フリーは反省ができないリアルタイムコンポジション、と僕は感じています。
佐藤:演る方にはたまらないですよね。同じ時はないんだから。
允彦:だから普通に食事をして酒を飲んで、女の子を口説くような場所では、フリーなんかは絶対できない。できるのはピットインだけ。僕らもピットインに出る時は心構えが違いますよね。相当、真剣勝負って感じです。
佐藤:すべてのミュージシャンがそういってくれますね。お客さんとも真剣勝負だし。
允彦:お客も耳が肥えています。厳しい時は厳しい。そういう場があるということは、尊いことなんです。もし、ピットインがなくなっちゃったら、日本のジャズの状況が変わっちゃうでしょうね。なんか生ぬるい感じに……。
佐藤:だから、やめるにやめられない(笑)。ここはミュージシャン全体がつくり上げた場。私は単に場所を提供しているだけなんです。もう私の一存ではどうにもならない世界に入っています(笑)。
允彦:場所が人格をもっちゃった。いわゆるそれが文化なんですよ。
佐藤:お客さんもそれを期待してくる。ミュージシャンもそれに真剣に答えなければならない。そのへんのクラブとはぜんぜん違いますよ。どんどん進化していますから。
允彦:未だに何かを生み出していかなければらないと思っています。だからホームグランド的に考えているんだけど、アウェイのように厳しいという面があって、安心はできない。あまっちょろいことをやったら、バシッと飛んでくるという感じでいつも演っている。
允彦さんの平等な精神の影響を受けここまで40年以上やってきた
佐藤:自分からすれば、ミュージシャンのやることを尊敬していますし、日本の宝だと思っています。そういう意味では、皆さん平等に扱っているということなんですが、平等というのはすごく難しい。実は僕は允彦さんの影響をすごく受けているんですよ。ジャズ界の仕組みは割と封建的な部分あって、そうエルヴィン・ジョーンズもそうでしたが、バンドマスターが絶対なんですよ。メンバーもそう思っている。エルヴィンが演奏旅行に出る時は、彼は飛行機で行く、メンバーはバスとか電車で行くというのが、あたり前の世界。日本にもそういう風習があった気がします。バンマスが一番偉い。バンドが演奏してギャラを得ますよね。その時に、まずバンマスが一番多く取って、他のメンバーにその他を配分する。それが当たり前という人が多かった。
僕もそういうものだと思っていて、ある時、允彦さんの演奏が終わって、ギャランティして、允彦さんのギャランティが少し多くて。その時に、「良武さん、なんで僕が多くて他のメンバーが少ないのよ」と言われた時にハッとしたんです。それが平等の気持ちなんですよ。
允彦:確かに僕のバンドはみんなそうなんですよ。移動も同じ席で行く。
佐藤:その時、平等という考えに共感したんです。要するにリベラルというか。その影響は受けました。それから、ミュージシャンと相談して、ギャランティはバンマスに渡すことにしました。68年くらいのこと。允彦さんの凄さは謙虚な凄さなんです。僕が以後40年間やっていく上で、ミュージシャンにとって平等に、というきっかけになっている。ただし、富樫さんだけは、移動に大変でしたから、そう意味で皆に支えられていましたね。音楽的にも場所はピットインしかない。だから、誠心誠意やってきました。
允彦:富樫さんは幸せだったと思いますよ。ピットインがあって。
佐藤:この12月8、9日に富樫さんの追悼コンサートがあるんです。ピットインで追悼コンサートをやるという時は、いつも允彦さんが陣頭指揮をとっていただいて。2000年以来、トコ(日野元彦)ちゃんもそうですし、コルゲン(鈴木宏昌)さんも。允彦さんがその時、決まって言う言葉は「俺ももうすぐですから」と(笑)。允彦さんの人柄、平等という考え方は何よりも大切だと思います。
允彦:というより、音楽は自分一人でできるわけじゃないから、録音したりする時もエンジニアがいて、はじめて録音できる訳です。いっぱい自分の音を聴いてもらう状態にするために、何人の裏の人がいるか。ピットインだっていますよね。
佐藤:その通りです。
允彦:それで最近は、どんどん周りが死んじゃうんでね、しょうがないから最近はコンピューターにいろんな音を入れて、好き勝手に音が出るようにしておいて、それに合わせて僕がピアノを弾くということやっています。どんどんそれが多くなってくる気がします。ランダムに音が出てくるプログラムを作って。フリーじゃないですか。二度と同じことをしないわけだし。でも、いまのところ一方通行。いま、こっちがやってたことで、PCの音も影響されるプログラムを考えています。この前ピットインでもやったんですよ。どうしてもドラムがいなくて、ベースとデュオで、コンピューター持ってきて音を走らせて、ベースとピアノと。
佐藤:とにかく思い立ったら、すぐにピットインでやってほしいですね(笑)。そういえば、六本木ピットインにかなり出ていましたよね。
允彦:僕は六本木でランドゥーガという団体を1年間やらせてもらいました。けっこう大人数でした。それとかメディカル・シュガー・バンク(MSB)というのもやりました。シンセサイザーを持ち込んで、当時のフュージョンですね。
佐藤:六本木ピットインは77年から27年間やりました。最初は新宿のままを持ち込んだら、ぜんぜんだめで、閉めて帰ろうと思ったら、たまたまリー・リトナーが来て、大入りになった。それで、フュージョンの店にドーンと切り換えました。4ビートの新宿、8ビートの六本木が定着したんです。
允彦:当時、鈴木宏昌さんはザ・プレーヤーズ。六本木がホームグランドでした。僕らは同じ時期にMSBとしてアルバムを出しました。
佐藤:ピットインの長い歴史の中で、新宿と六本木の両方で演奏ができたミュージシャンは少ないんです。
允彦:僕のアルバムで最近再発された「ダブル・エクスポージャー」というCDがあって、スティーヴ・ガッドとエディ・ゴメスのトリオ。六本木ピットインでのライブ録音でした。上にソニーの六本木スタジオがあってマルチケーブルを引いて、伊藤八十八さんがテープ持ってくれば、録れるって。それで録音した。これは4ビートでしたね。
佐藤:当時のその録音ができる環境が頭にあって、今年スタジオ・ピットインをオープンした時にマルチのケーブルを引いて、ライブを録れるようにしてあるんです。
允彦:六本木ピットインというのは、僕の中でも重要なものです。エレクトリックといっても意識は同じ。同時に4ビートのバンドもやっていましたから。また、佐藤さんにあのくらいのライブハウスを作ってほしでいですね(笑)。
(第6回に続く)
インタビュー・文 田中伊佐資
構成 「季刊・analog」樫出
写真 田代法生
佐藤允彦さん(ジャズピアニスト、作・編曲家) プロフィール

1941年東京生まれ。慶応義塾大学卒業後、1966年から1968年にかけて米国バークリー音楽院に留学、作・編曲を学ぶ。帰国後、1969年に初のリーダーアルバム『パラジウム』でスイングジャーナル誌「日本ジャズ賞」受賞。その後も、ビッグバンドのための作品『四つのジャズコンポジション』(1970年)、『邪馬台賦』(1972年)で二度の芸術祭優秀賞を受賞する。これまでに数多くのリーダーアルバムを発表しており、スティーヴ・ガッド(Ds)、エディ・ゴメス(B)のトリオでレコーディングした『アモーフィズム』の全米発売や、“セレクト・ライブ・アンダー・ザ・スカイ '90”で誕生した『ランドゥーガ』(スイングジャーナル誌「日本ジャズ賞」受賞)のフランスでのリリースなど、国際的にも高い評価を得ている。また、ベルリン、ドナウエッシンゲン、メールス、モントルー、イースト・ミーツ・ウエスト・イン・ニューヨークなどのジャズ・フェスティバルへの出演や、アフリカ、オーストラリア、ロシア、中南米などへのコンサート・ツアーと、国内に止まらない広範な活動は常に注目を集めている。作・編曲家としては、ナンシー・ウイルソン、アート・ファーマー、ヘレン・メリル、中川昌三、伊藤君子、宮本文昭を始めとする多数アーティストのレコーディングへの参加や、『オーケストラと三人のインプロヴァイザーのための「乱紋」』(1987年)、『WAVE IIIとオーケストラのためのコンチェルト』(1988年)などの実験的作品、「万国博覧会〜地方自治体館」(1970年)、「花と緑の博覧会〜JT館」(1990年)などのパビリオン音楽、リチャード・デューセンバーグIII世の筆名での〈ベルエア・ストリングス・シリーズ〉などを手掛けている。さらに、テレビ番組、映画、コマーシャルの分野での活躍も有名である。最近では、日本武道館に1000人の僧侶を集めて開催した声明コンサート“千僧音曼荼羅〜BUDDHIST MUSIC with 1000 Shomyo Voices”(1993年)において、作・編曲に加えて音楽監督も担当し、多大な評価を受けた。1997年には、自己のプロデュース・レーベル<BAJ Records>を創設、その活躍はますます多面化している。
本記事は「季刊・analog」にて好評連載中です。「analog」の購入はこちらから
秋吉敏子さんの渡米のニュースでジャズピアノをはじめ
フリージャズで、音楽への広い間口を得ることができた
オープン当初に出演する機会があり その後、バークリー音楽院に行く
佐藤良武(以下佐藤):佐藤允彦さんとは、本当に長い付き合いになりますね。
佐藤允彦(以下允彦):そうですね新宿ピットインが開店してすぐに出演しましたから。
佐藤:僕は允彦さんの4つも下ですよ。大学でいうと1年と4年。神様と下僕みたいなもんです(笑)
允彦:何言っているんですか。クラブのオーナーとプレーヤーというのは、やっぱり神様と……。最近のクラブのオーナーは、みんなそのノリ。新人が出たいというと、音楽の内容は関係なく、客を何人以上呼べるなら、出してやると。ほとんどそうです。
佐藤:ひとバンドを10人ノルマで、3つ出すと30人くらい集まる。まず売り上げありきなんですよ。でもほんとうは逆ですよ。そんなことはピットインは一切やっていない。あくまでミュージシャンにお任せするというのが私の理念。ステージはミュージシャンにまかせて、客を入れるのは私の仕事です。
允彦:今どき、そんな人はいないですよ。それを40年間やってきたということが凄いです。
佐藤:ミュージシャンのやることは尊敬もしているし、何をおやりになろうが、“どうぞやってください”という姿勢でやってきました。僕は一切何も言わなかったです(笑)。允彦さんは、ピットインへの出演は早かったですよね?
允彦:出演したのは本当に最初の頃ですよ。サックスは宮沢昭さん、ベースは寺川正興さん。僕はバークリーに66年に行きましたから、その前です。オープンしてすぐですね。
佐藤:ちょうど新宿にジャズがやってきた時ですね。66年になりますね。ところで、ピアノはいくつくらいからはじめたんですか?
允彦:ピアノは5歳から。たまたま家にピアノがあって、それを弾かされていました。先生についてレッスンもやっていましたね。ジャズピアノは高校1年の時くらいからかな。我が家は終戦になって没落が始まる。それでいよいよどん底になったのは高校1年の時です。その、3、4年前に秋吉敏子さんがアメリカに行ったという記事が出ていて。お袋がジャズっていうのをやると、アメリカにも行けるのね、と。ジャズのピアノをやっていれば食えるな、という発想(笑)。それでジャズをやれっ、てことになって……。それまで、ジャズのジャの字も知らなかった。
佐藤:バークリー音楽院に行ったのは秋吉さんが最初ですよね。その後に渡辺貞夫さん。
允彦:そうですね。その次が荒川康男さん。その次の年に僕が行ったんです。荒川さんは、はスタジオミュージシャンをやっていて、当時スタジオ界の売れっ子だった。テレビコマーシャルとか、いろんなレコード会社の録音とか、荒川さん、僕、それにドラムの原田寛治さんのトリオで回っていて、けっこうお金を稼いでいて、お金が貯まったから、行くよって……。僕は66年8月に渡米しましたから、その間にピットインには何回か出ています。
佐藤:当時の印象は覚えてますか?
允彦:景色は覚えています。部屋は縦型で、アップライトのピアノで……。
佐藤:そうそう。40席しかなかった。その後、貞夫さんが帰国して66年から出演しはじめた。貞夫さんが、アップライトじゃだめだよ、グランドピアノじゃなきゃ、って。このエピソードは前に話しましたね。
当時のジャズの状況と情勢と合致しニュージャズホールでフリーを展開
允彦:それと、ピットインとは別に開店した新宿ニュージャズホールにはずいぶんお世話になりました。アメリカから帰ってきてからですから69年です。あそこは、何で始まったんですか?
佐藤:中華屋さんが入っていたんですけど、経営ができなってくて出て行ったんです。その後に、スペースが空いていて、なんかやろうと。商売じゃなくて、ミュージシャンに演奏できる場所を提供した。その頃フリージャズはあまりやっていなくて、そういう意味では允彦さんが走りですね。
允彦:僕より富樫雅彦さんでしょう。あとは高柳昌行さん。富樫さんは、前から知っていました。僕がアメリカから帰ってきて、歌舞伎町の「タロー」で、荒川さんとデュオの演奏をしていた。そこに富樫さんがふらっと入ってきて、俺もやらせてくれよと。それでトリオになったんです。富樫さんがふた言目には、「ねえ、フリーやろうよ」って言うんですよ。そして、フリーを始めた頃に、富樫さんが事故で、入院しちゃった。
佐藤:富樫さんとやる前はフリーをやっていなかったんですか?
允彦:曲をやる時、その中のあるパートでフリーをやって、またなんかのきっかけで元に戻る、って感じのことはやっていました。富樫さんが倒れてしまって、トリオはなくなった。一人でやっていた時に、ニュージャズホールができて、そこで実験的なことをやりました。そのころは高木元輝とか沖至とか……。
佐藤:僕は、沖さんがバケツに水を張って、トランペットをブクブクやっているのを若い時に見て、ああジャズって芸術なんだと思いましたよ(笑)。その頃から、ミュージシャンのやることは、尊敬していますし、決して間違いじゃないと思っています。
允彦:佐藤さんは心が広いんですよ。
佐藤:パラジウムを作ったのはいつですか?
允彦:69年ですね。アメリカから帰ってきてトリオになってすぐ。タローで声がかかって演奏をするようになってから、当時スイングジャーナルの編集長だった児山紀芳さんが“録音しないか”っていって、東芝でレコードを作りました。当時、ニュージャズホールではタージ・マハル旅行団とか、生活向上委員会とか演っていて。裸になって水をぶちまけたり……。
佐藤:その時代の新宿は熱かった。1966年から69年あたりは、エネルギーが貯まっていた。それが爆発したのが69年の秋の新宿騒乱です。
允彦:山下洋輔さんのトリオは、支持されていた。あれは凄かった。
佐藤:山下さんがフリーをはじめたきっかけは当日にベースがいなくなって、しょうがないので二人でやろうと。やったら本人が一番面白くて。ちょうど、安保の学生がピットインにどさっと来た時期です。「体制をぶっ壊せ」という山下さんの言葉に合ったんでしょう。
允彦:ちょうど社会的なうねりとぴったり合ったんです。音楽と社会情勢、世界情勢は合致することが多いんです。
佐藤:音楽というのはそういう運命のものなんですよ。
「ピットイン」ではいつも真剣勝負。
ここでしかできない音楽もあり 新しいものにもチャレンジできる。
僕のホームグランドと呼べる場所
ピットインは厳しく心構えが違う まさに真剣勝負の場で甘くはない
允彦:僕らがフリーをやろうというのは、あの頃、ジャズのピークが過ぎて、世界中でちょうど変わり目だった。そんなことを感じて、いまさらビ・バップやってどうなのか、とか。僕らも、富樫さんが復帰した後に、高木元輝とか沖至とか入れて、ピットインに出演するでしょう。今では考えられないほど満タンなんですよ。今日は休憩を入れないで、全部ブッ通しでやるので、好きなときに出入りしてください、とか言って7時から11時くらいまで……。そんなこともやりました。富樫さんとやる場合、最初は試行錯誤の連続でしたね。必死に、あっちは何を考えているんだろう、どうなっているだろう、とかいつも壁にぶち当たる状態でした。そういう中から、お互いの方法論とか、どうやったら呼吸が読めるかとか、自分が閃いたモチーフをどうやって発展していくかとか、どこで切るかとか。そんな経験をお互いしたんじゃないのかな。
ようやく入り口がみえてきたかな、と思ったのは1980年くらい。そういうのが見えてくると、いろんなミュージシャンが来て、いろんなことをやっても、けっこう交流ができる。ある種、完全即興の自分なりの方法論が見つかってきた。音楽の考えの経路がいっぱい見えるようになってきた。そうすると、普通のアレンジするにしても作曲の時にも、ものすごく役に立つ。この広い引き出しはフリーからもらったものです。フリーは反省ができないリアルタイムコンポジション、と僕は感じています。
佐藤:演る方にはたまらないですよね。同じ時はないんだから。
允彦:だから普通に食事をして酒を飲んで、女の子を口説くような場所では、フリーなんかは絶対できない。できるのはピットインだけ。僕らもピットインに出る時は心構えが違いますよね。相当、真剣勝負って感じです。
佐藤:すべてのミュージシャンがそういってくれますね。お客さんとも真剣勝負だし。
允彦:お客も耳が肥えています。厳しい時は厳しい。そういう場があるということは、尊いことなんです。もし、ピットインがなくなっちゃったら、日本のジャズの状況が変わっちゃうでしょうね。なんか生ぬるい感じに……。
佐藤:だから、やめるにやめられない(笑)。ここはミュージシャン全体がつくり上げた場。私は単に場所を提供しているだけなんです。もう私の一存ではどうにもならない世界に入っています(笑)。
允彦:場所が人格をもっちゃった。いわゆるそれが文化なんですよ。
佐藤:お客さんもそれを期待してくる。ミュージシャンもそれに真剣に答えなければならない。そのへんのクラブとはぜんぜん違いますよ。どんどん進化していますから。
允彦:未だに何かを生み出していかなければらないと思っています。だからホームグランド的に考えているんだけど、アウェイのように厳しいという面があって、安心はできない。あまっちょろいことをやったら、バシッと飛んでくるという感じでいつも演っている。
允彦さんの平等な精神の影響を受けここまで40年以上やってきた
佐藤:自分からすれば、ミュージシャンのやることを尊敬していますし、日本の宝だと思っています。そういう意味では、皆さん平等に扱っているということなんですが、平等というのはすごく難しい。実は僕は允彦さんの影響をすごく受けているんですよ。ジャズ界の仕組みは割と封建的な部分あって、そうエルヴィン・ジョーンズもそうでしたが、バンドマスターが絶対なんですよ。メンバーもそう思っている。エルヴィンが演奏旅行に出る時は、彼は飛行機で行く、メンバーはバスとか電車で行くというのが、あたり前の世界。日本にもそういう風習があった気がします。バンマスが一番偉い。バンドが演奏してギャラを得ますよね。その時に、まずバンマスが一番多く取って、他のメンバーにその他を配分する。それが当たり前という人が多かった。
僕もそういうものだと思っていて、ある時、允彦さんの演奏が終わって、ギャランティして、允彦さんのギャランティが少し多くて。その時に、「良武さん、なんで僕が多くて他のメンバーが少ないのよ」と言われた時にハッとしたんです。それが平等の気持ちなんですよ。
允彦:確かに僕のバンドはみんなそうなんですよ。移動も同じ席で行く。
佐藤:その時、平等という考えに共感したんです。要するにリベラルというか。その影響は受けました。それから、ミュージシャンと相談して、ギャランティはバンマスに渡すことにしました。68年くらいのこと。允彦さんの凄さは謙虚な凄さなんです。僕が以後40年間やっていく上で、ミュージシャンにとって平等に、というきっかけになっている。ただし、富樫さんだけは、移動に大変でしたから、そう意味で皆に支えられていましたね。音楽的にも場所はピットインしかない。だから、誠心誠意やってきました。
允彦:富樫さんは幸せだったと思いますよ。ピットインがあって。
佐藤:この12月8、9日に富樫さんの追悼コンサートがあるんです。ピットインで追悼コンサートをやるという時は、いつも允彦さんが陣頭指揮をとっていただいて。2000年以来、トコ(日野元彦)ちゃんもそうですし、コルゲン(鈴木宏昌)さんも。允彦さんがその時、決まって言う言葉は「俺ももうすぐですから」と(笑)。允彦さんの人柄、平等という考え方は何よりも大切だと思います。
允彦:というより、音楽は自分一人でできるわけじゃないから、録音したりする時もエンジニアがいて、はじめて録音できる訳です。いっぱい自分の音を聴いてもらう状態にするために、何人の裏の人がいるか。ピットインだっていますよね。
佐藤:その通りです。
允彦:それで最近は、どんどん周りが死んじゃうんでね、しょうがないから最近はコンピューターにいろんな音を入れて、好き勝手に音が出るようにしておいて、それに合わせて僕がピアノを弾くということやっています。どんどんそれが多くなってくる気がします。ランダムに音が出てくるプログラムを作って。フリーじゃないですか。二度と同じことをしないわけだし。でも、いまのところ一方通行。いま、こっちがやってたことで、PCの音も影響されるプログラムを考えています。この前ピットインでもやったんですよ。どうしてもドラムがいなくて、ベースとデュオで、コンピューター持ってきて音を走らせて、ベースとピアノと。
佐藤:とにかく思い立ったら、すぐにピットインでやってほしいですね(笑)。そういえば、六本木ピットインにかなり出ていましたよね。
允彦:僕は六本木でランドゥーガという団体を1年間やらせてもらいました。けっこう大人数でした。それとかメディカル・シュガー・バンク(MSB)というのもやりました。シンセサイザーを持ち込んで、当時のフュージョンですね。
佐藤:六本木ピットインは77年から27年間やりました。最初は新宿のままを持ち込んだら、ぜんぜんだめで、閉めて帰ろうと思ったら、たまたまリー・リトナーが来て、大入りになった。それで、フュージョンの店にドーンと切り換えました。4ビートの新宿、8ビートの六本木が定着したんです。
允彦:当時、鈴木宏昌さんはザ・プレーヤーズ。六本木がホームグランドでした。僕らは同じ時期にMSBとしてアルバムを出しました。
佐藤:ピットインの長い歴史の中で、新宿と六本木の両方で演奏ができたミュージシャンは少ないんです。
允彦:僕のアルバムで最近再発された「ダブル・エクスポージャー」というCDがあって、スティーヴ・ガッドとエディ・ゴメスのトリオ。六本木ピットインでのライブ録音でした。上にソニーの六本木スタジオがあってマルチケーブルを引いて、伊藤八十八さんがテープ持ってくれば、録れるって。それで録音した。これは4ビートでしたね。
佐藤:当時のその録音ができる環境が頭にあって、今年スタジオ・ピットインをオープンした時にマルチのケーブルを引いて、ライブを録れるようにしてあるんです。
允彦:六本木ピットインというのは、僕の中でも重要なものです。エレクトリックといっても意識は同じ。同時に4ビートのバンドもやっていましたから。また、佐藤さんにあのくらいのライブハウスを作ってほしでいですね(笑)。
(第6回に続く)
インタビュー・文 田中伊佐資
構成 「季刊・analog」樫出
写真 田代法生
佐藤允彦さん(ジャズピアニスト、作・編曲家) プロフィール

本記事は「季刊・analog」にて好評連載中です。「analog」の購入はこちらから
関連リンク
トピック