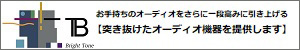異例とも言えるこだわりを凝縮した作品
UNAMASレーベル、ジャズ・ピアニストのユキ・アリマサによるクラシック作品『Dimentions』を配信開始
沢口音楽工房は、同社が展開するUNAMASレーベルの最新作となるユキ・アリマサ『Dimensions』を6月17日にリリースした。e-onkyo music(配信ページ)とHQM store(配信ページ)にて、2ch/5.0chで配信される。
UNAMASレーベルは、響きに定評ある軽井沢・大賀ホールにてレコーディングを行った「クラシック・シリーズ」をリリースしてきた。『Dimensions』はその第4作目にあたり、同レーベルが大賀ホールで行った録音としては初のピアノソロ・アルバムとなる。ここ数年のUNAMASは、クラシック・シリーズを年1回でリリースしていたが、本作は前作から2ヶ月足らずでのリリースとなった。
今回主役となるYuki Arimasa(ユキ・アリマサ)は、バークリー音楽大学を卒業後、同校にて助教授として教鞭を取るなど日本人としては稀有な実績を持つジャズピアニストだ。最大の特徴はオリジナリティにあり、ユキ・アリマサのスタイルは海外のジャズシーンからも高い評価を得ている。
しかし、ユキ・アリマサが今回『Dimensions』でプレイするのは、ジャズではなくクラシックの楽曲だ。バッハやベートーヴェン、ドビュッシーの楽曲に加え、自身のフェイバリットとなるGleen Sleevesの合計7曲が収録された本作は、「クラシック・シリーズ」にありながら、“ユキ・アリマサのジャズというフィルターを通したクラシック”が堪能できるユニークなアルバムとなっている。
リリースに先駆けた発表会には、レーベル代表でありレコーディングエンジニアである沢口"Mick"真生氏が登場。「UNAMASでは、"Art"、"Technology"、"Engineering"の融合を標榜してきましたが、これまでにも増してそれらの要素を実現できました」とその仕上がりを振り返る。
■スタインウェイ銘機の響きを余すことなく収録することを目指す
本作は、自らを「ジャズ屋」とする沢口氏にとって真骨頂ともいえる録音となったのではないだろうか。『Dimensions』のテーマは、大枠では過去のシリーズ3作品と同様だが、本作ならではのアプローチも見逃せない。
何よりも本作を象徴するのが、"Art"の部分だ。今回、ユキ・アリマサが使用したピアノは、スタインウェイの銘機として名高いD274。その中でも、20世紀における最重要ピアニストとして名高いアルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリが最も愛したという個体「NO427700」を弾いている。
録音当日に調律を行った調律師は、「スタインウェイのピアノは長時間弾いていると、演奏者に寄り添っていく他にはないピアノ」と語っていた。収録の際も、「焦ってすぐに録音しないで、2時間くらいはユキさんに弾かせて欲しい、と言われました」(沢口氏)のだという。
「こうした点も含めて“見えないアート”がスタインウェイにはあるんじゃないかな、と思います」と沢口氏が話すことからも分かるとおり、この“Art”の根底をなすスタインウェイ D274の響きこそが『Dimensions』の大きな聴きどころとなる。
■沢口氏ならではのマイキングでホールの響きまで再現
この"Art"を実現する上で、重要になるのが“Technology”と“Engineering”だ。
“Engineering”の要素を象徴するのが、沢口氏が今回採用した独特なマイキングだ。平面を構成する5chのメインマイクには、それぞれノイマンのデジタルマイクKM 133Dを使用。極めて高い解像度の音が録音できるとして昨今注目を集めつつあるデジタルマイクだ。沢口氏はLch、Rchでメインの音を捉えたうえで、さらにピアノの最低域の弦を狙ってセンターchのマイクを配置した。
これは「ピアノは2本で録ると周波数によって左右に振れてしまうのですが、センターchをこうしてセッティングすることで、音が安定してくるのです」(沢口氏)という意味でセッティングされたものだ。
また、100kHzまでフラットに伸びた特性を持つことで定評あるサンケンのCO-100Kを用いたハイトリアL/Rchのマイクと、フロントハイトL/Rchに使用したKM-133Dは、全て客席へ向けてセッティングされている。
「これはエンジニアリングの学校の教科書とは全然違うマイキングですが、あえてこうしています。大賀ホールは、ステージから客席に飛んで行く音がすごく“見える”場所です。特にピアノは非常にパルシブな楽器なので、ピアノと大賀ホールが共鳴するさまを捉えるためには音が飛ぶ方向へ向けた方が良い結果だったんです」と沢口氏はその理由を解説する。
一見すると、9chがそのまま各chにアサインされたシンプルなマイキングだが、セオリーとは大きく異なるアプローチをとった背景には、沢口氏がこれまで取り組んできたイマーシブ(没入感のある)・サラウンドへの経験とノウハウが行かされているのだ。
こうしたマイキングによる結果は、発表会で聴くことができた9chサラウンド再生で体験できた。ピアノから音が飛び出し、ホールへ拡散し、そしてリスナーの耳に入る。その響きが決して混濁することなく、ひとつひとつの音の輪郭を伴って混じりあうさまは、まさに半球面で構成されるイマーシブ・サラウンドの真骨頂だ。
もちろん本作は2chでもリリースされているが、最初から2chをターゲットとするのではなく9chの情報量をベースに組み上げたからこそ完成した2chとしてのメリットは想像以上に大きいことも注目すべき点のひとつだ。
■調音から電源対策まで徹底したサウンドチューニングを実施
そして最後のテーマとなるのが、“Technology”だ。4月にUNAMASレーベルからリリースされた『Death and The maiden』でも注目された徹底的なサウンドチューニングは、本作『Dimensions』でも引き続き採用されている。
前述のとおり、沢口氏は本作で「ピアノの響き」を強く意識している。響きは“鳴り”があってこそ成り立つもので、響きを生み出すピアノをいかに鳴らすかは、本作にとって重要な意味を持っていた。
ピアノが置かれるステージの床には、アコースティック・リヴァイブ製のチューニングキットを活用。ステージそのものが発する低域のノイズを除去するべく水晶クォーツレゾネーターを使用したことに加え、同社製のヒッコリーボードをピアノの下にインシュレーター的に使用するなど、徹底したアイソレーションが行われている。
さらにピアノの下にも同社の拡散板RWL-3を使用していることも注目したい。「ピアノの下は、本当は色々な音がしているのですが、それらは均一ではないので、拡散板を使用しています。音響ハウスで拡散パネルの有り無しをユキさんと実験した際、パネルあるの方がよい結果だったのです」と沢口氏が話すとおり、ここにも同氏の経験に基づくノウハウが採用されている。
そして、響きの要素を大きく左右するのが音楽信号そのもののS/Nだ。電源はエリーパワー製のバッテリー電源「POWER YIILE」を使用。今回マイクプリとして用いたRME「DMC-842M」および「Micstacy」用となるステージ側と、コントロールルームで使用された「MADIface XT」および「Pyramix」用に1台ずつ、合計2台を使った“オールバッテリー・ドライブ”の環境下レコーディングが進められている。
さらに見逃せないのが、『Death and the maiden』の収録時と同じく徹底したEMCノイズの除去だ。このEMCノイズ対策についてはJIONの宮下清孝氏が担当しており、ノイズを抑えながらも音を痩せさせないことを狙った対策が行われている。今回はさらに対策が強化されたことにも注目で、ファインメットの活用やクリーン電源の導入など、録音環境としては異例と言える電源対策行われた。
こうした取り組みの結果は、何よりも『Dimensions』に収録されたユキ・アリマサが弾くスタインウェイの音によく現れている。
オペラ劇場で録音された不朽の名作として名高いキース・ジャレットの『ケルン・コンサート』をレファレンスディスクとして使用しているオーディオファイルは多いと思うが、『Dimensions』にはそれを彷彿とさせるものがある。
もちろんユキ・アリマサとキース・ジャレットは全く異なるタイプのピアニストだが、この二人を結びつけるのは、静寂から立ち上がるピアノのパルシブな音色や広い空間に拡散される響き、そして何よりもエモーショナルな起伏である。このエモーションを考えられる限り現代最先端のアプローチで収録した本作は、まさにユキ・アリマサの個性と沢口氏の感性の化学反応によって生まれた音源と言える。
なお、本作のライナーノーツは、かつてドルビージャパンの代表を務めた伏木雅昭氏によるもの。音楽的なアプローチや、伏木氏だからこそのサウンド面での解説も、最先端のレコーディングに秘められた可能性を存分に知ることができる内容となっている。
現時点でのリリースは、前述のとおり2chと5.0chのみとなっており、9chサラウンドはリスニング環境の問題もありリリースは未定。そのかわり、ヘッドフォン環境で9chサラウンドを再現する「HPL9」での制作が進められており、こちらも近日リリースへ向けて準備が進められている。
UNAMASレーベルは、響きに定評ある軽井沢・大賀ホールにてレコーディングを行った「クラシック・シリーズ」をリリースしてきた。『Dimensions』はその第4作目にあたり、同レーベルが大賀ホールで行った録音としては初のピアノソロ・アルバムとなる。ここ数年のUNAMASは、クラシック・シリーズを年1回でリリースしていたが、本作は前作から2ヶ月足らずでのリリースとなった。
今回主役となるYuki Arimasa(ユキ・アリマサ)は、バークリー音楽大学を卒業後、同校にて助教授として教鞭を取るなど日本人としては稀有な実績を持つジャズピアニストだ。最大の特徴はオリジナリティにあり、ユキ・アリマサのスタイルは海外のジャズシーンからも高い評価を得ている。
しかし、ユキ・アリマサが今回『Dimensions』でプレイするのは、ジャズではなくクラシックの楽曲だ。バッハやベートーヴェン、ドビュッシーの楽曲に加え、自身のフェイバリットとなるGleen Sleevesの合計7曲が収録された本作は、「クラシック・シリーズ」にありながら、“ユキ・アリマサのジャズというフィルターを通したクラシック”が堪能できるユニークなアルバムとなっている。
リリースに先駆けた発表会には、レーベル代表でありレコーディングエンジニアである沢口"Mick"真生氏が登場。「UNAMASでは、"Art"、"Technology"、"Engineering"の融合を標榜してきましたが、これまでにも増してそれらの要素を実現できました」とその仕上がりを振り返る。
■スタインウェイ銘機の響きを余すことなく収録することを目指す
本作は、自らを「ジャズ屋」とする沢口氏にとって真骨頂ともいえる録音となったのではないだろうか。『Dimensions』のテーマは、大枠では過去のシリーズ3作品と同様だが、本作ならではのアプローチも見逃せない。
何よりも本作を象徴するのが、"Art"の部分だ。今回、ユキ・アリマサが使用したピアノは、スタインウェイの銘機として名高いD274。その中でも、20世紀における最重要ピアニストとして名高いアルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリが最も愛したという個体「NO427700」を弾いている。
録音当日に調律を行った調律師は、「スタインウェイのピアノは長時間弾いていると、演奏者に寄り添っていく他にはないピアノ」と語っていた。収録の際も、「焦ってすぐに録音しないで、2時間くらいはユキさんに弾かせて欲しい、と言われました」(沢口氏)のだという。
「こうした点も含めて“見えないアート”がスタインウェイにはあるんじゃないかな、と思います」と沢口氏が話すことからも分かるとおり、この“Art”の根底をなすスタインウェイ D274の響きこそが『Dimensions』の大きな聴きどころとなる。
■沢口氏ならではのマイキングでホールの響きまで再現
この"Art"を実現する上で、重要になるのが“Technology”と“Engineering”だ。
“Engineering”の要素を象徴するのが、沢口氏が今回採用した独特なマイキングだ。平面を構成する5chのメインマイクには、それぞれノイマンのデジタルマイクKM 133Dを使用。極めて高い解像度の音が録音できるとして昨今注目を集めつつあるデジタルマイクだ。沢口氏はLch、Rchでメインの音を捉えたうえで、さらにピアノの最低域の弦を狙ってセンターchのマイクを配置した。
これは「ピアノは2本で録ると周波数によって左右に振れてしまうのですが、センターchをこうしてセッティングすることで、音が安定してくるのです」(沢口氏)という意味でセッティングされたものだ。
また、100kHzまでフラットに伸びた特性を持つことで定評あるサンケンのCO-100Kを用いたハイトリアL/Rchのマイクと、フロントハイトL/Rchに使用したKM-133Dは、全て客席へ向けてセッティングされている。
「これはエンジニアリングの学校の教科書とは全然違うマイキングですが、あえてこうしています。大賀ホールは、ステージから客席に飛んで行く音がすごく“見える”場所です。特にピアノは非常にパルシブな楽器なので、ピアノと大賀ホールが共鳴するさまを捉えるためには音が飛ぶ方向へ向けた方が良い結果だったんです」と沢口氏はその理由を解説する。
一見すると、9chがそのまま各chにアサインされたシンプルなマイキングだが、セオリーとは大きく異なるアプローチをとった背景には、沢口氏がこれまで取り組んできたイマーシブ(没入感のある)・サラウンドへの経験とノウハウが行かされているのだ。
こうしたマイキングによる結果は、発表会で聴くことができた9chサラウンド再生で体験できた。ピアノから音が飛び出し、ホールへ拡散し、そしてリスナーの耳に入る。その響きが決して混濁することなく、ひとつひとつの音の輪郭を伴って混じりあうさまは、まさに半球面で構成されるイマーシブ・サラウンドの真骨頂だ。
もちろん本作は2chでもリリースされているが、最初から2chをターゲットとするのではなく9chの情報量をベースに組み上げたからこそ完成した2chとしてのメリットは想像以上に大きいことも注目すべき点のひとつだ。
■調音から電源対策まで徹底したサウンドチューニングを実施
そして最後のテーマとなるのが、“Technology”だ。4月にUNAMASレーベルからリリースされた『Death and The maiden』でも注目された徹底的なサウンドチューニングは、本作『Dimensions』でも引き続き採用されている。
前述のとおり、沢口氏は本作で「ピアノの響き」を強く意識している。響きは“鳴り”があってこそ成り立つもので、響きを生み出すピアノをいかに鳴らすかは、本作にとって重要な意味を持っていた。
ピアノが置かれるステージの床には、アコースティック・リヴァイブ製のチューニングキットを活用。ステージそのものが発する低域のノイズを除去するべく水晶クォーツレゾネーターを使用したことに加え、同社製のヒッコリーボードをピアノの下にインシュレーター的に使用するなど、徹底したアイソレーションが行われている。
さらにピアノの下にも同社の拡散板RWL-3を使用していることも注目したい。「ピアノの下は、本当は色々な音がしているのですが、それらは均一ではないので、拡散板を使用しています。音響ハウスで拡散パネルの有り無しをユキさんと実験した際、パネルあるの方がよい結果だったのです」と沢口氏が話すとおり、ここにも同氏の経験に基づくノウハウが採用されている。
そして、響きの要素を大きく左右するのが音楽信号そのもののS/Nだ。電源はエリーパワー製のバッテリー電源「POWER YIILE」を使用。今回マイクプリとして用いたRME「DMC-842M」および「Micstacy」用となるステージ側と、コントロールルームで使用された「MADIface XT」および「Pyramix」用に1台ずつ、合計2台を使った“オールバッテリー・ドライブ”の環境下レコーディングが進められている。
さらに見逃せないのが、『Death and the maiden』の収録時と同じく徹底したEMCノイズの除去だ。このEMCノイズ対策についてはJIONの宮下清孝氏が担当しており、ノイズを抑えながらも音を痩せさせないことを狙った対策が行われている。今回はさらに対策が強化されたことにも注目で、ファインメットの活用やクリーン電源の導入など、録音環境としては異例と言える電源対策行われた。
こうした取り組みの結果は、何よりも『Dimensions』に収録されたユキ・アリマサが弾くスタインウェイの音によく現れている。
オペラ劇場で録音された不朽の名作として名高いキース・ジャレットの『ケルン・コンサート』をレファレンスディスクとして使用しているオーディオファイルは多いと思うが、『Dimensions』にはそれを彷彿とさせるものがある。
もちろんユキ・アリマサとキース・ジャレットは全く異なるタイプのピアニストだが、この二人を結びつけるのは、静寂から立ち上がるピアノのパルシブな音色や広い空間に拡散される響き、そして何よりもエモーショナルな起伏である。このエモーションを考えられる限り現代最先端のアプローチで収録した本作は、まさにユキ・アリマサの個性と沢口氏の感性の化学反応によって生まれた音源と言える。
なお、本作のライナーノーツは、かつてドルビージャパンの代表を務めた伏木雅昭氏によるもの。音楽的なアプローチや、伏木氏だからこそのサウンド面での解説も、最先端のレコーディングに秘められた可能性を存分に知ることができる内容となっている。
現時点でのリリースは、前述のとおり2chと5.0chのみとなっており、9chサラウンドはリスニング環境の問題もありリリースは未定。そのかわり、ヘッドフォン環境で9chサラウンドを再現する「HPL9」での制作が進められており、こちらも近日リリースへ向けて準備が進められている。