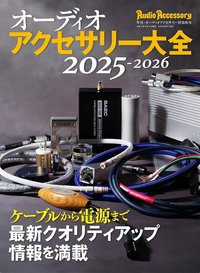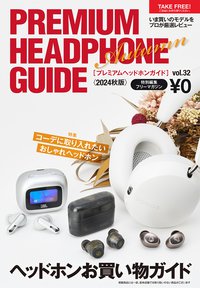Wi-Fi上でBluetooth、クアルコム「XPAN」がついに実用化! そのメリットや今後の進化を同社が説明
「Qualcomm Expanded Personal Area Network Technology(以下、XPAN)」は、ワイヤレスオーディオによるエンターテインメントや音声コミュニケーションのリスニング体験を向上させる米クアルコムの独自技術だ。
XPANは2023年10月に発表された技術だが、ついたシャオミがXPAN対応“第1号”となるワイヤレスイヤホンを発売した。対応アイテムが発表され、あわせて国内メディア向けの説明会も開催されたが、本稿では「XPANのメリット」をあらためて解説しよう。

XPANとは何か? Wi-Fi上でBluetoothオーディオを伝送する利点とは
XPANとは、クアルコムのSoCを採用したポータブルオーディオデバイスの接続性能を高めるワイヤレス技術だ。
XPANでは主に「音質」「ロバストネス(途切れにくさ)」「伝送遅延」の3点を大きく改善する。ポータブルデバイスではBluetoothが広く活用されているが、既に広く普及したBluetoothオーディオをクアルコム独自の超低消費電力によるWi-Fiプロトコルの上に載せながら、先述した3点がBluetoothオーディオよりさらに改善されることがXPANの大きな特長だ。
Wi-Fiを使ったオーディオ伝送は、据え置きコンポーネントやワイヤレススピーカーなどが多数対応しているが、完全ワイヤレスイヤホンやワイヤレスヘッドホンに採用されることは稀だ。
その理由は、一般的にWi-Fi機能をポータブルオーディオに搭載すると、Bluetoothオーディオによるリスニングと比較し、著しく電力を多く使ってしまうからだ。ゆえに積極的に採用する製品は少ない。
最近では米Sonosのワイヤレスヘッドホン「Sonos Ace」がWi-Fi機能を搭載し、同社サウンドバーとのP2P接続時にテレビ音声をスワップして聞いたり、サウンドバーによるイマーシブサウンドをヘッドホンリスニングで再現する機能を載せた。ただしこれも、通常はBluetoothオーディオで聴き、特定の環境で特別なリスニング体験を得るための「オプション機能」としている。
クアルコムは2023年後半に出荷を開始したオーディオ向けSoCのフラグシップ「Snapdragon S7+ Gen 1 Sound Platform」に初めてXPANを載せた。以降、チップが量産出荷され、デバイスメーカーによる商品の企画・開発の段階を約1年以上経て、いよいよシャオミが対応製品の「Xiaomi Buds 5 Pro(Wi-Fi版)」を発売した。シャオミはSnapdragonシリーズのモバイル向けSoCのティアワン企業でもある。「XPANでも1番乗り」を果たしたわけだ。


残念ながら、同社のXiaomi Buds 5 Proを筆者はまだ試せていない。アナウンスによると、同じシャオミの「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」を搭載したスマートフォン「Xiaomi 15 Ultra」と組み合わせると、XPANによる一部のワイヤレスオーディオ機能が使えるようだ。直販サイトの販売価格は24,980円(税込)のワイヤレスイヤホンなので、ミドルレンジ価格帯のモデルと言える。


XPANはまだ進化し、音質や安定性が今後さらに向上。192kHz対応も
クアルコムのメディア向け説明会では、本社のXPAN担当チームを代表してVoice&Music部門プロダクトマネージメント ディレクターのナイジェル・ブルゲス氏が技術を解説した。
XPANはいわゆる“ベータ版”ではないものの、まだ発展途上のものであることを強調し、「XPAN音質や接続性能の安定性は今後さらに向上する。対応する製品も増え続けることが期待できる」とブルゲス氏は述べた。実際、Xiaomi Buds 5 Proはソフトウェアアップデートによって機能も増えるという。

1つ目は「Wi-FiのP2P(Peer to Peer)接続によるハイクオリティなワイヤレス再生」だ。これはシャオミの製品による“1対1”の組み合わせにより、発売直後から使える機能だ。XPANの利用条件として「クアルコムのSnapdragon Soundに対応したチップセット同士」の環境であることが、少なくとも現状では必要となっている。
必然的にBluetoothオーディオのコーデックはクアルコムのaptX Adaptiveとなるが、最大96kHz/24bit相当のオーディオストリームをサポートする。また音質面では、最大48kHz/24bitのaptX Losslessコーデックによるリスニングが楽しめることもメリットのひとつに数えられるだろう。
スマホとワイヤレスイヤホンがWi-Fiによりダイレクトにつながることで、伝送遅延が抑えられ、ロバストネスも向上する。ゲーミング、あるいは音楽制作のモニタリング用途にもXPAN対応デバイスは歓迎されそうだ。
2つ目は、aptX Adaptiveのコーデックをブラッシュアップし、再生周波数帯域の上限を96kHzから192kHzにレベルアップする計画がある。クアルコムは実現に向けて鋭意開発中だが、ブルゲス氏は現時点で「いつ」利用可能になるのか明言していない。
そして3つ目は、ワイヤレスイヤホンをWi-Fiアクセスポイントに直接つなぎ、より広いエリアでオーディオストリーミングを受信できるようになる「Whole Home Coverage」だ。筆者はこれを意訳し「家まるごとワイヤレス機能」と理解している。

XPANはどう使う?どう便利? 実際の使用イメージや今後の課題
使用イメージとしては、ユーザーがリビングルームにXPAN対応スマホなどの送信デバイスを置いたまま、ユーザーがBluetoothの信号だけでは到達できなかった範囲まで足を伸ばしても、XPAN対応のワイヤレスイヤホンでオーディオリスニングや音声通話などが楽しめるという使い方だ。
この時、スマホからWi-Fiアクセスポイントへの安全かつシームレスな接続切り替えを実現できるよう、クアルコムは独自のソフトウェアも開発し、SoCとともに提供する。Wi-FiルーターはXPAN対応である必要はないが、P2P接続時には2.4GHzと5GHz、Whole Home Coverageの際には加えて6GHzの周波数帯域が使える。

ユーザーが自宅外でXPANを使う機会を筆者はまだあまりイメージできないが、ブルゲス氏は「例えばスポーツジムで、スマートフォンをロッカーに入れたままワイヤレスイヤホンだけを身に着け、身軽に“ながら聴き”を楽しむ使い方もありそう」だと話している。
お気に入りのプレイリストを頭から順に再生して聴くような楽しみ方であればアリだと思うが、スマホが手もとにないと、オーディオ単体コンテンツ以外の、例えばYouTubeの番組再生等はかえって不便に感じられそうだ。
そのためにというわけではないが、XPANに対応する“Snapdragon 8 Eliteシリーズ”のモバイルSoCと、オーディオ側のフラグシップSoCであるS7+はともにAIエージェントの音声操作がスムーズに動くよう設計された、ベースとなるスペックがとても高いチップセットであることも覚えておきたい。

まずはXPANが発表されてから約1年半が経ち、ついに対応する製品が誕生したことを喜びたい。筆者もできるだけ早く、シャオミのXPAN対応コンビを試聴しようと思う。
今後、XPAN対応機器のエコシステムはさらに拡大するのだろうか。クアルコムはまずコンピューティングデバイス(パソコン)向けのチップセットである「Snapdragon X Elite」と「Snapdragon X Plus」にもアップデートを行い、XPAN対応を実現する計画を表明している。

クアルコムが同じく力を入れているオートモーティブやXR/ARデバイスのためのチップセットにも、当然XPAN対応は拡大して然るべきだ。ブルゲス氏は具体的な計画を明言しなかったが、いずれクアルコムのあらゆるチップセットを載せたエッジデバイスに、XPANによる上質なワイヤレスオーディオ体験の輪を広げたいと語っていた。

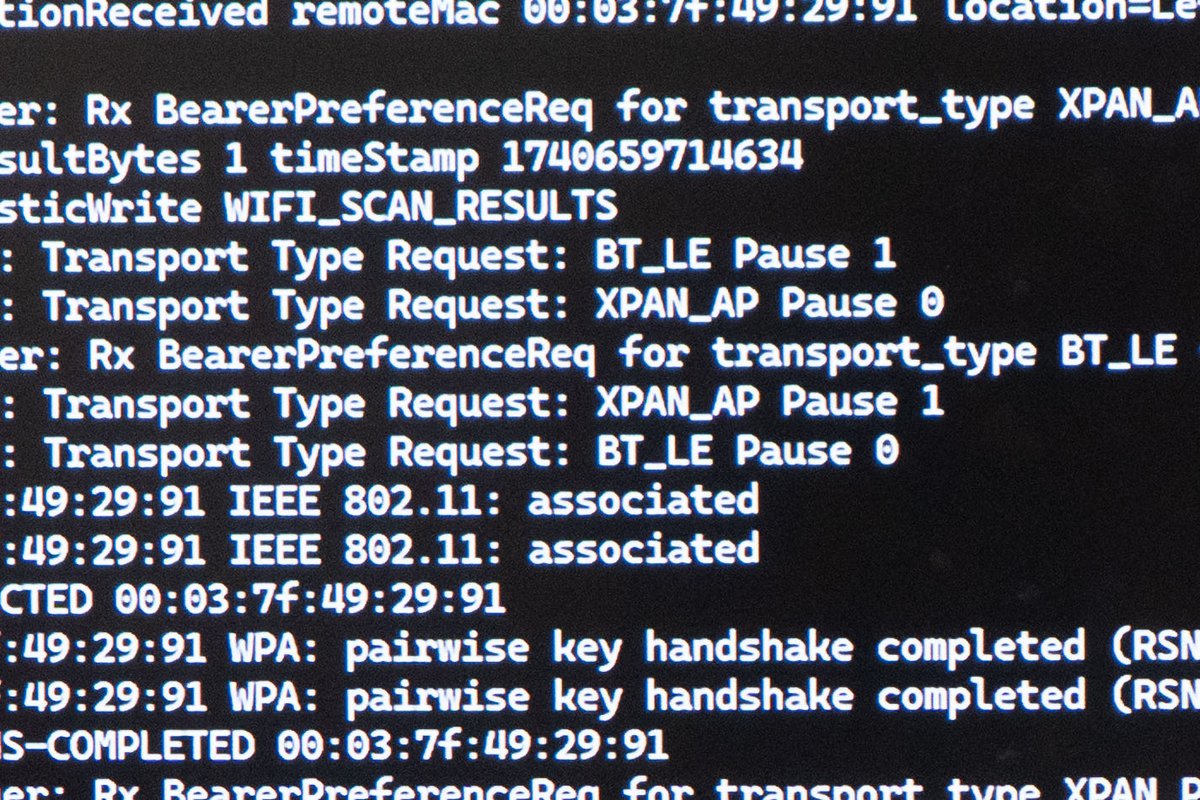

今後、ポータブルデバイスのワイヤレスオーディオ技術として、XPANのような「超低消費電力を実現するWi-Fi」が勢いよく台頭してくるかもしれない。ユーザーとしては、とにかくデバイスの互換性や使用できる環境要件などが複雑でない、実用的な選択肢になることを期待するばかりだ。