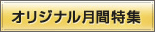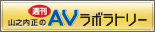|
||||
 |
||||
|
||||
貝山氏(以下 敬称略) このジャンルの「ネクスト」と言えば、例えば東芝REGZAの「超解像技術」が挙げられますね。 − 劇場と家庭用受像機のいずれをターゲットにするか、あるいは両方を対象とするのか? 映像作りのコンセプト・手法は大きく変わってきています。逆に、テレビやプロジェクター等の受像機側でも大きな変革が求められている時期にあると言えそうですね。
貝山 ポストフルHDという意味で私が現在注目しているのは、4Kあるいは2Kのクオリティを持つコンテンツの登場、あるいは4K、2K映像のアーカイブでの活用が進行しているということです。最近の映画界では、当然ながらさらなる高画質への探究が始まっています。解像度をフルHD以上に上げてマスターを作成し、そこからパッケージソフトを作っていく、あるいは劇場用プリントを作るというプロセスが広まりつつあるんです。そういった意味で、今回REGZAに搭載された「超解像技術」は4K時代を見据えた先進技術として大変注目しています。 − はい。 貝山 アメリカほどではありませんが、日本でも4Kクオリティの映画館が少しずつ登場し始めています。映画館で4Kクラスの映像を鑑賞する形態が日常化すれば、家庭用ディスプレイに対して今以上のクオリティを望むのは当然のことだと思います。 − 映像制作に携わる方も、フルHD以上のクオリティを持つディスプレイを想定して、シビアに映像を作り込む必要性が増してくるでしょうね。 松山氏(以下 敬称略) 映画制作の7〜8割をデジタル方式が占めるようになるのは事実でしょうから、コンテンツ製作者、受像システムのそれぞれが柔軟に対応するべき状況にあると思いますね。 貝山 そうですね。 松山 ただ、現行のデジタルハイビジョン画素がさらに2倍、4倍と伸びたときに、果たしてそれがフィルムの質を凌駕するものになるかどうかは、まだ判断が難しいですね。デジタル上映システムあるいは家庭用テレビシステムが、フィルムが本来持っている階調性をカバーできるかどうかが鍵となりそうです。そこまで至ってデジタルディスプレイが、フィルムとイコールになると思います。 貝山 解像度が上がるということ自体はもちろん歓迎ですがね。 − 貝山さんは、映像基準の軸足はフィルムとビデオのいずれに置いた方がいいとお考えですか?
貝山 どちらでも良いと思います。行き着く先は同じですから。原材がフィルムであれビデオであれ、撮った素材の画質を高く維持し、それを元に編集等の作業を進めていくことには変わりありません。 − なるほど。 貝山 私はこの前、非常に面白い体験をしました。フランシス・フォード・コッポラの新作『コッポラの胡蝶の夢』を観て、新たな発見があったのです。今までにない、ある意味で非常にしなやかな映像を体験することができたのです。この作品の興味深い点は、フィルムに近い階調を持ちながら、実はビデオで撮影しているということです。それを4Kマスターに起こして処理している。 − はい。 貝山 そういった意味で、映画の元素材が何かにこだわっていてもあまり意味はありません。新しい映像表現の可能性は、至るところにあるはずです。私を含めた鑑賞者の立場で申し上げれば、フィルムとビデオのどちらで撮影されていても構いません。自分がプロデュースを務める映画であれば、一緒にプロセスを共有する監督や撮影監督の方と議論して、フィルムで撮るかビデオで撮るかを決めるはずです。どちらかを選んで、一番良い機材を集め、一番良い方法で撮り、一番良い手法で後処理を行います。 |
||||
− 1920×1080という解像度が最終形だということはないはずですね。ところで、現状のフルHDコンテンツを再生する時に不満を感じることはありませんか? 貝山 今のハイビジョン映像では物足りなく思う時も来るかもしれませんね。フルHD映像に眼が慣れてしまうと、限界がいずれ見えてくる可能性はあると思います。 − はい。 貝山 そうなると映画で重要な奥行き感を自然に、そして緻密にディスプレイ側で出す必要性が確実に増しています。その目的を完璧に成し遂げるためには、現状の解像度では実は足りないのかもしれません。
松山 画素ということに限って申し上げれば、コンシューマーレベルでは必ずしも4Kまでは必要ではないかもしれません。結局は、階調再現性が豊かになることと合わせて解像度を引き上げなければ、映像の完成度は上がりません。受像機側での階調再現性がフィルム以上のクオリティを獲得することがあれば、改めて考える必要があるでしょうが。今の倍のビット数を持ったカメラ、あるいは放送システムが実際に現れた時に、また改めて検証してみたいと思います。 貝山 階調に関してはその通りだと思います。解像度を上げるだけでなく、階調の再現性も同時に上がれば無敵ですからね。 松山 映画制作者の意図とは異なるところで、デジタルの技術的改善が一方的に進んでいると感じられるケースもありますね。映っている画像に対してコントラストが良いかどうかを判断するのは、素材によって随分違うはずですから。 − はい。 松山 もちろん、制作者の意図を反映させるための技術進化は大歓迎です。一例を挙げましょう。『ラスト、コーション』という話題の映画をご存じですか? ロドリゴ・プリエトというカメラマンがアン・リー監督の意向に添い、説明的なセリフを一切排除して映像だけで語ろうとした映画です。この作品には大変感銘を受けました。言葉を排し、映像だけでストーリーを作っている。ディスプレイの側でも、そういった映像の持つ力を改めて考え直し、一生懸命伝えようとする技術を身に付けるべきだと思います。 貝山 いわゆる「映像言語」が大事だということですね。 松山 そうです。鑑賞者が明るい場所に居ようが、暗い場所に居ようが、テレビは全ての映像を最適に提供する必要がある。自分で調整できるマニアだけでなく、一般の方にも映像が持つ魅力をテレビ側でごく自然に伝える必要がありますね。 |
||||
貝山 ディスプレイはそういった映像が本来持つものをもっと柔軟に、しなやかに対応しく必要があると思います。解像度を引き上げる今回の東芝の技術は、さらにその一歩先を行く可能性を秘めていることは確かだと思います。 松山 テレビの技術担当者は、一時期よりもさらにセンシティブなものを求められているはずです。ある意味で非常に「うらやましい、やりがいのある」課題に取り組んでいると思います。REGZAを始めとするテレビというものは、条件の異なるあらゆる明るさの場所に引っ張り出されて、頑張らされているわけですから。販売店の店頭の日なたに置かれて、そこで光れと言われたり、そしてある時には、真っ暗な環境下で階調を出すことも求められています。このような無茶な要求をされつつも、その課題に果敢に取り組んでいるテレビがREGZAであるということでしょうね。 − ある意味、プロジェクターとテレビでは製品作りの難易度に違いがあるのかもしれませんね。
松山 プロジェクターの場合は、鑑賞条件がある程度決まっています。その前提で考えると、テレビの方がプロジェクター以上にシビアな製品作りを求められていると言えるかもしれませんね。 − 視聴ソースのバリエーションも随分違いますね。プロジェクター視聴の中心はあくまで映画ですが、テレビの場合はそれに加えて、普通のスタジオ撮影の放送も綺麗に映す必要がありますね。 松山 その通りです。 − さらに、地上デジタルやBSデジタル、SDパッケージとHDパッケージといったように、解像度が違うものも柔軟に映し出さねばなりません。求められるものは確かに非常に多いですね。 松山 今、東芝が取り組んでいる課題はそこですね。その命題に対して完璧を期そうと技術陣が汗を流しているのは確かです。液晶パネルそのものに起因する問題もありますから、単独では不可能かもしれませんが、挑戦するという貴重な姿勢は尊重する必要があると思います。 貝山 結局は、ディスプレイを造る方がバランス感覚を磨く必要があるということではないでしょうか? 例えば色表現でも、極端に突出した色があって、それが全体のバランスを崩したり肌色をおかしくしたりしたら、たちまち違和感が生じます。新しく開発した技術の特長を強調したいがために、全体のバランスを崩しては何にもなりません。例えば前後のコマの映像から中間の映像を造り、動きをスムーズにしようとする補間技術があります。これは将来的にも必要となる技術ですから、研究を進めることには賛成です。しかしこの技術では一部の映像で動きが不自然になるなど、未完の部分があります。こうした技術はさらに完成度を高めてから搭載するのが望ましい。幸いにも、東芝REGZAの解像度向上の取り組みは、安易な補間手法をとっているわけではなく、本来オリジナルの映像にある映像と比較して補正を行い、解像度を上げる技術です。映像が持つ意味をきちんと捉えた手法ですから、これからの4K、8Kの世界に繋がるものとして評価して良いでしょうね。 松山 東芝等が推し進める「超解像技術」は、例えばフィルムをデジタル映像に変換する際、あるいはデジタル映像を伝送する際に生じる情報の損失を抑えるという技術です。豊富にある過去のSDアーカイブ映像を、現行の薄型テレビフィットする画質に作り込むことも目的としています。 − はい。 松山 つまり、色々な解像度をどこに収斂し、実際の映像として映し出していくか、という実験と提案を盛り込んだのが今回の「ZH7000」ということでしょうね。 |
||||
|
|
||||