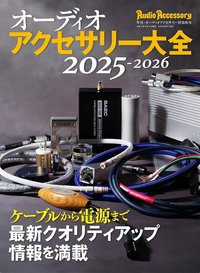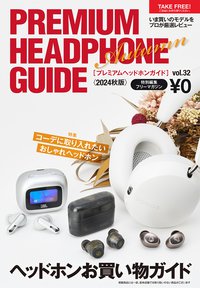サポート体制の充実も重要なテーマ
【特別インタビュー】LUMINの開発思想に角田郁雄氏が迫る!ネットワークオーディオの可能性に挑み続ける技術者集団
昨年秋に、ハイレゾ・ストリーミング/ダウンロードサービスのQobuz(コバズ)が日本で開始され、ハイレゾ再生にさらなる勢いが増した印象を受けます。そんななか、ネットワークプレーヤーブランドとして世界に名を馳せるLUMIN(ルーミン)の製品開発マネージャー、Li On(リー・オン)氏とグローバル・セールス&マーケティング・マネージャー、Angus Leung(アンガス・リュー)氏が来日され、インタビューすることができました。
―― お二人の経歴についてそれぞれ教えてください。
リー氏 私は以前はコンピューター・プログラミングの仕事をしていました。しかし、2005年に発生したサーズ(SARS)のパンデミックの時に、香港、台湾、韓国などでは、PC業界は大きく衰退してしまいました。そこで、個人的にも音楽とオーディオが大好きで、映画も好きでしたから、そういったことに関わる仕事をしたいと考えました。
Mediaboxというビデオボックス、ミュージックサーバーを開発し、放送業界やテレビでも使われるはずと思い、日本の大手メーカーにアプローチしたこともありました。結果的にはうまく進みませんでしたが。その後、ピクセル・マジック社のオーディオブランドとしてLUMINを立ち上げました。2012年には初代の「LUMIN A1」を発売し、現在に至っています。
アンガス氏 私は元々は建築家でした。若い時からオーディオ好きで、オーディオ店でビンテージ製品のレストアを通じて回路設計を学んできました。リーさんとは良いタイミングで出会うことになり、現在では商品企画を中心に、LUMINブランドを盛り立ててゆく良きパートナーとなっています。
―― LUMIN A1の登場は非常に素晴らしいもので、音質はもちろん、価格も当時の海外ネットワークプレーヤーとしては最適だったと思います。そもそも何故、ネットワークプレーヤーを発売することを考えられたのでしょう?
リー氏 当時はネットワークオーディオプレーヤーといえば、LINN、そしてSqueeze Box(スクイーズ・ボックス)くらいしかありませんでした。Squeeze Boxも楽しめましたが、LINNはハイエンドのオーディオを楽しめるプレーヤーとして画期的でした。そういった背景を踏まえ、LUMINとしての目標は、いち早くDSD再生を実現すること、またハイエンドモデルであっても、価格をできる限り抑えたかったということがあります。DSD再生の実現には、2年かかりましたけどね。
―― 当時から、とても使いやすい再生アプリ「LUMIN App」も開発されましたね。日本のメーカーにもそのソリューションが多く採用されています。
リー氏 日本では、嬉しいことにエソテリック、ティアック、ラックスマン、またオーディオラボにも採用されています。iPhoneのように、取り扱い説明書がなくても直感的に使えることが大切です。UPnPを採用したオープンフォーマットですから、汎用性も高いです。
アンガス氏 ユーザー・フレンドリーであることや親切なサポート体制は、当時からセールス的にも大切な要素と考えていました。
―― 私は、音質、デザインのみならず、回路にも大変興味があります。現在はESSのDACチップが採用されており、斬新な回路設計が特徴と感じています。ESSの何に着目しましたか?
リー氏 初代LUMIN A1では、Wolfson(ウォルフソン)のDACチップを採用しました。2016年発売の「LUMIN S1」からはESSのDACチップを採用しています。他の選択肢もありましたが、ESSが高いサンプリングレートに対応し、今でも最高のダイナミックレンジや超低歪みなどの諸特性を実現しているので、信頼しています。単にDACチップを採用するだけではなく、フラグシップモデル「LUMIN X1」からは独自のX1 LUMIN Filterを採用し、ESSのDACチップをカスタマイズ化しています
―― アナログ回路も高品位ですね。ルンダールの出力トランスも採用されています。アナログ回路をどう考えていますか。
アンガス氏 私たちは、広いダイナミックレンジの確保を重点に置いています。特定のパーツを目立たせているのではなく、デジタル回路とアナログ回路を同じレベルで考え、トータルで、ハイ・ゲイン=ハイ・ダイナミックレンジを実現させています。最新の「LUMIN P1 mini」でも、内部ボリュームを使いパワーアンプを強力にドライブします
―― 回路としては、FPGA→ESS DACチップ→ローパス・フィルター(I/V変換回路とバッファーアンプ)の構成ですね。FPGAはどんな役割ですか?
リー氏 FPGAでは、入力音源のサンプリングレートを生成するクロック・マネージメントを行っています。そして、低位相ノイズで高精度な安定性の高いFemtoクロックを44.1kHz系と48kHz系に各1式採用しています。この流れが、先のLUMIN Filterなのです。インパルス応答のプリリンギングとポストリンギングを大幅に低減した独自のミニマム・アポタイジング特性です。このフィルターにより、自然な音の立ち上がりを実現しています。
また音量調整には、フランスのLEEDHというデジタル音量アルゴリズムを採用しています。これは非公開の技術ですが、別搭載のメインCPUが、このLUMIN Filterを制御して音量調整を行っています。プリアンプ機能が搭載されているモデルについては、アナログ入力は192kHz/24bitに変換されてボリューム調整を行い、出力されます。
―― 電源も高品位ですね。
リー氏 当初は、高品位なスイッチング電源でしたが、今では、回路の性能と音質を考慮し、極めてローノイズで高品位なリニア電源を搭載しています。LUMIN X1などいくつかのモデルでは外部電源方式も採用しています。
―― 今後はどのような展開をお考えですか?
アンガス氏 そうですね、光ネットワークポート(SFP)の採用で音質がさらに向上している点はぜひ注目してほしいです。今後については、プレーヤー/トランスポート、両方のラインナップを強化していく予定です。Amazon Music再生にも対応したいですね。
最後に、お二人のお好きな音楽を聴いてみましたが、リー氏は、ポップスやアイドルソングが好きで、日本にはコンサートを目的に度々、来られるとか……。アンガス氏は、ジャズとクラシックがお好き。クラシックでは、名演奏家のソナタもお好きだとのこと。
実にフレンドリーで、質問に適切に応じて下さいました。デザイン、搭載技術、光ネットワーク再生への取り組み、そして高品位な音質、それらをウェル・バランスの価格で実現しているブランドだと改めて感嘆しました。今後のLUMINの展開からも目が離せません。
国内では1月24日(金)より発売となる最新モデル「LUMIN T3X」の音質も短時間ながら試聴しましたが、素晴らしく、大変心惹かれました。ぜひ、オーディオ銘機賞2025でネットオーディオ大賞を受賞した「P1 mini」の音質レビューも合わせてご覧ください。
実に良きインタビューとなりました。
■LUMINブランド始動の背景を聞く
―― お二人の経歴についてそれぞれ教えてください。
リー氏 私は以前はコンピューター・プログラミングの仕事をしていました。しかし、2005年に発生したサーズ(SARS)のパンデミックの時に、香港、台湾、韓国などでは、PC業界は大きく衰退してしまいました。そこで、個人的にも音楽とオーディオが大好きで、映画も好きでしたから、そういったことに関わる仕事をしたいと考えました。
Mediaboxというビデオボックス、ミュージックサーバーを開発し、放送業界やテレビでも使われるはずと思い、日本の大手メーカーにアプローチしたこともありました。結果的にはうまく進みませんでしたが。その後、ピクセル・マジック社のオーディオブランドとしてLUMINを立ち上げました。2012年には初代の「LUMIN A1」を発売し、現在に至っています。
アンガス氏 私は元々は建築家でした。若い時からオーディオ好きで、オーディオ店でビンテージ製品のレストアを通じて回路設計を学んできました。リーさんとは良いタイミングで出会うことになり、現在では商品企画を中心に、LUMINブランドを盛り立ててゆく良きパートナーとなっています。
―― LUMIN A1の登場は非常に素晴らしいもので、音質はもちろん、価格も当時の海外ネットワークプレーヤーとしては最適だったと思います。そもそも何故、ネットワークプレーヤーを発売することを考えられたのでしょう?
リー氏 当時はネットワークオーディオプレーヤーといえば、LINN、そしてSqueeze Box(スクイーズ・ボックス)くらいしかありませんでした。Squeeze Boxも楽しめましたが、LINNはハイエンドのオーディオを楽しめるプレーヤーとして画期的でした。そういった背景を踏まえ、LUMINとしての目標は、いち早くDSD再生を実現すること、またハイエンドモデルであっても、価格をできる限り抑えたかったということがあります。DSD再生の実現には、2年かかりましたけどね。
―― 当時から、とても使いやすい再生アプリ「LUMIN App」も開発されましたね。日本のメーカーにもそのソリューションが多く採用されています。
リー氏 日本では、嬉しいことにエソテリック、ティアック、ラックスマン、またオーディオラボにも採用されています。iPhoneのように、取り扱い説明書がなくても直感的に使えることが大切です。UPnPを採用したオープンフォーマットですから、汎用性も高いです。
アンガス氏 ユーザー・フレンドリーであることや親切なサポート体制は、当時からセールス的にも大切な要素と考えていました。
■ESSのDACチップを最大限活用した斬新な回路設計
―― 私は、音質、デザインのみならず、回路にも大変興味があります。現在はESSのDACチップが採用されており、斬新な回路設計が特徴と感じています。ESSの何に着目しましたか?
リー氏 初代LUMIN A1では、Wolfson(ウォルフソン)のDACチップを採用しました。2016年発売の「LUMIN S1」からはESSのDACチップを採用しています。他の選択肢もありましたが、ESSが高いサンプリングレートに対応し、今でも最高のダイナミックレンジや超低歪みなどの諸特性を実現しているので、信頼しています。単にDACチップを採用するだけではなく、フラグシップモデル「LUMIN X1」からは独自のX1 LUMIN Filterを採用し、ESSのDACチップをカスタマイズ化しています
―― アナログ回路も高品位ですね。ルンダールの出力トランスも採用されています。アナログ回路をどう考えていますか。
アンガス氏 私たちは、広いダイナミックレンジの確保を重点に置いています。特定のパーツを目立たせているのではなく、デジタル回路とアナログ回路を同じレベルで考え、トータルで、ハイ・ゲイン=ハイ・ダイナミックレンジを実現させています。最新の「LUMIN P1 mini」でも、内部ボリュームを使いパワーアンプを強力にドライブします
―― 回路としては、FPGA→ESS DACチップ→ローパス・フィルター(I/V変換回路とバッファーアンプ)の構成ですね。FPGAはどんな役割ですか?
リー氏 FPGAでは、入力音源のサンプリングレートを生成するクロック・マネージメントを行っています。そして、低位相ノイズで高精度な安定性の高いFemtoクロックを44.1kHz系と48kHz系に各1式採用しています。この流れが、先のLUMIN Filterなのです。インパルス応答のプリリンギングとポストリンギングを大幅に低減した独自のミニマム・アポタイジング特性です。このフィルターにより、自然な音の立ち上がりを実現しています。
また音量調整には、フランスのLEEDHというデジタル音量アルゴリズムを採用しています。これは非公開の技術ですが、別搭載のメインCPUが、このLUMIN Filterを制御して音量調整を行っています。プリアンプ機能が搭載されているモデルについては、アナログ入力は192kHz/24bitに変換されてボリューム調整を行い、出力されます。
―― 電源も高品位ですね。
リー氏 当初は、高品位なスイッチング電源でしたが、今では、回路の性能と音質を考慮し、極めてローノイズで高品位なリニア電源を搭載しています。LUMIN X1などいくつかのモデルでは外部電源方式も採用しています。
―― 今後はどのような展開をお考えですか?
アンガス氏 そうですね、光ネットワークポート(SFP)の採用で音質がさらに向上している点はぜひ注目してほしいです。今後については、プレーヤー/トランスポート、両方のラインナップを強化していく予定です。Amazon Music再生にも対応したいですね。
■技術と音質、そして価格のバランスの取れた高品位なプレーヤー
最後に、お二人のお好きな音楽を聴いてみましたが、リー氏は、ポップスやアイドルソングが好きで、日本にはコンサートを目的に度々、来られるとか……。アンガス氏は、ジャズとクラシックがお好き。クラシックでは、名演奏家のソナタもお好きだとのこと。
実にフレンドリーで、質問に適切に応じて下さいました。デザイン、搭載技術、光ネットワーク再生への取り組み、そして高品位な音質、それらをウェル・バランスの価格で実現しているブランドだと改めて感嘆しました。今後のLUMINの展開からも目が離せません。
国内では1月24日(金)より発売となる最新モデル「LUMIN T3X」の音質も短時間ながら試聴しましたが、素晴らしく、大変心惹かれました。ぜひ、オーディオ銘機賞2025でネットオーディオ大賞を受賞した「P1 mini」の音質レビューも合わせてご覧ください。
実に良きインタビューとなりました。