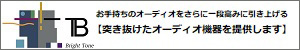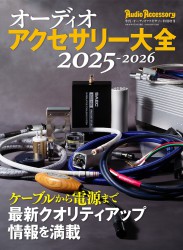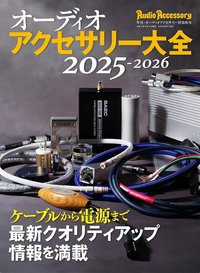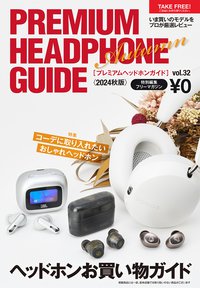“ちょい足し” から始まるroonの楽しみ。手持ちのオーディオを “無限のジュークボックス” に変える魔法の小箱
■「新しい音楽との無限の出会い」をもたらすroon
統合音楽ソフトとして非常に高い完成度を誇るroon。手元の音源管理に優れることはもちろん、Qobuzが日本でも正式にスタートしたことによって、そのポテンシャルを十全に楽しめる環境が整ってきた。
その状況をうけて、イギリス・CHORD(コード)製品等の輸入を担当するタイムロードが、「これからroonを始めたい!」というオーディオファンに向けた新たな製品を発売した。自社ブランドArchitectura(アーキテクチューラ)より、roon coreに最適化された小型PC「Nano Core」と、roon bridgeとなる「Nano Bridge」である。
それぞれの役割について解説する前に、roonというソフトウェアについて改めて説明しよう。
roonでは何ができるのか? 冒頭に、roonは「統合音楽ソフト」と説明したが、基本的な機能はiTunesのように音楽を再生・管理できるソフトウェアである。だがそれだけではなく、独自のアーティストデータベースを持っており、ある気に入った作品があったら、その作品に関わったミュージシャンやプロデューサーなどの関連から、新しいアーティストを探すことができる、特別な機能が用意されている。
この機能は、「ストリーミングサービス」と極めて相性が良い。ストリーミングサービスで1億曲以上の曲が聴き放題になる、とはいうものの、逆にどうすれば良いのか、どこから掘り下げれば良いのか途方に暮れてしまう。結局好きなアーティスト、知っている曲ばかりを聴いてしまう、ということもあるだろう。
「新しい音楽との出会い」は、かつてはCDショップの推薦やラジオなどをきっかけとすることが多かっただろう。またSpotify等各種ストリーミングサービスにもレコメンド機能は存在する。roonはそれをより「オーディオ的」あるいは「音楽ファン的」に深く楽しめるよう設計されたもの、と捉えることもできる。
この魅力を、タイムロード社長の平野さんは「ジュークボックスの楽しみ」と捉えている。だが、roonは買い切りのソフトウェアとして829.99ドル(日本円で約13万円)、サブスクリプションで月額14.99ドル(日本円で約2,300円)と、決して安くはない。そこにさらにハードウェアやストリーミングサービスの契約費用もかかるとなると大変だ。そこで、16万円強と比較的お求めやすい価格の「Nano Core」をリリースすることで、roonを手軽に始めてもらえる道筋をつけたい、と考えているのだ。
■手持ちのオーディオに “ちょい足し” できるroon core
「すでにオーディオシステムを持っている人に、簡単にアドオンしてroonを楽しんでもらいたい」。Nano Coreのコンセプトについて平野さんはそう語る。昨今のCDプレーヤーやプリメインアンプにはUSB入力が搭載されているものも多い。Nano CoreをUSBケーブルで既存システムと接続することで、手持ちのオーディオを活用しながら、“ちょい足し” でネットワークオーディオが楽しめるようになるのだ。
Nano Coreを使うための準備は簡単で、roonのソフトウェアを購入することのほかに、スマートフォンやタブレットにroonアプリ(ソフトウェアを購入していれば無料で使える)をインストールすること、そしてNano Coreを自宅のネットワーク(ルーターやハブ等)にLANケーブルで接続すること、USB-DAC(内蔵のCDプレーヤーやプリメインアンプ等)とUSBケーブルで接続する、これだけである。この辺りの設定に不安があれば、専門店でのサポートも受けられる。
開発を主導した奥村さんによると、Nano Coreは産業用PCをベースに、オーディオ機器として最適化して作られているという。非常に頑丈でノイズレス、いかなる環境でも(野外で長時間使っても!)安定した動作を実現するPCをベースに、roon core以外の不必要な機能はすべてカット。外観上はHDMI端子やヘッドホン出力端子なども備わっているが、これらは機能として使わないために停止させている。生きているのはLANポートとUSB Type-Aの3系統のみ。
USB Type-Aもよく見ると2種類あり、内側が青いUSB3.0対応が2系統、内側が灰色のUSB2.0対応が1系統。奥村さんによると、PCの規格上の問題として「USB3.0のほうがスピードが速い反面、オーディオには関係のないさまざまな機能が動いてしまうため、実は音質的にベストとは言えないと考えています」とのこと。そのため、「USB-DAC等への送り出しにはUSB2.0対応を使っていただき、USB3.0の方には外付けストレージなどを繋いで欲しいと考えています」とオススメの使いこなし方法を教えてくれた。
ちなみにNano Core本体にはストレージは基本的に内蔵していない。それは、万一故障して修理する必要が発生したときに、ストレージごと交換になる(=貯めたライブラリがダメになってしまう)リスクを避けるためだと言う。
■アキュフェーズのCDプレーヤーにroonをアドオン!
Nano CoreとアキュフェーズのCDプレーヤー「DP-770」をUSBケーブルで接続して動作検証を行った。iPadのroonアプリを立ち上げると、コア(core)を選択する画面が出てくるので、該当のcore(ここではNano Core by Architectura)をタップすればOK。
続けて、セッティングのAudioから、「オーディオの出力」を設定する。ここではアキュフェーズのDP-770を使っているので “accuphase” と名前をつけている。
Qobuzとの連携することで、配信されているアルバムがざっと一覧で表示されるので、あとは気になる音源をどんどんタップして再生していくだけ。ウィーン・フィルとジョン・ウィリアムズによる「インペリアルマーチ」をけば、ステージが眼前に広く展開し、ストリーミングとは思えないハイクオリティなサウンドがスピーカーから流れ出してくる。
ジョン・ウィリアムズはベルリン、ウィーン、東京と3つのパターンのライヴレコーディングを聴き比べるのもroonならとっても簡単。既存のオーディオシステムがある程度整っていれば、こんな小さな箱をひとつ追加するだけで無尽蔵の音楽に手軽にアクセスできるというのはたまらない魅力である。
■負荷分散で音質向上を狙う「Nano Bridge」
だが、タイムロードの提案はこれだけでは終わらない。「Nano Bridge」と呼ぶroon bridge製品も発売している。こちらは約9万円。
roon bridgeとは、roon coreの音源データをネットワーク経由(RAATと呼ばれる独自プロトコル)で受け取り、再生してDAコンバーターに送り出すものである。
Nano Coreでは、音源の送り出しと再生が1台の機械で賄われていたが、Nano Bridgeを追加することで、coreは音源の送り出し、bridgeは再生のみと、役割を分離させることができる。そのことで、機器の負荷を減らしオーディオのクオリティ向上を実現しようという考え方だ。Nano BridgeはラズパイベースのPCとなるが、こちらもbridge機能以外は停止されており、専用機としての役割となる。
今度はNano Bridgeを追加して音質をチェックする。Nano BridgeをLANケーブルでルーターと接続するとともに、USBケーブルは今度はbridgeからアキュフェーズDP-770に接続する。Nano Coreのみの場合よりも高域が自然に伸びやかになる印象で、低域の沈み込みもより深く重い。ぐっと「オーディオ的な解像感」が高まった印象だ。
“ちょい足し” で広がるroonの楽しみ。興味のある方は、ぜひお近くの専門店に問い合わせを。
関連リンク