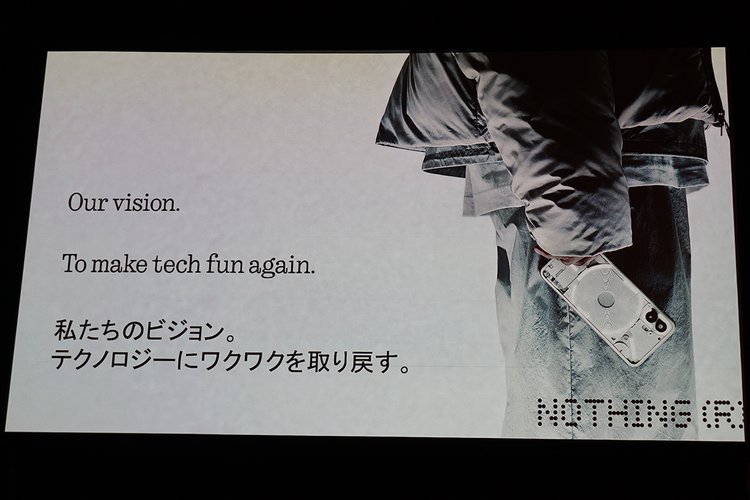「テクノロジーに“再び”ワクワクを取り戻したい」
Nothingスマホはなぜ透明? そこにはニーズに向き合いつつ遊び心を忘れない“デザイン哲学“があった
Nothingの製品はなぜ「透明」なのか?デザイン哲学を語る
「透明であるということは、ブランドの信条やモットーが形となって現れた結果である」。京都・上七軒歌舞練場にて11月23日に開催されたトークイベント『Nothing Design Talk in Kyoto/コンセプトから製品へ:Nothing流デザイン哲学』の中で、Nothingのデザインディレクターを務めるAdam Bates氏は、彼らの手がける製品デザインの象徴的な “透明性” についてそう語った。
Nothingは2020年創業の新鋭ブランド。2021年に初プロダクトとして完全ワイヤレスイヤホン「Ear (1)」を発表し、中の機構が見える透明(スケルトン)なデザインで注目を集めた。続いて登場したスマートフォン「Phone (1)」では背面部を透明なデザインとし、さらに内部に配置したLEDが光るGlyph Interface機構で話題となった。その後、現在までにイヤホン2製品、スマートフォンは第二世代「Phone (2)」が登場し、ブランドは4年目を迎えている。
すでに飽和状態にあるとも思える市場で、インパクトある製品を登場させているNothing。そのデザイン哲学の根底にあるのは、「Technical Warmth(テクノロジーのぬくもり)」だという。「テクノロジーは進化が進めば進むほど、どこか冷たいイメージになりがち。私たちはそこに人間性、人との交流、ユーザーの経験を重要視したいと考えている」と、グローバルブランド・クリエイティブディレクターのRyan Latham氏は語る。
Adam氏もまた「テクノロジーは進化によって、人々に脅威を与えるような怖い存在のようになってきた。我々は再びテクノロジーを、楽しいものへと取り戻したいと考えている」と、Nothingが掲げるビジョン「To make tech fun again.(テクノロジーにワクワクを取り戻す)」をあらためて強調した。
こうした考えのもとで開発されたNothingの製品は、 “透明” なデザインを採用している。これについては上述したように、アイデンティティでもあり、マーケティングや製品開発、ブランドコミュニケーションの全てにおいて透明性を重要視しており、それの表れでもあると説明する。
透明性の一例として、彼らは開発スタジオをジャーナリストや一般ユーザーにもオープンにしていると語る。そうした姿勢は、ユーザーとの関係構築にも影響しているのだろう。「双方向的な関係」とRyan氏が話すようにユーザーコミュニティが活発で、それもNothingの特徴といえる。
コミュニティの中では日本からも、さまざまなフィードバックがあるという。ブランドが始まった当初から関心の高い国の一つだったそうで、「Nothingの考えが理解されていると感じた」とRyan氏。もともとNothingはソニーや任天堂からインスピレーションを受けたとしており、また、Ryan氏とAdam氏のふたりも「日本の影響を多く受けてきた」とのこと。「これまでも日本から生まれたカルチャーや、“楽しさ” を感じる電化製品などから学んできたように、もっと学びを深め、Nothingの未来を大きく飛躍させたい」と述べた。
ニーズを生み出す独自性。美しいだけじゃない、機能と思いが融合したスマートフォン
Nothingの製品のなかで、最も注目を浴びた機能といえるのがGlyph Interfaceだろう。光のパターンによって、着信先やアプリの通知、充電状況などを知らせてくれるもので、ユーザー自身で重要な連絡の通知などをカスタマイズすることができる。
このGlyph Interfaceの開発に至るまで、Nothingでは成熟したスマートフォン市場のなかで、何ができるのかを全て問い直してきたという。そして、スマートフォンの普及により画面を見続ける時間が増えた現代において、その時間を減らすことができないか? という考えから、透明な背面を活かしたライティング機能に行き着いたそう。
たしかに、スマホを使っていると、何かの通知をきっかけに画面を見て、そのままSNSを見たり、様々なアプリを開いたりして、スクリーンタイムは増えがちだ。Nothingのスマートフォンは、透明な背面部にGlyph Interface機能をつけたことで、光によって自分にとって重要な通知かどうかを判断できる。そのため、「通知が来たからスマホを見る」ではなく、ユーザーがいま画面を見るかどうかを考えて、意識的にスマートフォンを使うことを促してくれる。
Phone (1)、Phone (2)と使い続けている筆者にとって、この点はまさに実感する部分だった。正直Nothingの目指す使い方とは違うかも知れないのだが、光る背面を見たいがために、スマートフォンを伏せて置くようになり、自分が見るべきと思う、見たいタイミングで画面をひらくため、通知が来てもすぐにスマホの画面を見ることはほとんどなくなっている。そもそも、透明な背面は光ることだけでなく、見えている中身までこだわり抜いてデザインされていてかっこいい。このスマホを持つなら、背面を見たいのだ。
内部のデザインは、Phone (1)のときにはニューヨーク地下鉄路線図から着想を得たとし、さらに象のフォルムが潜んでいたりと、遊び心にもあふれている。Adam氏はその開発について、「透明性をなるべく高めようと考えると、内部の細かな部品まで見せることになる。だから一つ一つ、機能を担った部品を自分達で作ることが多い。そのためデザインを考えるときには、エンジニアのようにならなければならない」と語る。
こうした製品開発において、自分で実際に作って、経験することを大事にしており、「作るのも、実際に使うのも私たち。メンバーは開発の場であるスタジオで最大限の時間を使うようにしている」のだとAdam氏。その場にはさまざまな技術者が集まり、顔を合わせて開発を進めることで、ハードとソフトをしっかり融合させたモノづくりが実現できているという。
そして、できる限り他社の動向には左右されない、ユーザー第一のデザインを追求することも重要だとし、「実際、これまで市場に “透明なスマートフォン” のニーズが強くあったわけではない。しかし、自分達がそれを重要だと確信し、製品を生み出すことで、同じように大事だと思ってくれるユーザーと繋がり、購入してもらうことができた」と力を込める。
緻密に作り込み、品質を高く保ちつつも忘れない「楽しさ」と「遊び心」
Nothingでは、デザインの始まりはすべて、グリッドを使って制作されるとのこと。体系的な図面の中で描くデザインは、ソリッドでメカニカル、かつミニマルで、簡単にイメージしやすいことも大事にしているのだそう。ロゴもその一つ。ドットが集まって「Nothing」が作り上げられており、タイポグラフィにも影響を受けたという。
Ryan氏は、Phone (1)、Phone (2)の背面デザインを例に挙げて、左右対称性であったり、各部品の比率や一体感、それらを美しく配置することなど、インダストリアルの観点から徹底していると説明。それと同じくらいに、ソフトウェアによるユーザー経験も重視し、「全てうまくいった時、唯一無二の製品になれる」と語る。
このように、Nothingの製品は、イヤホンもスマートフォンも全てが、デザインにも機能にも妥協なく開発されており、それぞれの製品に必要とされる品質の高さはきちんと確保されている。ただ、それだけに終始せず、さらに “楽しさ” も兼ね備えることも、らしさの一つである。
たとえばEar (2)では、ケースに窪みが設けられており、ハンドスピナーのように回すことができる。これはただ「楽しさ」を考えて設けられた役割だとAdam氏は語る。
また、パッケージにもこだわられている。スマートフォンならば、従来考えられている適切な方法というのがあるわけだが、Adam氏は「それではつまらないと思った。パッケージも製品の一部、面白いものにしたい」と考え、Phone (1)、Phone (2)ではレコードのジャケットようなデザインを採用したそうだ。
製品パッケージはすべて紙製で、開封する際にはビリビリと紐を引っ張るようにして一部を破いて開けるかたち。「たった一度きりの製品との出会い」というユーザー体験も重視したのだと語る。
これらのパッケージはリサイクル資源由来の紙を一部使用し、プラスチックは使用しないなど、サステナビリティにも配慮される。製品においてもリサイクル素材を活用し、カーボンフットプリントの削減も図られている。
Ryan氏は「スマートフォンは機能も質も大事、高品質な製品を提供することを第一に考えている」としつつ、「それ以外にも、楽しさやユーザー体験も重要。そして同じように、サステナビリティも重要視している」と説明。「市場競争や環境配慮などのシリアスな局面と、製品を通じた楽しさというのは、どちらも重要で、両立できると思っている」と語った。
テクノロジーの枠にとらわれず、楽しいことを追求。次なる展開に期待
『Nothing Design Talk in Kyoto/コンセプトから製品へ:Nothing流デザイン哲学』ではほかにも、Nothingの製品が生まれるまで、デザインの考え方はもちろん、その根底にあるNothingのカルチャーやビジョンが紹介され、改めて新鋭ブランドの目指すところを深く知ることができた。
第二部では、ゲストにスマイルズ 取締役社長 兼 CCOの野崎 瓦氏、京都精華大学デザイン学部准教授・副学長の蘆田裕史氏を迎えた、デザインを軸にブランディングやファッションなどの視点で対談セッションも行われた。
イベントの中でRyan氏は、「遊びの要素や実験を楽しむことも大事」だとし、その結果、偶然にNothingが目指す、ワクワクするものが生まれることがあるとも語った。たとえば、ロンドンのSOHO地区にオープンさせた唯一の実店舗のオープンが決まった際に、スタッフの声で生まれたのが「Beer(5.1%)」。テクノロジーブランドがビールを開発? と発表時から話題となり、大好評で売り切れとなったという。将来的に日本でも展開したいと語ってくれた。
さらに、透明性を大事にするNothingのデザイン精神を表したというアパレルアイテムも開発。「テクノロジーに敏感な10代ユーザーとのコラボでデザインコンセプトを実現、作業が終わった後も着ていたいワークウェア」だと紹介されており、12月にはコートや帽子も発売される。今後は、特別ブレンドのコーヒーも開発中だという。
これらも、「テクノロジーにワクワクを取り戻す、という軸の元、もっとワクワクすること、楽しいことをやっていこうという活動の一つ」だと語り、枠にとらわれないNothingらしさを強調した。最後に、Ryan氏に今後の展開について伺ってみたところ、「詳しいことは言えないけれど、オーディオやスマートフォンはもちろん、新しいカテゴリーでも新製品を考えている」と答えてくれた。いちファン、いちユーザーとしても、Nothingのさらなる活躍を楽しみにしたい。