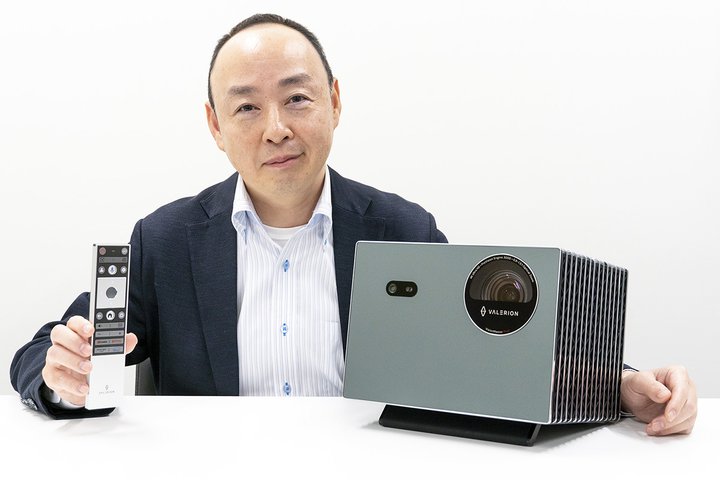公開日 2013/12/24 19:27
ラックスマンの旗艦パワーアンプ「M-900u」レビュー − 「C-900u」と組み合わせで聴く
「静寂感に鳥肌が立つほど驚いた」
■独自の「ODNF」がVer.4.0に進化
ラックスマンの新しいフラグシップ・パワーアンプ「M-900u」(関連ニュース)。位置づけ的には「M-800A」の後継機ということになるのだが、内容は完全に一新されており、ある部分では、同社の創業80周年を記念して造られた超弩級機の「B-1000f」(※生産完了)を超える存在になった。
フロントパネルの「容貌」は一変し、パワーメーターを備えたトラディショナルなものになった。このメーターは発光LEDによる電球色照明によって照らされる。筐体の剛性は非常に高く、質量こそ「M-800A」よりも500グラム軽い48kgになったが、緻密感や精密感は上昇しており、「B-1000f」に迫るほどだ。パワーアンプの基本的音色を決定づける重量バランスは非常に良好で、納品時やセッティング変更時に安心して移動させることができる(ただし、本機を持ち上げる際は絶対に複数名で作業すること!)。
回路は基本的にバランス方式で、入力バッファー段、ドライバー段、終段という3段構成だ。終段のパワートランジスタは3段ダーリントン4パラレルプッシュプルである。
ネガティブフィードバックはラックスマン独特のODNF4.0。これは歪成分のみをフィードバックさせ、ノイズを打ち消す画期的な回路のバージョン4.0であり、「M-800A」のバージョン2.3からずいぶん進歩したことになる。NFBをかけるかかけないかにはさまざまな議論があると思うが、個人的にはNFBを欠くアクロバティックな回路よりも、本機のような高度な帰還回路のほうが安心して使えると思う。
本機でもう一つ議論を呼ぶと思われるのが、終段のプッシュプル回路のバイアス電圧のかけ方である。「C-800A」が理論的に理想的なA級であったのに対して、本機は折衷案的なAB級が採用されているのだ。「A級アンプ原理主義者」は眉をひそめるかもしれない。だが、本機のスペックを冷静に検討していただきたい。
本機の出力は、スピーカー側のインピーダンスが8Ω時に150W×2、4Ω時に300W×2、2Ω時に600W×2、1Ω時に1200W(瞬間最大値)、と負荷抵抗値1Ωまでリニアに上昇している(ブリッジ接続時は8Ω時600W、2Ω時2400Wが保証される)。また、正式にはアナウンスされていないが、AB級動作機としてはバイアスが非常に深く、8Ω時に12W×2までがA級動作領域である。したがって1Ω時でも約100W×2までがA級動作の限界ということになる。これは必要十分なスペックではないだろうか?
それよりも問題なのは発熱だ。A級動作機は理論的には正しい音が出るはずではあるものの、大出力機になればなるほど素子や回路が熱をもち、音像のシャープネスや音場のトランスペアレンシーが低下してしまうのである。同社のA級動作プリメイン型機「L-590AX」のような30W×2(8Ω)程度の出力をもつモデルならば、発熱による影響は皆無なのだが、150W×2(8Ω)を純A級動作で得るのは得策ではない、というのが現在のラックスマンの技術陣のコンセンサスのようだ。
それでも本機の深いバイアスによる発熱は、彼らにとって看過できないレベルにあるらしく、トップパネルにはパンチングメタルを施された放熱孔が切られている(これが昔のフェラーリエンジンのキャブレターの吸気孔めいていて、個人的には滅茶苦茶シビれた)。
■試聴:「C-900u」との組み合わせでB&W「802 Diamond」を鳴らす
さて、本機のサウンドである。本機のペアとして開発された「C-900u」との組み合わせでB&W「802 Diamond」を鳴らしたのだが、まずは静寂感に鳥肌が立つほど驚いた。
これは「C-900u」の影響も強いのだろうが、音が出た瞬間、再びゾクゾクっときた。試聴に使用したのはフィッシャー指揮&ブダペスト祝祭管によるワーグナーの「神々の黄昏/ジークフリートの葬送行進曲」。無音の中から聴こえてくるティンパニーの弱奏が単なる小さい音ではなく、小さいけれども自らの意志をもった音のように感じられたのである。
そして低弦の慟哭のような力強い音が筆者の顔面を痛打して椅子から転げ落ちそうになった。この鳴らしにくいスピーカーのウーファーをこれほどグリップし、さらには低音を飛ばす能力のあるパワーアンプがオーディオ史上に一体何台あっただろうか。
これほどショッキングなサウンドを放つのにもかかわらず、本機は楽曲や演奏に対して音楽的な介入を一切しない。ただ、プリアンプ等から入力された信号をありのままに増幅してスピーカーをドライブするだけである。先代の「M-800A」が微かに音楽的介入をしたので物足らなく思うリスナーもおられるかもしれないが、音楽そのものに語らせる本機の振る舞いに慣れると、音楽的介入が古臭く感じられてくるにちがいない。
本機はラックスマンの新しいサウンドの地平を指し示す象徴的なモデルである。
ラックスマンの新しいフラグシップ・パワーアンプ「M-900u」(関連ニュース)。位置づけ的には「M-800A」の後継機ということになるのだが、内容は完全に一新されており、ある部分では、同社の創業80周年を記念して造られた超弩級機の「B-1000f」(※生産完了)を超える存在になった。
フロントパネルの「容貌」は一変し、パワーメーターを備えたトラディショナルなものになった。このメーターは発光LEDによる電球色照明によって照らされる。筐体の剛性は非常に高く、質量こそ「M-800A」よりも500グラム軽い48kgになったが、緻密感や精密感は上昇しており、「B-1000f」に迫るほどだ。パワーアンプの基本的音色を決定づける重量バランスは非常に良好で、納品時やセッティング変更時に安心して移動させることができる(ただし、本機を持ち上げる際は絶対に複数名で作業すること!)。
回路は基本的にバランス方式で、入力バッファー段、ドライバー段、終段という3段構成だ。終段のパワートランジスタは3段ダーリントン4パラレルプッシュプルである。
ネガティブフィードバックはラックスマン独特のODNF4.0。これは歪成分のみをフィードバックさせ、ノイズを打ち消す画期的な回路のバージョン4.0であり、「M-800A」のバージョン2.3からずいぶん進歩したことになる。NFBをかけるかかけないかにはさまざまな議論があると思うが、個人的にはNFBを欠くアクロバティックな回路よりも、本機のような高度な帰還回路のほうが安心して使えると思う。
本機でもう一つ議論を呼ぶと思われるのが、終段のプッシュプル回路のバイアス電圧のかけ方である。「C-800A」が理論的に理想的なA級であったのに対して、本機は折衷案的なAB級が採用されているのだ。「A級アンプ原理主義者」は眉をひそめるかもしれない。だが、本機のスペックを冷静に検討していただきたい。
本機の出力は、スピーカー側のインピーダンスが8Ω時に150W×2、4Ω時に300W×2、2Ω時に600W×2、1Ω時に1200W(瞬間最大値)、と負荷抵抗値1Ωまでリニアに上昇している(ブリッジ接続時は8Ω時600W、2Ω時2400Wが保証される)。また、正式にはアナウンスされていないが、AB級動作機としてはバイアスが非常に深く、8Ω時に12W×2までがA級動作領域である。したがって1Ω時でも約100W×2までがA級動作の限界ということになる。これは必要十分なスペックではないだろうか?
それよりも問題なのは発熱だ。A級動作機は理論的には正しい音が出るはずではあるものの、大出力機になればなるほど素子や回路が熱をもち、音像のシャープネスや音場のトランスペアレンシーが低下してしまうのである。同社のA級動作プリメイン型機「L-590AX」のような30W×2(8Ω)程度の出力をもつモデルならば、発熱による影響は皆無なのだが、150W×2(8Ω)を純A級動作で得るのは得策ではない、というのが現在のラックスマンの技術陣のコンセンサスのようだ。
それでも本機の深いバイアスによる発熱は、彼らにとって看過できないレベルにあるらしく、トップパネルにはパンチングメタルを施された放熱孔が切られている(これが昔のフェラーリエンジンのキャブレターの吸気孔めいていて、個人的には滅茶苦茶シビれた)。
■試聴:「C-900u」との組み合わせでB&W「802 Diamond」を鳴らす
さて、本機のサウンドである。本機のペアとして開発された「C-900u」との組み合わせでB&W「802 Diamond」を鳴らしたのだが、まずは静寂感に鳥肌が立つほど驚いた。
これは「C-900u」の影響も強いのだろうが、音が出た瞬間、再びゾクゾクっときた。試聴に使用したのはフィッシャー指揮&ブダペスト祝祭管によるワーグナーの「神々の黄昏/ジークフリートの葬送行進曲」。無音の中から聴こえてくるティンパニーの弱奏が単なる小さい音ではなく、小さいけれども自らの意志をもった音のように感じられたのである。
そして低弦の慟哭のような力強い音が筆者の顔面を痛打して椅子から転げ落ちそうになった。この鳴らしにくいスピーカーのウーファーをこれほどグリップし、さらには低音を飛ばす能力のあるパワーアンプがオーディオ史上に一体何台あっただろうか。
これほどショッキングなサウンドを放つのにもかかわらず、本機は楽曲や演奏に対して音楽的な介入を一切しない。ただ、プリアンプ等から入力された信号をありのままに増幅してスピーカーをドライブするだけである。先代の「M-800A」が微かに音楽的介入をしたので物足らなく思うリスナーもおられるかもしれないが、音楽そのものに語らせる本機の振る舞いに慣れると、音楽的介入が古臭く感じられてくるにちがいない。
本機はラックスマンの新しいサウンドの地平を指し示す象徴的なモデルである。