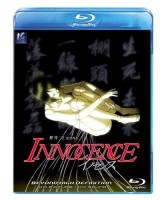話題のソフトを“Wooo”で観る − 第4回『イノセンス』 (Blu-ray Disc)
この連載「話題のソフトを“Wooo”で観る」では、AV評論家・大橋伸太郎氏が旬のソフトの見どころや内容をご紹介するとともに、“Wooo”薄型テレビで視聴した際の映像調整のコツなどについてもお伝えします。DVDソフトに限らず、放送や次世代光ディスクなど、様々なコンテンツをご紹介していく予定です。第4回はBlu-ray Discソフト『イノセンス』をお届けします。
押井守と「アニメーション」
ホームシアター誌の取材でずいぶん多くの読者に伺ったが、5年ほど前に出会った一人に、賃貸アパートでホームシアターを楽しんでいて『なかなかいいセンスをしているな』と思えた20代の若者がいた。彼に、あなたの尊敬する映画監督は? と訊いたら「押井守です」と返ってきて、ほう、そうなのかと思った。30~50代のホームシアターファンに同じ質問をすると、毎回必ず黒澤、ルーカス、コッポラ、スピルバーグ、キューブリックといった巨匠の名が挙がってきたからである。
『攻殻機動隊』でその名は知っていたが、情けないことに筆者は当時まだジャパニメーションに偏見があって見ていなかった。それから1~2年してクリエイターの高城剛氏のご自宅に伺った折、「日本の映画界にこれから天才級は出てきますか」と訊いたら、オマエは何を言うかとばかりに「エッ、そんなの、いっぱいいるじゃん」と目をまん丸くしておられた。氏の「天才リスト」の中にその時、その名が入っていたかは定かでない。しかし、2004年に『イノセンス』が公開された今はためらわずに言おう。押井守は現在の日本を最も代表する映画作家であると。
『イノセンス』に先立つ『攻殻機動隊』は、米ビルボード誌のビデオ総合チャートで発売第一週に売り上げ一位の快挙を達成、ジャパニメーションのポテンシャルについて、日本を含む世界に知らしめたエポックメイキングな作品である。しかし、『イノセンス』はそれをはるかに凌駕し新しい段階に入っている(熱心なファンの間には異論もあろうが)。実写に対するアニメーションの立ち位置から完全に離脱し、作品のテーマにおいても21世紀型映画である。
20世紀を代表する芸術である映画の90%が、人間のエモーション、行動、人格の発展を社会や歴史的・個人的事件、自然との関わりの中で描いてきた。映画のこの前提についてハリウッドでは“ヒューマンデべロップメント”と呼ぶのだそうだが、前19世紀にヨーロッパで言葉によって表現の頂点に達したテーマが、20世紀に映像という新しい皮袋の中に入ったと考えていい。恋愛に代表される心理と行動、人間観察という長編小説のテーマは、俳優の肉体と演技を通じて表現する映画という新しい表現方法と親和性が高く、小説からコンテンツを引き継ぐような形で映画はボーダーレスな発展を遂げたのである。その傍らで、描かれた絵が動く驚異としてアニメが誕生した。
20世紀末になり「人間」の捉え方が大きく変化した。人間も人間の作り出した電脳やテクノロジー、情報、あるいは国家さえも広義の「自然」であり、単純な相対化はできないという考え方である。社会的存在としてのロジカルな人間のみを前景においてその感情や行動を動線にしたコンテンツでそれは表現し切れない。人間という存在の深度を表現することは感情、生理、行動を掘り下げていくことだったから、役歴を持った俳優の既視感は観客にとってプラスだったし、何より肉体の生身の質感が必要だった。しかし、人間の「深度」の意味合いが変わった。抽象化された人間、つまりキャラクターを使った方が深く大きい普遍的な表現ができる場合もある。
『攻殻機動隊』の中で草薙素子は言う。「(真っ暗な海に潜っていると)恐れ、不安、孤独、闇、もしかしたら希望。海面に浮かび上がる時、違う自分になれるんじゃないかって、そんな気がする時がある」。これは原作漫画にないセリフだ。ハードなSFエンターテインメントの外観に包まれた押井守の作品世界の一つの核、宇宙感覚としての人間がここに集約されている。『攻殻機動隊』はまだアニメの段階に留まっていた。そこでは萌芽だった映画の新しい眺望が『イノセンス』で広々と開けたのである。押井守は語る。「(映画)全体の枠の中で実写というものは一つのカテゴリーに過ぎない」。『イノセンス』はもうアニメと呼ぶべきでなく、かといって特別なカテゴリーや名称を新たに考える必要もない。何より「現代の映画」と呼ぶのがふさわしい。
映画『イノセンス』をBlu-ray Discで見るということ
映画『イノセンス』は士郎正宗の漫画『攻殻機動隊』の中の「ROBOT ROND ロボットロンド」を脚色したものである。原作本を買う時、書店員に(本の中の)どのエピソードが『イノセンス』の話なの、と聞いたら、いやあ、あれは原作を置き去りにして押井さんが走っちゃっていますからねえ、と嬉しそうに教えてくれた。映画は原作の骨子を使ったに過ぎない。原作「ROBOT ROND ロボットロンド」の中心人物は草薙素子だが、映画版『攻殻機動隊』の最後、素子は義体(素子は脳以外を機械化したサイボーグ)を損壊し失踪してしまったので、『イノセンス』では最後にトムリアンデ型ロボットの一体の電脳に侵入し、今回の主人公バトーとトグサを助けるだけである。
ストーリーを紹介しておくと、同一型の愛玩用ロボット・トムリアンデが暴走し持ち主を殺して自壊する連続事件が発生した。新開発品を製造元が裕福な顧客に実験的に配ったのである。被害者の中に暴力団会長や公安関係者が含まれテロの可能性が否定できないため、公安九課・攻殻機動隊が捜査を任命された。七課のサイボーグ刑事バトーは、暴走を起こしたトムリアンデが特定の器官を持つセクサロイドで、破壊した機体の音声バッファには「助けて…」という断末魔が記録されていたことを知り、製造元ロクスソルフ社に接触を開始するが検査部長はすでに殺害されていた…。
原作になくて映画にあるものは「痛み」である。結末近く、救出された少女をバトーは一喝する。「犠牲者が出ることは考えなかったのか。人間のことじゃねえ。魂を吹き込まれた人形がどうなるかは考えなかったのか」。少女は「だって、私は人形になりたくなかったんだもん」と答える。トムリアンデの一体の声を借りて素子がいう。「人形たちも声があったら、人間になりたくないと叫んだでしょうね」。
原作では次のようだった。「被害者が出るとは考えなかったのか? お前たちがやらせたんだ、わかってるのか!?」「そんな。先に私たちに悪いことしたの外の人たちだもの…」。
映画版のテーマは、文化という自分の似姿を営々と作り続ける人間の業と欲望を「人形」に象徴させて描くことに変わった。ロボットへの「痛み」というと手塚治虫を連想するが、手塚が描いたものは、科学文明が生み出した新しい地球の成員と人間がいかに共生していくかというヒューマニズム哲学だった。『イノセンス』では人間とロボットの境界はもはやあいまいになっていて、“ゴースト”の有無がかろうじて最後の一線である。人間とロボットを相対的にとらえるのでなく、大きな連続感の中でモラリスト・押井守が感じる痛みである。
前作から9年間の歳月を反映し『イノセンス』の映像は途方もない進歩を遂げた。択捉経済特区のビジュアルは圧巻でこれも映画版の創意である。本作は2DアニメとCGで成立しているが、動画キャラクターに付き物だった描線は限りなく細く、ソフトなグラデーションを持つ淡い影が動いていくような表現である。
押井作品の情報量の多さは今作で始まったことではないが、本作では目立たない所で映像に厚みを出すため、ロングシーンで描き込まれる小さな群集のせめて3割を動かしてほしいと、押井が作画担当者に懇願したそうだ。こうした創意と情熱、技術の塊のような『イノセンス』をハイビジョンディスクで、そして最新の大画面プラズマディスプレイで見られることは本当に素晴らしいことだと思う。押井の世界観は唯一無二の色彩によって構築されている。非難の対象になった引用が多くて哲学的で饒舌なセリフと同様、現実にはありえないものを出してくることでリアリティが生まれるのだ。

視聴には「W42P-HR9000」を使用した視聴に使用した日立の42V型プラズマテレビ「W42P-HR9000」は垂直解像度1080画素のハイビジョン対応機で、ブルーレイ版『イノセンス』の画面密度を余すところなく掬い上げるばかりでなく、画像処理エンジン“Picture Master HD”が、既発売のDVDに比べて格段にパレットを広げたハイビジョンの広大な色の世界を作者の意図に忠実に描き分ける。テーマとメディアの関係について先に「新しい酒は新しい皮袋に」と書いたが、ソフトとそれを見るディスプレイについてもそうありたい。W42P-HR9000はこの新しい映画ソフトを鑑賞するのに、まことにふさわしい製品といえるだろう。
AV的な見所と画質調整のポイント
視聴は照度100ルクス前後の筆者仕事場で、入力にはソニーのPLAYSTATION3を使用した。セットアップ時のディスプレイ自動設定でW42P-HR9000は720pと判定されたので、手動で1080iに変更した。1080pでの入力はできない。ちなみに、PS3はブルーレイディスクの再生にはデリケートな面があり、取り扱ううちに指紋がついたディスクを一度再生できなくなった。階下で使用中のパナソニックの北米仕様の再生専用機ではそのようなことはなかった。
映画を見る場合のセットアップの基本は、一作を通して見る色温度の設定だ。『イノセンス』は一種のフィルムノワールでありダークシーンが多い。行動的でハイテンション、ギャグも多い原作に比べて、映画は苦悩に満ちた世界観である。だからといって、映像をペシミスティックに暗く沈ませてはならない。文明とは人間が違和感や不安を覚えても後戻りはできないものであり、一日でも先の未来を見たいという人間の普遍的な欲望がSFを生み映画を生み、そこに活力を吹き込み続けているのだ。
押井監督とて、いままで見られなかった凄いものを見せたくてこの映画を作ったのだろうから。繊細な描画を活かし、キャラクターのみ前景に置いたアニメの平板さに帰らないことを心掛ける一方で、冴えた力強い画面を映像調整で狙った。シックな色彩を活かすことはいうまでもない。
ただし、『イノセント』は、平均明度の高いシーンと低いシーンの差が実写映画ではありえないほど大きく、しかも急峻に移り変わるから、コントラストと黒レベル(ブライトネス)の設定に手こずる。それ以外の、例えば色再現はデフォルトの設定のままで非常に美しい官能的な色彩を味わうことができ、RGBドライブ/カットオフのゲイン調整に入っていく必要はなかった。2Dで描かれた人物なので、微妙なグラデーションがなくノイズが目立ちやすいので実写映画でオフにすることの多いYNRは弱に設定した。結局、下記の設定で、冴えていると同時にソフトなトーン、鮮烈でありながらシックな色彩という再生上の相反する課題をW42P-HR9000はみごとに表現し、最後まで快適に見ることができた。
映像モード: シネマティック
明るさ:-20
黒レベル:+3
色の濃さ:-8
色合い:0
画質:-15
色温度:中
ディテール:切
コントラスト:リニア
黒補正:切
LTI:切
CTI:切
YNR:弱
CNR:弱
ポイントとなるシーンを一つ挙げるなら、CH10の択捉経済特区の祭りのシーンだろう。世界中、未来にさえももありえない場所を描いて、幼い時に畏怖を持って見上げた都会の記憶につながる懐かしさがある。CGと2Dアニメで前景、中景、後景の重層的奥行きを巧みに表現していて、これがもっと深い奥行きを感じさせるようになるといい。筆者が普段は使わないW42-HR9000の黒補正を「弱」にしてみた。すると増殖した高層建築群の谷間の街並みに射す影が濃く深くなり、憂愁を感じさせる映像になった。ただし、より照明を落とした環境(今回は手元照度計で100ルクスで視聴)では、黒が重く感じられるかもしれない。このブルーレイディスク版『イノセンス』と日立W42P-HR9000のコンビネーション、ご覧になる方すべてに至上の映像体験を与えてくれるに違いない。
(大橋伸太郎)
大橋伸太郎 プロフィール
1956 年神奈川県鎌倉市生まれ。早稲田大学第一文学部卒。フジサンケイグループにて、美術書、児童書を企画編集後、(株)音元出版に入社、1990年『AV REVIEW』編集長、1998年には日本初にして現在も唯一の定期刊行ホームシアター専門誌『ホームシアターファイル』を刊行した。ホームシアターのオーソリティとして講演多数2006年に評論家に転身。趣味はウィーン、ミラノなど海外都市訪問をふくむコンサート鑑賞、アスレチックジム、ボルドーワイン。
バックナンバー
・第1回『ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女』
・第2回『アンダーワールド2 エボリューション』
・第3回『ダ・ヴィンチ・コード』
押井守と「アニメーション」
ホームシアター誌の取材でずいぶん多くの読者に伺ったが、5年ほど前に出会った一人に、賃貸アパートでホームシアターを楽しんでいて『なかなかいいセンスをしているな』と思えた20代の若者がいた。彼に、あなたの尊敬する映画監督は? と訊いたら「押井守です」と返ってきて、ほう、そうなのかと思った。30~50代のホームシアターファンに同じ質問をすると、毎回必ず黒澤、ルーカス、コッポラ、スピルバーグ、キューブリックといった巨匠の名が挙がってきたからである。
『攻殻機動隊』でその名は知っていたが、情けないことに筆者は当時まだジャパニメーションに偏見があって見ていなかった。それから1~2年してクリエイターの高城剛氏のご自宅に伺った折、「日本の映画界にこれから天才級は出てきますか」と訊いたら、オマエは何を言うかとばかりに「エッ、そんなの、いっぱいいるじゃん」と目をまん丸くしておられた。氏の「天才リスト」の中にその時、その名が入っていたかは定かでない。しかし、2004年に『イノセンス』が公開された今はためらわずに言おう。押井守は現在の日本を最も代表する映画作家であると。
『イノセンス』に先立つ『攻殻機動隊』は、米ビルボード誌のビデオ総合チャートで発売第一週に売り上げ一位の快挙を達成、ジャパニメーションのポテンシャルについて、日本を含む世界に知らしめたエポックメイキングな作品である。しかし、『イノセンス』はそれをはるかに凌駕し新しい段階に入っている(熱心なファンの間には異論もあろうが)。実写に対するアニメーションの立ち位置から完全に離脱し、作品のテーマにおいても21世紀型映画である。
20世紀を代表する芸術である映画の90%が、人間のエモーション、行動、人格の発展を社会や歴史的・個人的事件、自然との関わりの中で描いてきた。映画のこの前提についてハリウッドでは“ヒューマンデべロップメント”と呼ぶのだそうだが、前19世紀にヨーロッパで言葉によって表現の頂点に達したテーマが、20世紀に映像という新しい皮袋の中に入ったと考えていい。恋愛に代表される心理と行動、人間観察という長編小説のテーマは、俳優の肉体と演技を通じて表現する映画という新しい表現方法と親和性が高く、小説からコンテンツを引き継ぐような形で映画はボーダーレスな発展を遂げたのである。その傍らで、描かれた絵が動く驚異としてアニメが誕生した。
20世紀末になり「人間」の捉え方が大きく変化した。人間も人間の作り出した電脳やテクノロジー、情報、あるいは国家さえも広義の「自然」であり、単純な相対化はできないという考え方である。社会的存在としてのロジカルな人間のみを前景においてその感情や行動を動線にしたコンテンツでそれは表現し切れない。人間という存在の深度を表現することは感情、生理、行動を掘り下げていくことだったから、役歴を持った俳優の既視感は観客にとってプラスだったし、何より肉体の生身の質感が必要だった。しかし、人間の「深度」の意味合いが変わった。抽象化された人間、つまりキャラクターを使った方が深く大きい普遍的な表現ができる場合もある。
『攻殻機動隊』の中で草薙素子は言う。「(真っ暗な海に潜っていると)恐れ、不安、孤独、闇、もしかしたら希望。海面に浮かび上がる時、違う自分になれるんじゃないかって、そんな気がする時がある」。これは原作漫画にないセリフだ。ハードなSFエンターテインメントの外観に包まれた押井守の作品世界の一つの核、宇宙感覚としての人間がここに集約されている。『攻殻機動隊』はまだアニメの段階に留まっていた。そこでは萌芽だった映画の新しい眺望が『イノセンス』で広々と開けたのである。押井守は語る。「(映画)全体の枠の中で実写というものは一つのカテゴリーに過ぎない」。『イノセンス』はもうアニメと呼ぶべきでなく、かといって特別なカテゴリーや名称を新たに考える必要もない。何より「現代の映画」と呼ぶのがふさわしい。
映画『イノセンス』をBlu-ray Discで見るということ
映画『イノセンス』は士郎正宗の漫画『攻殻機動隊』の中の「ROBOT ROND ロボットロンド」を脚色したものである。原作本を買う時、書店員に(本の中の)どのエピソードが『イノセンス』の話なの、と聞いたら、いやあ、あれは原作を置き去りにして押井さんが走っちゃっていますからねえ、と嬉しそうに教えてくれた。映画は原作の骨子を使ったに過ぎない。原作「ROBOT ROND ロボットロンド」の中心人物は草薙素子だが、映画版『攻殻機動隊』の最後、素子は義体(素子は脳以外を機械化したサイボーグ)を損壊し失踪してしまったので、『イノセンス』では最後にトムリアンデ型ロボットの一体の電脳に侵入し、今回の主人公バトーとトグサを助けるだけである。
ストーリーを紹介しておくと、同一型の愛玩用ロボット・トムリアンデが暴走し持ち主を殺して自壊する連続事件が発生した。新開発品を製造元が裕福な顧客に実験的に配ったのである。被害者の中に暴力団会長や公安関係者が含まれテロの可能性が否定できないため、公安九課・攻殻機動隊が捜査を任命された。七課のサイボーグ刑事バトーは、暴走を起こしたトムリアンデが特定の器官を持つセクサロイドで、破壊した機体の音声バッファには「助けて…」という断末魔が記録されていたことを知り、製造元ロクスソルフ社に接触を開始するが検査部長はすでに殺害されていた…。
原作になくて映画にあるものは「痛み」である。結末近く、救出された少女をバトーは一喝する。「犠牲者が出ることは考えなかったのか。人間のことじゃねえ。魂を吹き込まれた人形がどうなるかは考えなかったのか」。少女は「だって、私は人形になりたくなかったんだもん」と答える。トムリアンデの一体の声を借りて素子がいう。「人形たちも声があったら、人間になりたくないと叫んだでしょうね」。
原作では次のようだった。「被害者が出るとは考えなかったのか? お前たちがやらせたんだ、わかってるのか!?」「そんな。先に私たちに悪いことしたの外の人たちだもの…」。
映画版のテーマは、文化という自分の似姿を営々と作り続ける人間の業と欲望を「人形」に象徴させて描くことに変わった。ロボットへの「痛み」というと手塚治虫を連想するが、手塚が描いたものは、科学文明が生み出した新しい地球の成員と人間がいかに共生していくかというヒューマニズム哲学だった。『イノセンス』では人間とロボットの境界はもはやあいまいになっていて、“ゴースト”の有無がかろうじて最後の一線である。人間とロボットを相対的にとらえるのでなく、大きな連続感の中でモラリスト・押井守が感じる痛みである。
前作から9年間の歳月を反映し『イノセンス』の映像は途方もない進歩を遂げた。択捉経済特区のビジュアルは圧巻でこれも映画版の創意である。本作は2DアニメとCGで成立しているが、動画キャラクターに付き物だった描線は限りなく細く、ソフトなグラデーションを持つ淡い影が動いていくような表現である。
押井作品の情報量の多さは今作で始まったことではないが、本作では目立たない所で映像に厚みを出すため、ロングシーンで描き込まれる小さな群集のせめて3割を動かしてほしいと、押井が作画担当者に懇願したそうだ。こうした創意と情熱、技術の塊のような『イノセンス』をハイビジョンディスクで、そして最新の大画面プラズマディスプレイで見られることは本当に素晴らしいことだと思う。押井の世界観は唯一無二の色彩によって構築されている。非難の対象になった引用が多くて哲学的で饒舌なセリフと同様、現実にはありえないものを出してくることでリアリティが生まれるのだ。

視聴には「W42P-HR9000」を使用した
AV的な見所と画質調整のポイント
視聴は照度100ルクス前後の筆者仕事場で、入力にはソニーのPLAYSTATION3を使用した。セットアップ時のディスプレイ自動設定でW42P-HR9000は720pと判定されたので、手動で1080iに変更した。1080pでの入力はできない。ちなみに、PS3はブルーレイディスクの再生にはデリケートな面があり、取り扱ううちに指紋がついたディスクを一度再生できなくなった。階下で使用中のパナソニックの北米仕様の再生専用機ではそのようなことはなかった。
映画を見る場合のセットアップの基本は、一作を通して見る色温度の設定だ。『イノセンス』は一種のフィルムノワールでありダークシーンが多い。行動的でハイテンション、ギャグも多い原作に比べて、映画は苦悩に満ちた世界観である。だからといって、映像をペシミスティックに暗く沈ませてはならない。文明とは人間が違和感や不安を覚えても後戻りはできないものであり、一日でも先の未来を見たいという人間の普遍的な欲望がSFを生み映画を生み、そこに活力を吹き込み続けているのだ。
押井監督とて、いままで見られなかった凄いものを見せたくてこの映画を作ったのだろうから。繊細な描画を活かし、キャラクターのみ前景に置いたアニメの平板さに帰らないことを心掛ける一方で、冴えた力強い画面を映像調整で狙った。シックな色彩を活かすことはいうまでもない。
ただし、『イノセント』は、平均明度の高いシーンと低いシーンの差が実写映画ではありえないほど大きく、しかも急峻に移り変わるから、コントラストと黒レベル(ブライトネス)の設定に手こずる。それ以外の、例えば色再現はデフォルトの設定のままで非常に美しい官能的な色彩を味わうことができ、RGBドライブ/カットオフのゲイン調整に入っていく必要はなかった。2Dで描かれた人物なので、微妙なグラデーションがなくノイズが目立ちやすいので実写映画でオフにすることの多いYNRは弱に設定した。結局、下記の設定で、冴えていると同時にソフトなトーン、鮮烈でありながらシックな色彩という再生上の相反する課題をW42P-HR9000はみごとに表現し、最後まで快適に見ることができた。
映像モード: シネマティック
明るさ:-20
黒レベル:+3
色の濃さ:-8
色合い:0
画質:-15
色温度:中
ディテール:切
コントラスト:リニア
黒補正:切
LTI:切
CTI:切
YNR:弱
CNR:弱
ポイントとなるシーンを一つ挙げるなら、CH10の択捉経済特区の祭りのシーンだろう。世界中、未来にさえももありえない場所を描いて、幼い時に畏怖を持って見上げた都会の記憶につながる懐かしさがある。CGと2Dアニメで前景、中景、後景の重層的奥行きを巧みに表現していて、これがもっと深い奥行きを感じさせるようになるといい。筆者が普段は使わないW42-HR9000の黒補正を「弱」にしてみた。すると増殖した高層建築群の谷間の街並みに射す影が濃く深くなり、憂愁を感じさせる映像になった。ただし、より照明を落とした環境(今回は手元照度計で100ルクスで視聴)では、黒が重く感じられるかもしれない。このブルーレイディスク版『イノセンス』と日立W42P-HR9000のコンビネーション、ご覧になる方すべてに至上の映像体験を与えてくれるに違いない。
(大橋伸太郎)
大橋伸太郎 プロフィール
1956 年神奈川県鎌倉市生まれ。早稲田大学第一文学部卒。フジサンケイグループにて、美術書、児童書を企画編集後、(株)音元出版に入社、1990年『AV REVIEW』編集長、1998年には日本初にして現在も唯一の定期刊行ホームシアター専門誌『ホームシアターファイル』を刊行した。ホームシアターのオーソリティとして講演多数2006年に評論家に転身。趣味はウィーン、ミラノなど海外都市訪問をふくむコンサート鑑賞、アスレチックジム、ボルドーワイン。
バックナンバー
・第1回『ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女』
・第2回『アンダーワールド2 エボリューション』
・第3回『ダ・ヴィンチ・コード』