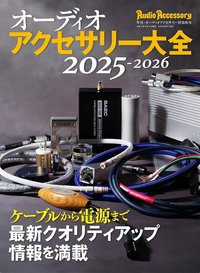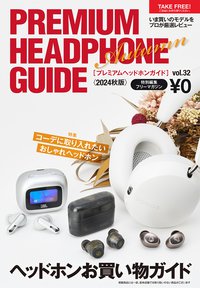会田肇が速攻チェック - レンズ交換式ビデオカメラ「NEX-VG10」の実力は?
■レンズ交換型ゆえの独特な使用スタイル
本体の重さは620gだが、標準のレンズやバッテリー等を加えた撮影時重量は約1.3kg。それだけに、VG10を手にするとややズシリとした重さを感じさせる。標準装備されるバッテリー(NP-FV70)を付けた状態では、レンズの重さもあって、ややフロントヘビーになる。ただしグリップ部分がしっかりとしていることもあって、手首への負担はさほど感じさせない。
撮影するスタイルは、モニターを開いたり、ファインダーを通じたりと、基本的にこれまでのハンディカムと同じだ。フリーアングルのモニターを備えたことで、ロー/ハイアングル撮影ではNEX-5/3よりもはるかに扱いやすい。
しかし、ズーム操作では従来のハンディカムとの違いを実感する。電動ズームが搭載されておらず、通常のデジタル一眼と同様、手動でズーム操作を行う必要があるからだ。つまり、電動ズームを使った定速ズーミングと同じ事をやろうと思ったら、よほど熟練しないと実現は難しい。というよりも、本機のズーム機能はトリミング変更用であって、動画撮影中のズーム操作は目的外の機能と割り切った方が良いかもしれない。
VG10で見逃せないのは、動画撮影時の絞りやシャッター速度、ゲイン、ホワイトバランスなどの各種調整を可能としていることだ。ハンディカムを使い慣れている人からすれば、つい画面上をタッチしてしまいそうになるが、操作は本体側に備えられたコントロールジョグダイヤルやホットキーを組み合わせて行う。
操作はボタンの位置を覚えるまで多少慣れが必要と感じたが、一度慣れてしまえば難しいということはない。それでも、メニューとの関係をもう少し整理して、より直感的に操作できると良かったように思う。また、αレンズを組み合わせた時のオートフォーカスはNEX-5/3と同様、VG10でも動作しないので注意したい。
■これまでのビデオカメラでは得られなかった“感動映像”
さて、VG10の画質だが、試作機レベルとはいえ、映像を通して伝わる解像感、空気感は、従来のハンディカムとは明らかに次元の違いを感じさせるものだった。風で揺れる木々はそのざわめきまでも画面から伝わってきそうだし、水面にできる波紋はどこか爽やかな印象を感じさせる。
奥にある被写体にフォーカスを合わせ、手前の植え込みをボカしてみる。この時に得られるボケ味の美しさを見ただけでも鳥肌が立つ。
夜景撮影に場を移してみると、決して明るすぎず、自然な露出で夜景を表現。ノイズはしっかりと抑えられ、夜空を妙に明るくすることもない。ここで夜景のイルミをボカしてみたら、これが完全な円形ボケ。ここまで美しいボケはこれまでになかったもので、感動させられる。
続いて、αレンズを組み合わせて撮影してみた。今回はF1.8/135mmレンズを組み合わせ、モニターに浮かぶ被写体にピントを合わせてみる。すると、前後がボケる中に被写体がフワッと浮かび上がった。
こうしたカットは写真でこそ見たことはあったが、動く動画として、しかもコンシューマ用カメラという身近な存在でこれが実現できるだからたまらない。映像が感動を生み出すとはこういうことなんだ、と改めて実感した次第だ。
ソニーはこれまで数々のハンディカムを世に送り出してきたが、コンシューマ用機器ゆえの様々な制約の中で、妥協せざるを得なかったのは否めない。
それが一眼デジカメをベースにした新たなデバイスを得たことで、これまでの制約がなくなり、思い切った映像へのこだわりへと突き進むことができた。生い立ちこそ一眼デジカメであるにもかかわらず、あえてハンディカムの名を冠したのもそうした想いが反映されているからではないだろうか。
撮ることへの妥協なきスペックをハンディカムが手中に収めた。NEX-VG10はそんなハンディカムの新しいページを切り拓く、記念すべき一台なのだ。
会田肇 プロフィール
1956年、茨城県生まれ。明治大学政治経済学部卒。自動車雑誌編集者を経てフリーとなる。クルマ、スポーツ、旅行などアウトドアの趣味を多く持ち、アウトドア系オーディオビジュアルライターとしての第一人者。カー雑誌などでカーナビをはじめとするカーAVを中心とした取材、執筆に従事する一方で、ビデオカメラやデジタルカメラの批評活動を積極的に続けている。