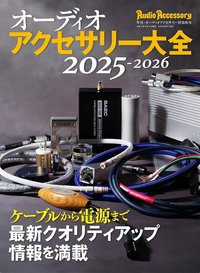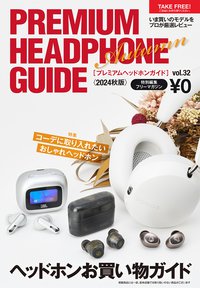「オーディオ哲学宗教談義」
【対談】オーディオは本当に進歩したのか<第1回> 哲学者・黒崎政男氏と宗教学者・島田裕巳氏が語る
コルトレーン『至上の愛』の精神性と宗教性
黒崎 聴かなかったもん、『ビッチェス・ブリュー』。今でも聴きません。実は、マイルスの60年代は今回ワルシャワ再生(黒崎自宅にてアナログ復活の意)になってから、初めてちゃんと聴くようになった。『カインド・オブ・ブルー』から『フォア&モア』『マイルス・スマイルズ』など素晴らしい10年間。ピアノがビル・エヴァンスなのかウィントン・ケリーなのか。ドラムスはトニー・ウィリアムスが入ったか。サックスはまだジョージ・コールマンか。などメンバーの違いが面白くて、マイルスのステレオ盤が面白くなった。だけど、エレキになる『ビッチェス・ブリュー』以降は、今回もやっぱり聴く気にならない。
もう一度コルトレーンに話を戻しましょう。我々「わざわざかけたくない」「ずっと聴いていない」というアルバムがあるんですよ。
島田 『至上の愛』なんて好きじゃない。何回も聴こうなんて思えない。どう聴いていいか分からない。
黒崎 何回も聴けるものじゃないよね。
島田 確かに神がかっているコルトレーンを当時聴いていたけど、本当に好きかというとどうだか。
黒崎 僕は本当に好きだった。
一同 (笑)
島田 以前、新宿のDIGでコルトレーンの命日にコルトレーンだけをずっとかけるというイベントがあって、それに友人と行ったんだけど、友人の方は憑依状態で聴いているわけです。私はやっぱりそういう風にはならない。一応、宗教学者なので。
一同 (笑)
島田 『コルトレーン・ジャパン』など長過ぎるし。
黒崎 私はコルトレーンを心から愛していましたね。その頂点が『至上の愛』。でもそれはしょっちゅう聴けるものではない。
島田 マタイは?
黒崎 バッハのマタイ受難曲は案外母性的なのでそう距離はないのです。リヒターの『音楽の捧げ物』は精神を高めて聴く。さっきかけたカンタータ26番はピークよリは少し下がった感じで聴けます。バッハの曲の中でも私の中にはヒエラルキーがあって、一番高尚なのと、気楽なものがある。今日の自分はここまでいけないから、この辺りを聴いておこう、とか。すごく厳密だった。
一同 (笑)
黒崎 シェリングの『無伴奏ヴァイオリン』は、もう最高。カザルスの『無伴奏チェロ』は、それよりはちょっと気楽。高校時代にそういうヒエラルキーがありました。
それとは別にコルトレーンは素晴らしい。『至上の愛』が頂点で、『Transition(トランジション)』(Impulse)
なんかはその次くらい。『至上の愛』は自分の精神状態を高めてから聴いていたんですが、最近は聴くのがつらくなってきた。
島田 なぜ?
黒崎 我々にとって「精神性」という価値が変化してきたからだと思います。今は「精神が……」などという言葉を使わなくなってきているけれども、70年代から80年代中までは、精神性とか、崇高とか、超越的なもの……というのが色濃くあった。それが80年中から90年にかけてフラットになって、今や完全に崩れた。むしろ、再構築しようかなという雰囲気があるけれども。
だから、80年代以降は、価値を追求するようなコルトレーンの音楽にはかえって苦痛を覚えるようになりました。だからもう何十年も聴いていないんですよ。
島田 あんなのずっと聴かされていたらどうかなっちゃう。今から聴くの? なんだか恐ろしくなってきた!
一同 (笑)
黒崎 リンLP12とKLIMAX EXAKT 350 Katalystで「パート1」を聴きましょうか。10分くらいかな。今日のテーマのひとつとなる、ジョン・コルトレーン『至上の愛』です。
~ジョン・コルトレーン『至上の愛』「PART 1」試聴~
島田 演奏の仕方が、奔放とかではなく、すごく抑制がきいています。リンの機材が特にそう聴こえさせるのかもしれないし、楽曲そのものがそうなのかもしれないけれど。コルトレーンの中に「こういう風にしなきゃいけない」という感じが見え隠れしてる。それまでのコルトレーンの演奏にあった音色や表現が『至上の愛』にはない。どうでしたか? 久しぶりに聴いて。
黒崎 私は、まず、当時を思い出して懐かしかったすね。リンだとさすがにノイズがなくて、何か冷静というか客観的に聴こえる。他方、このアルバムを、ヴィンテージのシステムで聴くと、70年代初頭の当時のざわつき……というか熱気がすごい。RCAプレーヤー+JBLハーツフィールドの方が合っている。
島田 あの頃このリンの音で聴けたら、世の中コルトレーンに騒がなかったかもね。
一同 (笑)
黒崎 私は最古が最善だと思っていて、SPレコードが最高だと思っています。つまり蓄音器。LPになると、繊細な表現は増えるけど熱が下がる。LPとCDを比べると、やはり熱はLPの方があります。「熱」ということでいえば、当時性というか古い方がいい。
島田 宗教学的にいうと、アメリカのミュージシャンはジャズだけでなくロックでもゴスペルの影響もすごく強く受けています。音楽の才能がある子供は、大抵、教会にスカウトされて聖歌隊に送られるかオルガン弾きになる。必ずみんなそういう経歴を辿っているんですよね。例えば、カーペンターズのお兄さんもオルガン弾きから始まった。カーペンターズのレコードを見ても、一部ゴスペルがあります。
当時のアメリカは一度売れると環境が180度変わるくらい爆発的に売れて、アルコールやドラッグに溺れることも少なくありません。これじゃだめだと思ったとき彼らを救うのは、やはりキリスト教なのです。罪深さを感じて改心体験をすると、音楽も変わって神の愛なんかを歌うようになる。そうしたとき、たいていゴスペルという音楽が使われるんです。ところが、『至上の愛』はゴスペルではない。『至上の愛』の神様は、マルコムXやイスラム教に近いような気がしますね。一緒に人間と楽しんだり歌ってくれるのではない。
黒崎 超越的な感じ。トランスセンデントな。
島田 そうですね。ジャケットには、コルトレーンの神に対する賛美の詩が書いてありますね。しかし音楽性でいえば、体の中に染み込んでいるものではないaような。
黒崎 もっと外的なことだと。
島田 その辺りが、聴いていて苦しいと感じてしまう部分かなと思います。
黒崎 ベートーヴェンは耳が聞こえなくなって悩むでしょう? さらに晩年はさまざまな身体的重苦があった。でもほんの一瞬治る時があったのです。後期ですけれど、弦楽四重奏曲の中に、神に感謝するという楽章があって、ものすごくホッとした素晴らしい楽章なのです。麻薬中毒から抜けられたとか、病気が治ったとか、苦しさから解放された時の神への感謝というのがありますが、島田さんの仰るコルトレーンのプレイはそういうものよりはもっと抽象的な?
島田 ええ、かなり抽象的ですね。コルトレーンの中に土着的な部分があったかなかったかは、ちょっと分からないです。例えば、キース・ジャレットなんかでもフリーで自由に弾きますけど、ベースはゴスペルです。だから彼のゴスペル的部分が出てくることで、音楽性が表れるわけです。
黒崎 『ケルン・コンサート』とか。
島田 なので、キースがバッハとかクラシックをやると、ゴスペルが入ってきてちょっと変な感じがするんですよね。
黒崎 ジャズの歴史ってサッチモ、つまりルイ・アーム・ストロングが1925年から30年くらいに、数ドルもらって1枚吹込むってことでホット5かホット7とかって、100曲くらい入れて、っていうところから始まっている。黒人の苦しみから始まりましたよね。25年のサッチモを蓄音器で聴いていて特にそれを感じますし、チャーリー・パーカーについてはめちゃくちゃな人だけど、やはり彼自身の中から溢れ出るものがある。しかし、コルトレーンは、借りてきた神だった?
島田 借りてきた……というより、コルトレーンは考え過ぎていますよね。
黒崎 頭の神。ということはつまり、あれはコルトレーンの勝手な思い込みに時代が反応してしまったと。
島田 ちょっとおかしくなっていたのでしょう、本人が。とにかく吹き続ける。止まらない。『ライブ・イン・ジャパン』なんかまさにそういう状態。
黒崎 僕の目論見では、バッハという崇高なものを聴くのと、『至上の愛』を聴くのは、当時の精神性という意味においてオーバーラップし同一性があったのが、時代とともに音楽から精神性とか崇高性とかいうものが切り取られてフラットになってしまった。そういう今、コルトレーンは辛いよね、という図式だったわけですよ。そうじゃないというわけですね? むしろ、不自然であると?
島田 どうでしょうか。まあでも、単純には楽しめないんですよね。時代のひとコマではあったけれども、そうした文脈なしに今ジャズを聴き始めた人が『至上の愛』を聴いて好きになるかというと、なかなか難しいんじゃないでしょうか。
黒崎 その点、バッハのカンタータは受け入れられてますよね。
島田 バッハは作曲家だけど、コルトレーンは演奏家ですからね。演奏家はその時代の生身の人間であるということが前提としてあります。それに対してバッハは解釈があり得るので。
黒崎 バッハについても、カール・リヒターが70年代までやったけれども、そこから急激に古楽ブームが起こって、リヒターの精神性が否定されていき、もっと身体的な快楽になっていきましたね。
黒崎 聴かなかったもん、『ビッチェス・ブリュー』。今でも聴きません。実は、マイルスの60年代は今回ワルシャワ再生(黒崎自宅にてアナログ復活の意)になってから、初めてちゃんと聴くようになった。『カインド・オブ・ブルー』から『フォア&モア』『マイルス・スマイルズ』など素晴らしい10年間。ピアノがビル・エヴァンスなのかウィントン・ケリーなのか。ドラムスはトニー・ウィリアムスが入ったか。サックスはまだジョージ・コールマンか。などメンバーの違いが面白くて、マイルスのステレオ盤が面白くなった。だけど、エレキになる『ビッチェス・ブリュー』以降は、今回もやっぱり聴く気にならない。
もう一度コルトレーンに話を戻しましょう。我々「わざわざかけたくない」「ずっと聴いていない」というアルバムがあるんですよ。
島田 『至上の愛』なんて好きじゃない。何回も聴こうなんて思えない。どう聴いていいか分からない。
黒崎 何回も聴けるものじゃないよね。
島田 確かに神がかっているコルトレーンを当時聴いていたけど、本当に好きかというとどうだか。
黒崎 僕は本当に好きだった。
一同 (笑)
島田 以前、新宿のDIGでコルトレーンの命日にコルトレーンだけをずっとかけるというイベントがあって、それに友人と行ったんだけど、友人の方は憑依状態で聴いているわけです。私はやっぱりそういう風にはならない。一応、宗教学者なので。
一同 (笑)
島田 『コルトレーン・ジャパン』など長過ぎるし。
黒崎 私はコルトレーンを心から愛していましたね。その頂点が『至上の愛』。でもそれはしょっちゅう聴けるものではない。
島田 マタイは?
黒崎 バッハのマタイ受難曲は案外母性的なのでそう距離はないのです。リヒターの『音楽の捧げ物』は精神を高めて聴く。さっきかけたカンタータ26番はピークよリは少し下がった感じで聴けます。バッハの曲の中でも私の中にはヒエラルキーがあって、一番高尚なのと、気楽なものがある。今日の自分はここまでいけないから、この辺りを聴いておこう、とか。すごく厳密だった。
一同 (笑)
黒崎 シェリングの『無伴奏ヴァイオリン』は、もう最高。カザルスの『無伴奏チェロ』は、それよりはちょっと気楽。高校時代にそういうヒエラルキーがありました。
それとは別にコルトレーンは素晴らしい。『至上の愛』が頂点で、『Transition(トランジション)』(Impulse)
なんかはその次くらい。『至上の愛』は自分の精神状態を高めてから聴いていたんですが、最近は聴くのがつらくなってきた。
島田 なぜ?
黒崎 我々にとって「精神性」という価値が変化してきたからだと思います。今は「精神が……」などという言葉を使わなくなってきているけれども、70年代から80年代中までは、精神性とか、崇高とか、超越的なもの……というのが色濃くあった。それが80年中から90年にかけてフラットになって、今や完全に崩れた。むしろ、再構築しようかなという雰囲気があるけれども。
だから、80年代以降は、価値を追求するようなコルトレーンの音楽にはかえって苦痛を覚えるようになりました。だからもう何十年も聴いていないんですよ。
島田 あんなのずっと聴かされていたらどうかなっちゃう。今から聴くの? なんだか恐ろしくなってきた!
一同 (笑)
黒崎 リンLP12とKLIMAX EXAKT 350 Katalystで「パート1」を聴きましょうか。10分くらいかな。今日のテーマのひとつとなる、ジョン・コルトレーン『至上の愛』です。
~ジョン・コルトレーン『至上の愛』「PART 1」試聴~
島田 演奏の仕方が、奔放とかではなく、すごく抑制がきいています。リンの機材が特にそう聴こえさせるのかもしれないし、楽曲そのものがそうなのかもしれないけれど。コルトレーンの中に「こういう風にしなきゃいけない」という感じが見え隠れしてる。それまでのコルトレーンの演奏にあった音色や表現が『至上の愛』にはない。どうでしたか? 久しぶりに聴いて。
黒崎 私は、まず、当時を思い出して懐かしかったすね。リンだとさすがにノイズがなくて、何か冷静というか客観的に聴こえる。他方、このアルバムを、ヴィンテージのシステムで聴くと、70年代初頭の当時のざわつき……というか熱気がすごい。RCAプレーヤー+JBLハーツフィールドの方が合っている。
島田 あの頃このリンの音で聴けたら、世の中コルトレーンに騒がなかったかもね。
一同 (笑)
黒崎 私は最古が最善だと思っていて、SPレコードが最高だと思っています。つまり蓄音器。LPになると、繊細な表現は増えるけど熱が下がる。LPとCDを比べると、やはり熱はLPの方があります。「熱」ということでいえば、当時性というか古い方がいい。
島田 宗教学的にいうと、アメリカのミュージシャンはジャズだけでなくロックでもゴスペルの影響もすごく強く受けています。音楽の才能がある子供は、大抵、教会にスカウトされて聖歌隊に送られるかオルガン弾きになる。必ずみんなそういう経歴を辿っているんですよね。例えば、カーペンターズのお兄さんもオルガン弾きから始まった。カーペンターズのレコードを見ても、一部ゴスペルがあります。
当時のアメリカは一度売れると環境が180度変わるくらい爆発的に売れて、アルコールやドラッグに溺れることも少なくありません。これじゃだめだと思ったとき彼らを救うのは、やはりキリスト教なのです。罪深さを感じて改心体験をすると、音楽も変わって神の愛なんかを歌うようになる。そうしたとき、たいていゴスペルという音楽が使われるんです。ところが、『至上の愛』はゴスペルではない。『至上の愛』の神様は、マルコムXやイスラム教に近いような気がしますね。一緒に人間と楽しんだり歌ってくれるのではない。
黒崎 超越的な感じ。トランスセンデントな。
島田 そうですね。ジャケットには、コルトレーンの神に対する賛美の詩が書いてありますね。しかし音楽性でいえば、体の中に染み込んでいるものではないaような。
黒崎 もっと外的なことだと。
島田 その辺りが、聴いていて苦しいと感じてしまう部分かなと思います。
黒崎 ベートーヴェンは耳が聞こえなくなって悩むでしょう? さらに晩年はさまざまな身体的重苦があった。でもほんの一瞬治る時があったのです。後期ですけれど、弦楽四重奏曲の中に、神に感謝するという楽章があって、ものすごくホッとした素晴らしい楽章なのです。麻薬中毒から抜けられたとか、病気が治ったとか、苦しさから解放された時の神への感謝というのがありますが、島田さんの仰るコルトレーンのプレイはそういうものよりはもっと抽象的な?
島田 ええ、かなり抽象的ですね。コルトレーンの中に土着的な部分があったかなかったかは、ちょっと分からないです。例えば、キース・ジャレットなんかでもフリーで自由に弾きますけど、ベースはゴスペルです。だから彼のゴスペル的部分が出てくることで、音楽性が表れるわけです。
黒崎 『ケルン・コンサート』とか。
島田 なので、キースがバッハとかクラシックをやると、ゴスペルが入ってきてちょっと変な感じがするんですよね。
黒崎 ジャズの歴史ってサッチモ、つまりルイ・アーム・ストロングが1925年から30年くらいに、数ドルもらって1枚吹込むってことでホット5かホット7とかって、100曲くらい入れて、っていうところから始まっている。黒人の苦しみから始まりましたよね。25年のサッチモを蓄音器で聴いていて特にそれを感じますし、チャーリー・パーカーについてはめちゃくちゃな人だけど、やはり彼自身の中から溢れ出るものがある。しかし、コルトレーンは、借りてきた神だった?
島田 借りてきた……というより、コルトレーンは考え過ぎていますよね。
黒崎 頭の神。ということはつまり、あれはコルトレーンの勝手な思い込みに時代が反応してしまったと。
島田 ちょっとおかしくなっていたのでしょう、本人が。とにかく吹き続ける。止まらない。『ライブ・イン・ジャパン』なんかまさにそういう状態。
黒崎 僕の目論見では、バッハという崇高なものを聴くのと、『至上の愛』を聴くのは、当時の精神性という意味においてオーバーラップし同一性があったのが、時代とともに音楽から精神性とか崇高性とかいうものが切り取られてフラットになってしまった。そういう今、コルトレーンは辛いよね、という図式だったわけですよ。そうじゃないというわけですね? むしろ、不自然であると?
島田 どうでしょうか。まあでも、単純には楽しめないんですよね。時代のひとコマではあったけれども、そうした文脈なしに今ジャズを聴き始めた人が『至上の愛』を聴いて好きになるかというと、なかなか難しいんじゃないでしょうか。
黒崎 その点、バッハのカンタータは受け入れられてますよね。
島田 バッハは作曲家だけど、コルトレーンは演奏家ですからね。演奏家はその時代の生身の人間であるということが前提としてあります。それに対してバッハは解釈があり得るので。
黒崎 バッハについても、カール・リヒターが70年代までやったけれども、そこから急激に古楽ブームが起こって、リヒターの精神性が否定されていき、もっと身体的な快楽になっていきましたね。