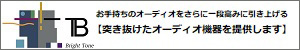【連載】PIT INNその歴史とミュージシャン − 第3回:「ピットイン」と辛島文雄さんの運命の出会い(前編)
今回は特別ゲストとして、日本を代表するジャズピアニストの辛島文雄さんに登場していただき、佐藤さんと対談形式で、ピットインとの深い関わりと思い出を語っていただくことにする。(辛島さんとの対談は次号を含め2回連続となります)
NYから戻って特別な意味を持つ「ピットイン」へ出演
自分のやりたいジャズをやる、という姿勢で臨んできた
クラシックピアノを3歳から始め大学時代はドラマーをやっていた
佐藤良武(以下佐藤):辛島さんとは、ずいぶん長い付き合いですね。
辛島文雄(以下辛島):かれこれ30年以上は軽く経っていますね。
佐藤:82年に「ピットインミュージック」(ピットインのプロダクション部門)と専属契約する以前から出演してもらっていますからね。そもそも最初にピアノを始めたのは何歳から?
辛島:父親が大分大学の音楽科教授だったので、3歳ぐらいからクラシックのレッスンを受けていたんです。
佐藤:そうするとジャズに接するようになったのは……。
辛島:高校時代からです。やっぱり思春期ですから、クラシック以外にも興味を持つわけです。僕らの世代だとビートルズ、楽器をやる人だとベンチャーズかな。僕は天の邪鬼っぽいところがあって、みんなが騒いでいるのを見て「ちょっと違うなぁ」(笑)といきがっていましたね。それで高校1年の時に「モダン・ジャズという音楽があるんだよ」と友達が教えてくれた。
佐藤:最初に聴いたジャズは憶えてる?
辛島:モダン・ジャズ・カルテットの「ジャンゴ」でしたね。5曲入りのソノシートで350円だったかな。プレスティッジのオムニバス盤で、マイルス、ゲッツ、ロリンズ、モンク、それにMJQが入っていた。MJQが一番クラシックに近かったから、わかりやすくて「おお、こんなかっこいい音楽があるんだ」と思いましたね。そのうちに、ほかの演奏も好きになってきて、初めて買ったLPがロリンズの『ワークタイム』。スピード感に溢れる速い曲が好きで、マックス・ローチのファンになりましたね。スティックを買って、百科事典を叩くようになって、そのうちちゃんとドラムを練習するようになりました。
佐藤:確か高校、大学でドラムも叩いていたんだよね。
辛島:九州大学に進学してジャズ研に入った時、先輩よりも僕の方がドラムはうまかったんですよ。ピアノも併行してやっていて、高校生の割にはトミー・フラナガンやジョン・ルイスなんかのコピーもしていましたね。
エルヴィンジョーンズのステージを九州で観てジャズピアノを志した
佐藤:「ピットイン」がオープンしたのは65年。ちょうどその頃になるのかな。
辛島:65年なら僕が17歳の時ですね。そういえば、その翌年、エルヴィン・ジョーンズが日本に長く滞在することがあって「ピットイン」で何日間か日本人とセッションをしましたよね。実はその前にステージを博多で観ているんですよ。面白かったのは、エルヴィンはステージで正面を向かないんですね。袖の方を見ながらドラムを叩いている。視線の先を見ると、後に奥さんになるケイコさんがいたんです(笑)。
佐藤:2人がなれ初めの頃だ。やっぱりエルヴィンにはかなりのインパクトがあった?
辛島:いや、それがエルヴィンよりピアノのマッコイ・タイナーでしたね。マッコイを見てピアニストになろうと決意したといってもいいです。これは決定的でした。当時、彼はもうコルトレーンのバンドを去っていたけれど、在籍していた時代の作品に親しんでいたから、ああこれが本物のマッコイなんだと感動しました。
佐藤:エルヴィンを見てドラマーになっていたら、後にエルヴィンのバンドに入れなかった(笑)。
辛島:ドラマーを志さなかったのは、理由があって、ドラムは誰かがいないと演奏できないのに対し、ピアノはひとりでもできるからです。
佐藤:ドラマーは楽器を運ぶのがたいへんだしね。ピアニストは手ぶらでいいし。
辛島:そう、それもありますね。セットを運ぶ時に雨が降っているとタクシーが止まらない。
佐藤:わりと合理的なんだよね。いつもキッチリと論拠を組み立てていくタイプだよね。
辛島:要するに計算高い(笑)。そういう自分がイヤでね。
九州からいきなりニューヨークへ 帰国後、東京にてチャンスを得た
佐藤:大学時代は専らピアノに打ち込んでいたの?
辛島:学生運動が盛んな時代だったらから、学校が封鎖されているんですよ。そこで真夜中の0時頃に学校に行って朝までピアノを弾く、という生活を送っていました。まだ自分のピアノを持っていませんでした。その頃が一番ジャズを勉強した時代だったかもしれない。なんだかんだで、僕は2年間ほど大学を留年したんですよ。みんなは「東京へ行け」と盛んに勧めたけれど、まだまだ未熟だと思ったから練習をしていたかったんですね。たとえば上京して、バイトをしながらピアノを弾くなんてことは、絶対にできないですよ。楽器の練習はほとんど職人の世界だから、どれだけ時間をかけられるかに尽きるんです。僕はピアノだけで食っていけるレベルの線を自分で引いていて、そこまで到達したかった。
佐藤:トレーニング期間を経てから、すぐに東京へ乗り込まなくて、一挙にニューヨークに渡った。
辛島:その前にステーキハウスでピアノを弾いていたんですね。渡米の資金が要るから。その当時、72年ぐらいでしたが、大卒初任給の倍ぐらいのいい給料をとっていました。考えてみれば僕の今までの人生で一番リッチな時代でした(笑)。その後に、郷里の大分にジャズクラブができて、夜の8時から朝の4時まででソロを弾く仕事をしました。さらに破格の給料で、3カ月ほどタバコ代しか使わないような生活をして、55万円ぐらいが貯まった。親父にも負担してもらったり、餞別だ、なんだかんだで120万円ぐらいの資金ができました。
佐藤:当時としては大金だ。
辛島:ニューヨークに渡ってからは、なるべく長くいたかったんですけど、いまの女房と婚約していて、向こうは堅気の家柄だから、ちゃんとケジメをつけないといけないということで、9カ月ぐらいで帰らざるを得なくなりました。
佐藤:ちょうどそのタイミングで渡辺貞夫カルテットのオーデションがあったでしょう。
辛島:それも戻ってくる理由でした。ただ飛行機が遅れて、帰国した翌日のぼろぼろ状態で臨んだことは憶えています。そんなことは貞夫さんには関係ないことですから、落ちてしまって、本田竹広さんが抜擢されました。僕はその年結婚して、東京に落ち着き、ようやく「ピットイン」に出演できるようになったんです。
佐藤:そもそもの始まりはいきなり店にやってきたという話だけど。
辛島:店のマネージャーに「僕、ピアノ弾けるんですけど」と売り込みに行ったんです。ちょっと聴いてもらって、気に入ってもらえたようです。
佐藤:その頃「ピットイン」は3軒あったね。「ピットイン」本体と「ニュージャズホール」、それに「ピットイン・ティールーム」から名前を変えた「サムライ」。
辛島:「ピットイン」という名前は学生の時からもちろん知っていました。でも「ピットイン」を特別の存在として意識するようになったのは、あるきっかけがあったんです。大分のクラブで夜中に弾いていた時、東京からミュージシャンも来るんですね。その時、ピアニストの寺下誠さんがこう言っていた。「明日の昼、『ピットイン』に出るから夜行列車で帰る。それが終わったらまたすぐ大分に戻ってくる」と。僕は、「ピットイン」って、そんなに大事な場所なんだとインプットされたんです。また、往復の交通費は「ピットイン」が当然出しているものだと思ったから、これはすごいと感動したわけですよ(笑)。
佐藤:それを出演者全員にしていたら、ウチはたいへんなことになってる(笑)。
辛島:自腹でトンボ帰りでもいいから「ピットイン」に出たいというその気持ちは、自分が同じ立場になってわかりましたね。つまり店のムードに合わせたり、命じられた音楽をやったりするのではなくて、自分自身の音楽ができるということなんですよ。それは今も昔もずっとそうですけど、「ピットイン」は客におもねる必要のない、自分を表現できる場所なんですね。
佐藤:私は口出しせずに、ミュージシャンには最高のパフォーマンスを見せてくださいというスタンスだからね。
佐藤さんとは価値観や興味が共通していて出会い以来、30年以上の付き合いとなった。
そして「ピットイン」への出演で認められエルヴィン・ジョーンズのバンドに入ることになる…
「ピットイン」への出始めは忙しくジョージ大塚バンドで知られるように
辛島:「ピットイン」に出始めは忙しかった。いくつかのバンドから声がかかって、四つぐらいを掛け持ちするようになって。
佐藤:それだけ対応できたということだよね。それと「ニューヨーク帰り」というプロフィールが良かった。当時、そういうミュージシャンはとても少なくて、ステータスだった。
辛島:まあ、実力が同じぐらいでも、ジャズミュージシャンは珍しいもの好きが多いから、あいつにやらせてみようというのはありますね。そうこうするうちにベーシストの水橋孝さんのバンドに入ったんです。
佐藤:それからすぐジョージ大塚さんのバンドに抜擢されて、辛島文雄というピアニストが世間に知られるようになった。私自身も辛島さんに注目するようになったのはこの頃からだね。というのは「ピットイン」を始めてからずっと、ジョージさんは店のクリーンナップを打っていたような存在だったから。それが74年?
辛島:そうです。それ以来、良武さんとは親しくさせてもらっています。
佐藤:最近は少なくなったけれど、「ピットイン」を始めて10年ぐらいは、芸術家肌というか奔放なミュージシャンが随分いた。だけど辛島さんとは普通に世間話ができる。ウマがあうというのかな。
辛島:価値観や興味があるものが共通していますね。ゴルフとか野球、車とかね。
佐藤:仕事も生活もピシッと整然としている。
辛島:結婚していたし、ピアノは趣味みたいなもので、いつ止めてもいいんだというのではなくて、これは職業だという意識が強いですね。ただ職業といっても、何でもやりますよ、というのではなくて、自分のやりたいジャズをやるということなんだけれど。
佐藤:スタイルが終始一貫してブレていない。どんな音楽が流行ろうと、またどんな大物と共演しようとも、自分のスタイルを曲げない。その部分は素晴らしいと思いますね。レコード会社に言われるままではなくて。
辛島:それができたのも、女房や自分の両親、女房の両親も含めて、良武さんのような良き理解者がサポートしてくれるからですね。やっぱり生活していけなかったら、そんなこと言っていられないですよ。それに人から指示された音楽は、やっていて面白くないし。
78年に再来日したエルヴィン・ジョーンズに会い
翌年バンドに加わることを勧められた
佐藤:エルヴィン・ジョーンズのバンドにいた時も自分を貫いていたね。エルヴィンと初めて顔を合わせたのはいつだったの?
辛島:78年です。その時に『ムーン・フラワー』という僕のアルバムで共演できたのですが、かなり四苦八苦した記憶があります。なかなか音が合わなかった。その翌年の正月にもエルヴィンとケイコさんは日本にやって来て、福岡で一緒にライブをやりました。その時エルヴィンは「フミオ、うまくなったな」と言ってくれました。しばらく経って夏あたりに「オレのバンドに入らないか」と誘ってくれたんです。ようやく僕が正式にエルヴィンのバンドに加入したのは80年のことでした。そこから僕の音楽人生が劇的に変わっていきました。
(第4回に続く)
インタビュー・文 田中伊佐資
写真:川村容一
辛島文雄さん(ピアニスト、コンポーザー)プロフィール

1948年、大分県出身。上京後、ジョージ大塚(Ds)グループに在籍。1978年のエルヴィン・ジョーンズ(Ds)との共演を機に、1980年から6年間にわたってエルヴィン・ジョーンズ=ジャズマシーンに参加、アメリカ、ヨーロッパを中心とした世界各国のジャズシーンに登場、これにより国際的ピアニストとしての地位を築く。同時代にして、故日野元彦(Ds)とも親交を深め、トリオを結成。その後、ピアノソロにも新境地を見出し、その活動は発展的に今日まで継続している。88年、辛島文雄クインテットを結成、本格的なジャズユニットとして高い評価を得た。また、ソリストとしても、角田健一ビックバンド、神奈川フィルハーモニー管弦楽団、新日本交響楽団に迎えられ「ラプソディ・イン・ブルー」を好演している。94年、トニー・ウィリアムス(Ds)を擁した「フミオ・カラシマ・イン・サンフランシスコ」をリリース。その後、渡辺香津美(Gtr)などのオールスターによる「オープン・ザ・ゲイト」をリリース。また、99年、ハーモニカの名手トゥーツ・シールマンスとデュオによる「ランコントル」をリリース。2006年、ジャック・ディジョネット(Ds)とのコラボレーションによる「グレイト・タイム」を発表。これによりエルヴィン・ジョーンズ(Ds)、トニー・ウイリアムス(Ds)に続くスーパー・ドラマーとの共演を果たす。CD デビュー30周年を飾るに相応しい24枚目のリーダーアルバムである。辛島文雄はエルヴィン・ジョーンズのスピリッツを継承している日本人ミュージシャンの第一人者であり、ジャズのフィールドから最上のピアノテクニックを確立したピアニストとして高い評価を受けている。2003年にキューバ、パナマ、エルサルバドル、メキシコ、アルゼンチンの中南米5カ国を訪問。国際的にも日本を代表する実力派ジャズピアニストとして知られる。
本記事は「季刊・analog」にて好評連載中です。「analog」の購入はこちらから
NYから戻って特別な意味を持つ「ピットイン」へ出演
自分のやりたいジャズをやる、という姿勢で臨んできた
クラシックピアノを3歳から始め大学時代はドラマーをやっていた
佐藤良武(以下佐藤):辛島さんとは、ずいぶん長い付き合いですね。
辛島文雄(以下辛島):かれこれ30年以上は軽く経っていますね。
佐藤:82年に「ピットインミュージック」(ピットインのプロダクション部門)と専属契約する以前から出演してもらっていますからね。そもそも最初にピアノを始めたのは何歳から?
辛島:父親が大分大学の音楽科教授だったので、3歳ぐらいからクラシックのレッスンを受けていたんです。
佐藤:そうするとジャズに接するようになったのは……。
辛島:高校時代からです。やっぱり思春期ですから、クラシック以外にも興味を持つわけです。僕らの世代だとビートルズ、楽器をやる人だとベンチャーズかな。僕は天の邪鬼っぽいところがあって、みんなが騒いでいるのを見て「ちょっと違うなぁ」(笑)といきがっていましたね。それで高校1年の時に「モダン・ジャズという音楽があるんだよ」と友達が教えてくれた。
佐藤:最初に聴いたジャズは憶えてる?
辛島:モダン・ジャズ・カルテットの「ジャンゴ」でしたね。5曲入りのソノシートで350円だったかな。プレスティッジのオムニバス盤で、マイルス、ゲッツ、ロリンズ、モンク、それにMJQが入っていた。MJQが一番クラシックに近かったから、わかりやすくて「おお、こんなかっこいい音楽があるんだ」と思いましたね。そのうちに、ほかの演奏も好きになってきて、初めて買ったLPがロリンズの『ワークタイム』。スピード感に溢れる速い曲が好きで、マックス・ローチのファンになりましたね。スティックを買って、百科事典を叩くようになって、そのうちちゃんとドラムを練習するようになりました。
佐藤:確か高校、大学でドラムも叩いていたんだよね。
辛島:九州大学に進学してジャズ研に入った時、先輩よりも僕の方がドラムはうまかったんですよ。ピアノも併行してやっていて、高校生の割にはトミー・フラナガンやジョン・ルイスなんかのコピーもしていましたね。
エルヴィンジョーンズのステージを九州で観てジャズピアノを志した
佐藤:「ピットイン」がオープンしたのは65年。ちょうどその頃になるのかな。
辛島:65年なら僕が17歳の時ですね。そういえば、その翌年、エルヴィン・ジョーンズが日本に長く滞在することがあって「ピットイン」で何日間か日本人とセッションをしましたよね。実はその前にステージを博多で観ているんですよ。面白かったのは、エルヴィンはステージで正面を向かないんですね。袖の方を見ながらドラムを叩いている。視線の先を見ると、後に奥さんになるケイコさんがいたんです(笑)。
佐藤:2人がなれ初めの頃だ。やっぱりエルヴィンにはかなりのインパクトがあった?
辛島:いや、それがエルヴィンよりピアノのマッコイ・タイナーでしたね。マッコイを見てピアニストになろうと決意したといってもいいです。これは決定的でした。当時、彼はもうコルトレーンのバンドを去っていたけれど、在籍していた時代の作品に親しんでいたから、ああこれが本物のマッコイなんだと感動しました。
佐藤:エルヴィンを見てドラマーになっていたら、後にエルヴィンのバンドに入れなかった(笑)。
辛島:ドラマーを志さなかったのは、理由があって、ドラムは誰かがいないと演奏できないのに対し、ピアノはひとりでもできるからです。
佐藤:ドラマーは楽器を運ぶのがたいへんだしね。ピアニストは手ぶらでいいし。
辛島:そう、それもありますね。セットを運ぶ時に雨が降っているとタクシーが止まらない。
佐藤:わりと合理的なんだよね。いつもキッチリと論拠を組み立てていくタイプだよね。
辛島:要するに計算高い(笑)。そういう自分がイヤでね。
九州からいきなりニューヨークへ 帰国後、東京にてチャンスを得た
佐藤:大学時代は専らピアノに打ち込んでいたの?
辛島:学生運動が盛んな時代だったらから、学校が封鎖されているんですよ。そこで真夜中の0時頃に学校に行って朝までピアノを弾く、という生活を送っていました。まだ自分のピアノを持っていませんでした。その頃が一番ジャズを勉強した時代だったかもしれない。なんだかんだで、僕は2年間ほど大学を留年したんですよ。みんなは「東京へ行け」と盛んに勧めたけれど、まだまだ未熟だと思ったから練習をしていたかったんですね。たとえば上京して、バイトをしながらピアノを弾くなんてことは、絶対にできないですよ。楽器の練習はほとんど職人の世界だから、どれだけ時間をかけられるかに尽きるんです。僕はピアノだけで食っていけるレベルの線を自分で引いていて、そこまで到達したかった。
佐藤:トレーニング期間を経てから、すぐに東京へ乗り込まなくて、一挙にニューヨークに渡った。
辛島:その前にステーキハウスでピアノを弾いていたんですね。渡米の資金が要るから。その当時、72年ぐらいでしたが、大卒初任給の倍ぐらいのいい給料をとっていました。考えてみれば僕の今までの人生で一番リッチな時代でした(笑)。その後に、郷里の大分にジャズクラブができて、夜の8時から朝の4時まででソロを弾く仕事をしました。さらに破格の給料で、3カ月ほどタバコ代しか使わないような生活をして、55万円ぐらいが貯まった。親父にも負担してもらったり、餞別だ、なんだかんだで120万円ぐらいの資金ができました。
佐藤:当時としては大金だ。
辛島:ニューヨークに渡ってからは、なるべく長くいたかったんですけど、いまの女房と婚約していて、向こうは堅気の家柄だから、ちゃんとケジメをつけないといけないということで、9カ月ぐらいで帰らざるを得なくなりました。
佐藤:ちょうどそのタイミングで渡辺貞夫カルテットのオーデションがあったでしょう。
辛島:それも戻ってくる理由でした。ただ飛行機が遅れて、帰国した翌日のぼろぼろ状態で臨んだことは憶えています。そんなことは貞夫さんには関係ないことですから、落ちてしまって、本田竹広さんが抜擢されました。僕はその年結婚して、東京に落ち着き、ようやく「ピットイン」に出演できるようになったんです。
佐藤:そもそもの始まりはいきなり店にやってきたという話だけど。
辛島:店のマネージャーに「僕、ピアノ弾けるんですけど」と売り込みに行ったんです。ちょっと聴いてもらって、気に入ってもらえたようです。
佐藤:その頃「ピットイン」は3軒あったね。「ピットイン」本体と「ニュージャズホール」、それに「ピットイン・ティールーム」から名前を変えた「サムライ」。
辛島:「ピットイン」という名前は学生の時からもちろん知っていました。でも「ピットイン」を特別の存在として意識するようになったのは、あるきっかけがあったんです。大分のクラブで夜中に弾いていた時、東京からミュージシャンも来るんですね。その時、ピアニストの寺下誠さんがこう言っていた。「明日の昼、『ピットイン』に出るから夜行列車で帰る。それが終わったらまたすぐ大分に戻ってくる」と。僕は、「ピットイン」って、そんなに大事な場所なんだとインプットされたんです。また、往復の交通費は「ピットイン」が当然出しているものだと思ったから、これはすごいと感動したわけですよ(笑)。
佐藤:それを出演者全員にしていたら、ウチはたいへんなことになってる(笑)。
辛島:自腹でトンボ帰りでもいいから「ピットイン」に出たいというその気持ちは、自分が同じ立場になってわかりましたね。つまり店のムードに合わせたり、命じられた音楽をやったりするのではなくて、自分自身の音楽ができるということなんですよ。それは今も昔もずっとそうですけど、「ピットイン」は客におもねる必要のない、自分を表現できる場所なんですね。
佐藤:私は口出しせずに、ミュージシャンには最高のパフォーマンスを見せてくださいというスタンスだからね。
佐藤さんとは価値観や興味が共通していて出会い以来、30年以上の付き合いとなった。
そして「ピットイン」への出演で認められエルヴィン・ジョーンズのバンドに入ることになる…
「ピットイン」への出始めは忙しくジョージ大塚バンドで知られるように
辛島:「ピットイン」に出始めは忙しかった。いくつかのバンドから声がかかって、四つぐらいを掛け持ちするようになって。
佐藤:それだけ対応できたということだよね。それと「ニューヨーク帰り」というプロフィールが良かった。当時、そういうミュージシャンはとても少なくて、ステータスだった。
辛島:まあ、実力が同じぐらいでも、ジャズミュージシャンは珍しいもの好きが多いから、あいつにやらせてみようというのはありますね。そうこうするうちにベーシストの水橋孝さんのバンドに入ったんです。
佐藤:それからすぐジョージ大塚さんのバンドに抜擢されて、辛島文雄というピアニストが世間に知られるようになった。私自身も辛島さんに注目するようになったのはこの頃からだね。というのは「ピットイン」を始めてからずっと、ジョージさんは店のクリーンナップを打っていたような存在だったから。それが74年?
辛島:そうです。それ以来、良武さんとは親しくさせてもらっています。
佐藤:最近は少なくなったけれど、「ピットイン」を始めて10年ぐらいは、芸術家肌というか奔放なミュージシャンが随分いた。だけど辛島さんとは普通に世間話ができる。ウマがあうというのかな。
辛島:価値観や興味があるものが共通していますね。ゴルフとか野球、車とかね。
佐藤:仕事も生活もピシッと整然としている。
辛島:結婚していたし、ピアノは趣味みたいなもので、いつ止めてもいいんだというのではなくて、これは職業だという意識が強いですね。ただ職業といっても、何でもやりますよ、というのではなくて、自分のやりたいジャズをやるということなんだけれど。
佐藤:スタイルが終始一貫してブレていない。どんな音楽が流行ろうと、またどんな大物と共演しようとも、自分のスタイルを曲げない。その部分は素晴らしいと思いますね。レコード会社に言われるままではなくて。
辛島:それができたのも、女房や自分の両親、女房の両親も含めて、良武さんのような良き理解者がサポートしてくれるからですね。やっぱり生活していけなかったら、そんなこと言っていられないですよ。それに人から指示された音楽は、やっていて面白くないし。
78年に再来日したエルヴィン・ジョーンズに会い
翌年バンドに加わることを勧められた
佐藤:エルヴィン・ジョーンズのバンドにいた時も自分を貫いていたね。エルヴィンと初めて顔を合わせたのはいつだったの?
辛島:78年です。その時に『ムーン・フラワー』という僕のアルバムで共演できたのですが、かなり四苦八苦した記憶があります。なかなか音が合わなかった。その翌年の正月にもエルヴィンとケイコさんは日本にやって来て、福岡で一緒にライブをやりました。その時エルヴィンは「フミオ、うまくなったな」と言ってくれました。しばらく経って夏あたりに「オレのバンドに入らないか」と誘ってくれたんです。ようやく僕が正式にエルヴィンのバンドに加入したのは80年のことでした。そこから僕の音楽人生が劇的に変わっていきました。
(第4回に続く)
インタビュー・文 田中伊佐資
写真:川村容一
辛島文雄さん(ピアニスト、コンポーザー)プロフィール

本記事は「季刊・analog」にて好評連載中です。「analog」の購入はこちらから
関連リンク