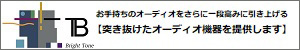【連載】PIT INNその歴史とミュージシャン − 第4回:「ピットイン」と辛島文雄さんの運命の出会い(後編)
今回は特別ゲストとして、日本を代表するジャズピアニストの辛島文雄さんに登場していただき、佐藤さんと対談形式で、ピットインとの深い関わりと思い出を語っていただくことにする。(辛島さんとの対談は前号から続いており、今回は後編となります)
マイルスの演奏で衝撃を受け、ジャズへの意識が一変
自分の奢りに泣けてしまい、今思い出しても鳥肌が立つ
渡米した時は自負心を持っていた
結局エルヴィンと長く一緒に演奏
佐藤良武(以下佐藤):辛島さんがエルヴィン・ジョーンズに認められて、彼のバンドに入ったのが80年。その年の8月に「辛島文雄、エルヴィン・ジョーンズ・ジャズ・マシーン加入渡米記念サヨナラ・セッション」を「新宿ピットイン」でやりましたね。
辛島文雄(以下辛島):良武さんが音頭をとっていただいた壮行会ですね。渡辺香津美さんやジョージ大塚さんをはじめ、たくさんのミュージシャンに出演してもらいました。
佐藤:エルヴィンのバンドに加入するということは、国際的に有名になることですから、これはしっかりとお披露目しておこうと思ったんです。
辛島:海外生活は、経済的にもたいへんだろうからと、売り上げをお祝いとして頂戴しました。ステージの上で、のし袋をもらったのは後にも先にもこれ1回だけですよ。確か27万円が入っていましたね。
佐藤:よく憶えているね。こちらは売り上げをかき集めてそっくり渡したから記憶はないですよ。ともかく「ピットイン」で活動していたピアニストが世界に羽ばたくわけですから、これは個人的にもうれしかった。
辛島:僕はまだ若くて、思い上がりが激しかった頃だから「オレは実力があるから行くんだ」ぐらいに思っていましたね(笑)。ファンや友人、家族に行かせてもらったにすぎないのにね。
佐藤:あの時、そんな自惚れがあったの?微塵も感じなかったけど(笑)。
辛島:まあ、それぐらいの自負心がないと世界を舞台にしてやっていられないというのはありますよ。バンドで「この次はどう弾いたらいいのでしょう」みたいな姿勢では、すぐにクビになっちゃうんですよ。
佐藤:ピットイン・ミュージック(ピットインのプロダクション部門)と専属契約をしたのがエルヴィン・バンド加入2年後。バンドにはかれこれ6年間もいたんだよね。これはすごいことですよ。だいたい3年でメンバーは入れ替わるわけだから。
辛島:それだけ長くいると最後の方は、僕がバンドの音楽監督みたいになっていましたね。プライベートでもエルヴィンとは何でも言い合えて、ケイコ夫人から「兄弟みたいね」なんて言われました。そういう関係の中で、エルヴィンとバンドからジャズのスピリットそのものを吸収できました。その大きさといったら、とても言葉にはできません。それを若いミュージシャンに可能な限り伝えるのが、僕の使命だと思っています。
世界を駆け巡りテングになっていたが
ノルウェーでその考えが吹き飛んだ
佐藤:エルヴィン・バンドのことを思うと、「ピットイン」開店20周年の85年に録音した『ライヴ・アット・ピットイン』が私は特に感慨深いです。自分が制作者ということもあるけれど、エルヴィンを「ピットイン」で録音するというのは自分の夢でもあったし、「ピットイン」出身の辛島さんが凱旋したということもあった。あの時は、どんな気持ちだったの?
辛島:依然として恐いものなしだったから、自分がエルヴィン・バンドの一員でいることは当然だ、みたいに思っていた(笑)。
佐藤:(笑)。まあ、それだけ溶け込んでいたわけだし、世界中をツアーで回っていたわけだからね。
辛島:メンバーも一流だし、本気で彼らとジャズをやりあっていた。バンドを完全に掌握していたし、メンバーが「次の曲はどうする?」って、エルヴィンじゃなくて僕に訊いてくるほどだったから、完全にテングになっていましたね。そのテングの鼻をへし折った男がいたんですよ。
佐藤:というと?
辛島:ノルウェーのモルデというところで毎年ジャズ・フェスティバルが開かれていて、ある年、自分たちも出演したんです。僕らの演奏は夜中に終わって、帰ろうとしたらこれからマイルス・デイヴィスのステージが始まるというんです。僕はマイルスと同じフェスティバルに出たという記念に、1曲だけ聴いて帰ろうと思った。夜中の1時頃、白夜の下で演奏が始まったら、もう帰れなくなっちゃった。びっちり2時間。最後の方はボロボロ泣いちゃった。
佐藤:泣いた?
辛島:マイルスとエルヴィンがやっている音楽は表面的にはまったく違うものですけど、中味は等しいということに気づいたんです。要するにブルースです。根っこは黒人のブルースなんです。「僕のような日本人がジャズをやっていてごめんなさい」と痛切に思いました。そして自分はなんて奢りを持ってジャズに取り組んでいたんだ、という衝撃を受けました。もう泣けて泣けてしょうがなかった。その時ですよ、僕の中でジャズに対して別のスイッチが入ったのは。いまでもこのことを思い出すと鳥肌が立ってきます。
佐藤:それはエルヴィンとやっていなければわからなかったことじゃないかなあ。
辛島:まったくその通りです。当時、エルヴィンは伝統的な古い音楽、マイルスは斬新な音楽をやっていると認識していました。そして僕はもっと新しいことをやりたいと思っていました。
佐藤:エルヴィンにはそのことをアピールしたことがあった?
辛島:ええ。その時エルヴィンはこう答えたんです。「フミオ、オレはコルトレーンのバンドで『マイ・フェイヴァリット・シングス』を1万回やったんだぞ」って(笑)。
佐藤:そう言われると「すみませんでした」って感じですよね(笑)。「花嫁人形」とか「五木の子守歌」とか日本の曲をエルヴィンは大好きで、それを必ずライブでは繰り返していましたね。
辛島:あれは日本人としては、しんどいんですよ。ただもう、マイルスの一件があってから、そういうことを言うのは一切やめた。毎回同じ曲であっても、どれだけ新鮮な気持ちでチャレンジできるかということが重要なんだなと思ったわけです。
佐藤:マイルスだって「ソー・ホワット」を延々とやっていましたからね。
辛島:それまでの僕はジャズをファッションのように見ていたんだと思います。重要なことは表面的なことではなくて、ジャズの奥底に流れているスピリットです。良武さんは「辛島さんのスタイルはぶれていない」と言ってくれますが、スピリットはずっと不変ですからね。
佐藤良武さんが「新宿ピットイン」で錚々たるメンバーの壮行ライブを開催してくれ
エルヴィン・バンドに入り5年間世界を回る − 自らのジャズを追求するために86年に帰国
バンドではリーダーの意思が絶対
危機感が募ってきて独立のため帰国
佐藤:「ピットイン」もオープンからずっと40年間、一貫した姿勢でやっています。そのあたりに私と辛島さんは、価値観が一緒で気が合っているのかもしれません。それで、エルヴィン・バンドを辞めたのは、いつ頃だったけ?
辛島:86年ですね。僕はまだ30代の後半で若かったし、このままずっとバンドにいれば、一本立ちできずに終わってしまうという危機感が募ってきたんです。
佐藤:そろそろ独立したいな、と相談を受けたことがありましたね。こちらは「ピットインミュージック」のアーチストとして契約している以上、エルヴィンのバンドとはいえ、いつまでもサイドマンのままでいることもないだろうという判断だった。
辛島:ジャズは自由な演奏ができる音楽ですが、バンドに所属していれば、リーダーの意向に添わなければいけません。「ああいうソロは、自分のバンドでやってくれ」とエルヴィンから指摘されているプレイヤーもいました。私の場合、「花嫁人形」をとことんやり尽くしていった結果、そのうちドビュッシーやラベルみたいな雰囲気になっていったんですね。エルヴィンはそれが不満だったらしくて、「美空ひばりの歌のイントロみたいに弾いてくれ」と言い出したんです。僕らが黒人のブルースが好きなように、エルヴィンもある意味日本人のブルースである歌謡曲や演歌が好きでした。エルヴィンの凄いところは、「花嫁人形」という原曲に振り回されないで、それを超越した世界でドラムを叩いていたことです。けれど、僕はそういう音楽が好きではないからジャズをやっているんですよ(笑)。いまならエルヴィンの気持ちもわかるので、いくらでも望み通りに弾けますけれど、当時の僕は「そんなことできない」って突っぱねたわけです。そうなるとバンドを立ち去るしかありません。
佐藤:エルヴィンは美空ひばりと並んで座頭市も好きでした。世界の第一線でプレイする人間として、強い者に対する憧れというものがあったのかもしれない。
辛島:世界中を旅していると、人種的なことで屈辱的な扱いを受けることがたびたびありました。座頭市は虐げられた境遇をはね返して最後は勝つというストーリーですから、その心情はわかります。
天才ジャック・ディジョネットとの
共演で再び燃える演奏を体感できた
佐藤:辛島さんはバンドを辞めてから、共演するドラマーについて悩んでいたようでした。エルヴィンほどの天才は二人といないわけですからね。
辛島:辞めてすぐは、奥平真吾さんと組むことができたので、それほどショックはありませんでした。でも、彼が91年にニューヨークに渡ってしまって、それから2年間ぐらいですよ、フィットするドラマーがいなくて困ったのは。ピアノを止めようと思ったこともありました。
佐藤:辛島さんは、そこでもう一皮むけたんじゃないかと思います。それがあって、昨年の『グレイト・タイム』で一挙に花開いた感じがしますね。世界最高のドラマー、ジャック・ディジョネットと激しく渡り合っている。
辛島:僕は20枚以上もリーダーアルバムを作ってきましたが、どうしてもどこか一部に納得できないところがあったんですね。ところが、初対面のプレイヤーと同じ目線であれほどの音楽ができた。これは初めての体験だった。『グレイト・タイム』は現時点で僕のベスト作品といえます。
佐藤:辛島さんはドラムを叩けるし、ジャックはピアノを弾けるでしょう。わかり合えることが多かったのではないでしょうか。やはり偉大なドラマーのトニー・ウィリアムスと共演した『イン・サンフランシスコ』(94年)よりも内容がよかった。
辛島:あの時は緊張していましたね。どこかに、まだ自分で力が足らないと思いながら弾いていたところがあった。
佐藤:若い頃とまったく違うんだね(笑)。
辛島:でも今回、初めてジャックとやって、まったく同じ力がぶつかり合ったという感触がありました。ベースのドリュー・グレスを含めて3人に一体感がありました。アメリカやヨーロッパでリリースしても受け入れられる作品だと思っています。
佐藤:ジャックといえば、キース・ジャレットのスタンダーズのイメージが強いですけど、そのクオリティとまったく引けを取っていない。
辛島:確かにみんなが思っているジャックは、スタンダーズということになるのだろうけど、僕にとっては、60年代末から70年にかけてマイルス・バンドにいた頃なんですよ。その時代のジャックを引き出せたかなと思っています。
佐藤:ジャックをあれだけ叩かせたんだからね。かなり燃えたみたいだね。
辛島:燃えたといえば、レコーディングの休憩時間でやった卓球も燃えた。実力伯仲で、二人とも必死だった(笑)。

『グレイト・タイム』収録時の模様(Photo by John Abbott)

『グレイト・タイム』のレコーディングでは演奏も燃えたが、休憩時間の卓球にも熱が入った(Photo by John Abbott)
『グレイト・タイム』収録時の辛島トリオ。左からジャック・ディジョネット、辛島さん、ドリュー・グレス(Photo by John Abbott)
3人のアイドルとの共演を実現したが
「まさにこれから」の気持ちでいる
佐藤:またジャック・ディジョネットと何か残せるといいですね。エルヴィンもトニーもいなくなってしまって、ジャズ・ドラマーの大御所といえば、もはや彼しかいない。
辛島:僕がドラムをやっていた学生時代、エルヴィン、トニー、ジャックの3人はずっとアイドルでした。いつかは彼らと肩を並べて演奏したいと思っていたので、3人と共演できたことは感無量です。
佐藤:3人と共演したピアニストは世界的にもそう多くはいないでしょう。そういう意味では、辛島さんは、これからもっとステップアップしていくアーチストだと思っています。ピットインとしては、万全のサポートをしたいと思っていますね。
辛島:まさにこれからです。「イッツ・ジャスト・ビギニング」(2003年発表のアルバムタイトル)ということですね。
(第5回に続く)
インタビュー・文 田中伊佐資
メイン写真 田代法生(その他の写真 川村容一)
辛島文雄さん(ピアニスト、コンポーザー)プロフィール

1948年、大分県出身。上京後、ジョージ大塚(Ds)グループに在籍。1978年のエルヴィン・ジョーンズ(Ds)との共演を機に、1980年から6年間にわたってエルヴィン・ジョーンズ=ジャズマシーンに参加、アメリカ、ヨーロッパを中心とした世界各国のジャズシーンに登場、これにより国際的ピアニストとしての地位を築く。同時代にして、故日野元彦(Ds)とも親交を深め、トリオを結成。その後、ピアノソロにも新境地を見出し、その活動は発展的に今日まで継続している。88年、辛島文雄クインテットを結成、本格的なジャズユニットとして高い評価を得た。また、ソリストとしても、角田健一ビックバンド、神奈川フィルハーモニー管弦楽団、新日本交響楽団に迎えられ「ラプソディ・イン・ブルー」を好演している。94年、トニー・ウィリアムス(Ds)を擁した「フミオ・カラシマ・イン・サンフランシスコ」をリリース。その後、渡辺香津美(Gtr)などのオールスターによる「オープン・ザ・ゲイト」をリリース。また、99年、ハーモニカの名手トゥーツ・シールマンスとデュオによる「ランコントル」をリリース。2006年、ジャック・ディジョネット(Ds)とのコラボレーションによる「グレイト・タイム」を発表。これによりエルヴィン・ジョーンズ(Ds)、トニー・ウイリアムス(Ds)に続くスーパー・ドラマーとの共演を果たす。CD デビュー30周年を飾るに相応しい24枚目のリーダーアルバムである。辛島文雄はエルヴィン・ジョーンズのスピリッツを継承している日本人ミュージシャンの第一人者であり、ジャズのフィールドから最上のピアノテクニックを確立したピアニストとして高い評価を受けている。2003年にキューバ、パナマ、エルサルバドル、メキシコ、アルゼンチンの中南米5カ国を訪問。国際的にも日本を代表する実力派ジャズピアニストとして知られる。
本記事は「季刊・analog」にて好評連載中です。「analog」の購入はこちらから
マイルスの演奏で衝撃を受け、ジャズへの意識が一変
自分の奢りに泣けてしまい、今思い出しても鳥肌が立つ
渡米した時は自負心を持っていた
結局エルヴィンと長く一緒に演奏
佐藤良武(以下佐藤):辛島さんがエルヴィン・ジョーンズに認められて、彼のバンドに入ったのが80年。その年の8月に「辛島文雄、エルヴィン・ジョーンズ・ジャズ・マシーン加入渡米記念サヨナラ・セッション」を「新宿ピットイン」でやりましたね。
辛島文雄(以下辛島):良武さんが音頭をとっていただいた壮行会ですね。渡辺香津美さんやジョージ大塚さんをはじめ、たくさんのミュージシャンに出演してもらいました。
佐藤:エルヴィンのバンドに加入するということは、国際的に有名になることですから、これはしっかりとお披露目しておこうと思ったんです。
辛島:海外生活は、経済的にもたいへんだろうからと、売り上げをお祝いとして頂戴しました。ステージの上で、のし袋をもらったのは後にも先にもこれ1回だけですよ。確か27万円が入っていましたね。
佐藤:よく憶えているね。こちらは売り上げをかき集めてそっくり渡したから記憶はないですよ。ともかく「ピットイン」で活動していたピアニストが世界に羽ばたくわけですから、これは個人的にもうれしかった。
辛島:僕はまだ若くて、思い上がりが激しかった頃だから「オレは実力があるから行くんだ」ぐらいに思っていましたね(笑)。ファンや友人、家族に行かせてもらったにすぎないのにね。
佐藤:あの時、そんな自惚れがあったの?微塵も感じなかったけど(笑)。
辛島:まあ、それぐらいの自負心がないと世界を舞台にしてやっていられないというのはありますよ。バンドで「この次はどう弾いたらいいのでしょう」みたいな姿勢では、すぐにクビになっちゃうんですよ。
佐藤:ピットイン・ミュージック(ピットインのプロダクション部門)と専属契約をしたのがエルヴィン・バンド加入2年後。バンドにはかれこれ6年間もいたんだよね。これはすごいことですよ。だいたい3年でメンバーは入れ替わるわけだから。
辛島:それだけ長くいると最後の方は、僕がバンドの音楽監督みたいになっていましたね。プライベートでもエルヴィンとは何でも言い合えて、ケイコ夫人から「兄弟みたいね」なんて言われました。そういう関係の中で、エルヴィンとバンドからジャズのスピリットそのものを吸収できました。その大きさといったら、とても言葉にはできません。それを若いミュージシャンに可能な限り伝えるのが、僕の使命だと思っています。
世界を駆け巡りテングになっていたが
ノルウェーでその考えが吹き飛んだ
佐藤:エルヴィン・バンドのことを思うと、「ピットイン」開店20周年の85年に録音した『ライヴ・アット・ピットイン』が私は特に感慨深いです。自分が制作者ということもあるけれど、エルヴィンを「ピットイン」で録音するというのは自分の夢でもあったし、「ピットイン」出身の辛島さんが凱旋したということもあった。あの時は、どんな気持ちだったの?
辛島:依然として恐いものなしだったから、自分がエルヴィン・バンドの一員でいることは当然だ、みたいに思っていた(笑)。
佐藤:(笑)。まあ、それだけ溶け込んでいたわけだし、世界中をツアーで回っていたわけだからね。
辛島:メンバーも一流だし、本気で彼らとジャズをやりあっていた。バンドを完全に掌握していたし、メンバーが「次の曲はどうする?」って、エルヴィンじゃなくて僕に訊いてくるほどだったから、完全にテングになっていましたね。そのテングの鼻をへし折った男がいたんですよ。
佐藤:というと?
辛島:ノルウェーのモルデというところで毎年ジャズ・フェスティバルが開かれていて、ある年、自分たちも出演したんです。僕らの演奏は夜中に終わって、帰ろうとしたらこれからマイルス・デイヴィスのステージが始まるというんです。僕はマイルスと同じフェスティバルに出たという記念に、1曲だけ聴いて帰ろうと思った。夜中の1時頃、白夜の下で演奏が始まったら、もう帰れなくなっちゃった。びっちり2時間。最後の方はボロボロ泣いちゃった。
佐藤:泣いた?
辛島:マイルスとエルヴィンがやっている音楽は表面的にはまったく違うものですけど、中味は等しいということに気づいたんです。要するにブルースです。根っこは黒人のブルースなんです。「僕のような日本人がジャズをやっていてごめんなさい」と痛切に思いました。そして自分はなんて奢りを持ってジャズに取り組んでいたんだ、という衝撃を受けました。もう泣けて泣けてしょうがなかった。その時ですよ、僕の中でジャズに対して別のスイッチが入ったのは。いまでもこのことを思い出すと鳥肌が立ってきます。
佐藤:それはエルヴィンとやっていなければわからなかったことじゃないかなあ。
辛島:まったくその通りです。当時、エルヴィンは伝統的な古い音楽、マイルスは斬新な音楽をやっていると認識していました。そして僕はもっと新しいことをやりたいと思っていました。
佐藤:エルヴィンにはそのことをアピールしたことがあった?
辛島:ええ。その時エルヴィンはこう答えたんです。「フミオ、オレはコルトレーンのバンドで『マイ・フェイヴァリット・シングス』を1万回やったんだぞ」って(笑)。
佐藤:そう言われると「すみませんでした」って感じですよね(笑)。「花嫁人形」とか「五木の子守歌」とか日本の曲をエルヴィンは大好きで、それを必ずライブでは繰り返していましたね。
辛島:あれは日本人としては、しんどいんですよ。ただもう、マイルスの一件があってから、そういうことを言うのは一切やめた。毎回同じ曲であっても、どれだけ新鮮な気持ちでチャレンジできるかということが重要なんだなと思ったわけです。
佐藤:マイルスだって「ソー・ホワット」を延々とやっていましたからね。
辛島:それまでの僕はジャズをファッションのように見ていたんだと思います。重要なことは表面的なことではなくて、ジャズの奥底に流れているスピリットです。良武さんは「辛島さんのスタイルはぶれていない」と言ってくれますが、スピリットはずっと不変ですからね。
佐藤良武さんが「新宿ピットイン」で錚々たるメンバーの壮行ライブを開催してくれ
エルヴィン・バンドに入り5年間世界を回る − 自らのジャズを追求するために86年に帰国
バンドではリーダーの意思が絶対
危機感が募ってきて独立のため帰国
佐藤:「ピットイン」もオープンからずっと40年間、一貫した姿勢でやっています。そのあたりに私と辛島さんは、価値観が一緒で気が合っているのかもしれません。それで、エルヴィン・バンドを辞めたのは、いつ頃だったけ?
辛島:86年ですね。僕はまだ30代の後半で若かったし、このままずっとバンドにいれば、一本立ちできずに終わってしまうという危機感が募ってきたんです。
佐藤:そろそろ独立したいな、と相談を受けたことがありましたね。こちらは「ピットインミュージック」のアーチストとして契約している以上、エルヴィンのバンドとはいえ、いつまでもサイドマンのままでいることもないだろうという判断だった。
辛島:ジャズは自由な演奏ができる音楽ですが、バンドに所属していれば、リーダーの意向に添わなければいけません。「ああいうソロは、自分のバンドでやってくれ」とエルヴィンから指摘されているプレイヤーもいました。私の場合、「花嫁人形」をとことんやり尽くしていった結果、そのうちドビュッシーやラベルみたいな雰囲気になっていったんですね。エルヴィンはそれが不満だったらしくて、「美空ひばりの歌のイントロみたいに弾いてくれ」と言い出したんです。僕らが黒人のブルースが好きなように、エルヴィンもある意味日本人のブルースである歌謡曲や演歌が好きでした。エルヴィンの凄いところは、「花嫁人形」という原曲に振り回されないで、それを超越した世界でドラムを叩いていたことです。けれど、僕はそういう音楽が好きではないからジャズをやっているんですよ(笑)。いまならエルヴィンの気持ちもわかるので、いくらでも望み通りに弾けますけれど、当時の僕は「そんなことできない」って突っぱねたわけです。そうなるとバンドを立ち去るしかありません。
佐藤:エルヴィンは美空ひばりと並んで座頭市も好きでした。世界の第一線でプレイする人間として、強い者に対する憧れというものがあったのかもしれない。
辛島:世界中を旅していると、人種的なことで屈辱的な扱いを受けることがたびたびありました。座頭市は虐げられた境遇をはね返して最後は勝つというストーリーですから、その心情はわかります。
天才ジャック・ディジョネットとの
共演で再び燃える演奏を体感できた
佐藤:辛島さんはバンドを辞めてから、共演するドラマーについて悩んでいたようでした。エルヴィンほどの天才は二人といないわけですからね。
辛島:辞めてすぐは、奥平真吾さんと組むことができたので、それほどショックはありませんでした。でも、彼が91年にニューヨークに渡ってしまって、それから2年間ぐらいですよ、フィットするドラマーがいなくて困ったのは。ピアノを止めようと思ったこともありました。
佐藤:辛島さんは、そこでもう一皮むけたんじゃないかと思います。それがあって、昨年の『グレイト・タイム』で一挙に花開いた感じがしますね。世界最高のドラマー、ジャック・ディジョネットと激しく渡り合っている。
辛島:僕は20枚以上もリーダーアルバムを作ってきましたが、どうしてもどこか一部に納得できないところがあったんですね。ところが、初対面のプレイヤーと同じ目線であれほどの音楽ができた。これは初めての体験だった。『グレイト・タイム』は現時点で僕のベスト作品といえます。
佐藤:辛島さんはドラムを叩けるし、ジャックはピアノを弾けるでしょう。わかり合えることが多かったのではないでしょうか。やはり偉大なドラマーのトニー・ウィリアムスと共演した『イン・サンフランシスコ』(94年)よりも内容がよかった。
辛島:あの時は緊張していましたね。どこかに、まだ自分で力が足らないと思いながら弾いていたところがあった。
佐藤:若い頃とまったく違うんだね(笑)。
辛島:でも今回、初めてジャックとやって、まったく同じ力がぶつかり合ったという感触がありました。ベースのドリュー・グレスを含めて3人に一体感がありました。アメリカやヨーロッパでリリースしても受け入れられる作品だと思っています。
佐藤:ジャックといえば、キース・ジャレットのスタンダーズのイメージが強いですけど、そのクオリティとまったく引けを取っていない。
辛島:確かにみんなが思っているジャックは、スタンダーズということになるのだろうけど、僕にとっては、60年代末から70年にかけてマイルス・バンドにいた頃なんですよ。その時代のジャックを引き出せたかなと思っています。
佐藤:ジャックをあれだけ叩かせたんだからね。かなり燃えたみたいだね。
辛島:燃えたといえば、レコーディングの休憩時間でやった卓球も燃えた。実力伯仲で、二人とも必死だった(笑)。

『グレイト・タイム』収録時の模様(Photo by John Abbott)


『グレイト・タイム』のレコーディングでは演奏も燃えたが、休憩時間の卓球にも熱が入った(Photo by John Abbott)

『グレイト・タイム』収録時の辛島トリオ。左からジャック・ディジョネット、辛島さん、ドリュー・グレス(Photo by John Abbott)
3人のアイドルとの共演を実現したが
「まさにこれから」の気持ちでいる
佐藤:またジャック・ディジョネットと何か残せるといいですね。エルヴィンもトニーもいなくなってしまって、ジャズ・ドラマーの大御所といえば、もはや彼しかいない。
辛島:僕がドラムをやっていた学生時代、エルヴィン、トニー、ジャックの3人はずっとアイドルでした。いつかは彼らと肩を並べて演奏したいと思っていたので、3人と共演できたことは感無量です。
佐藤:3人と共演したピアニストは世界的にもそう多くはいないでしょう。そういう意味では、辛島さんは、これからもっとステップアップしていくアーチストだと思っています。ピットインとしては、万全のサポートをしたいと思っていますね。
辛島:まさにこれからです。「イッツ・ジャスト・ビギニング」(2003年発表のアルバムタイトル)ということですね。
(第5回に続く)
インタビュー・文 田中伊佐資
メイン写真 田代法生(その他の写真 川村容一)
辛島文雄さん(ピアニスト、コンポーザー)プロフィール

本記事は「季刊・analog」にて好評連載中です。「analog」の購入はこちらから
関連リンク