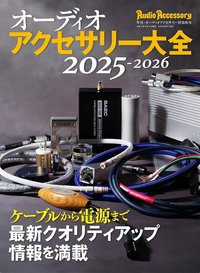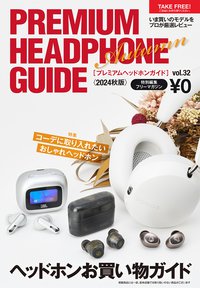デノンのサウンドマスターが作るのは音質だけじゃない。山内慎一氏の仕事哲学から見える、デノンが世界で愛される理由
デノンにおいて、すべての製品の音決めを手がけているのがサウンドマスターの山内慎一氏だ。2015年にサウンドマスターに就任して以来、「Vivid & Spacious」のフィロソフィーのもと実に多くの製品を手掛け、オーディオファンからの確かな信頼を得てきた。
そして2023年にはフラグシップAVアンプ「AVC-A1H」とフラグシップアナログプレーヤー「DP-3000NE」を、2024年には新フラグシッププリメインアンプ「PMA-3000NE」/SACDプレーヤー「DCD-3000NE」をリリース。
“デノンの新たな顔” とも呼べるプレミアム機を一気に打ち出してきた山内氏は、今年でサウンドマスター就任から10年を迎える。そこで今回、デノンをよく知る大橋伸太郎氏が山内氏にインタビューを実施。今改めて、山内慎一という人物に迫ってみよう。

デノンのAVサラウンドアンプの内部に目をこらしてみると、音質上の要所要所にS.Y.の刻印の入ったパーツをみつけることができる。サウンドマスターSHINICHI YAMAUCHI(山内慎一)のイニシャルである。
過去、多くのオーディオメーカーにヒアリングによる音決めをして量産へ向けてGOを出す責任者はいた。しかしデノンのサウンドマスターの仕事はそれとは違う。
山内氏は現在Hi-FiとAV両方のサウンドマスターを務める立場にある。氏は試作機に耳を傾けるばかりでなくその内部深く分け入っていく。AVアンプの部品点数は圧倒的に多いが、構成部品のひとつひとつを検討し必要とあれば、部品メーカーにカスタム品をオーダーし投入する。サウンドマスターには、膨大なパーツ(奏者)が生む音をまとめていくオーケストラ指揮者の耳が必要なのだ。
一昨年のフラグシップ機、「AVC-A1H」の音決めをしたのも山内氏。妥協を知らない氏が音質検討に費やした時間は10か月以上、AVアンプでは過去最長であった。デノンのサウンドマスターの仕事は、従来のメーカーになかったユニークで深いものなのだ。
サウンドマスター山内慎一氏がどんな思いと方法で音を作っていくのか。そこには困難や葛藤はあるのか。そして山内氏がめざす音のゴールとはなにか。率直に訊いてみよう。
フォノカートリッジが取り持ったデノンへの入社
大橋伸太郎氏(以下:大橋):山内さんのキャリアからお教えください。どうしてデノン(入社当時はデンオン)に入社したのですか?
山内慎一氏(以下:山内):一般のオーディオファン同様に、もっぱらの関心は自分の家のオーディオをいかによくするかでした。デノンとの接点は “DL-103シリーズ” を使ったことに始まります。「DL-103LCII」でレコードを聴いていました。そういう縁でデノンを就職先に選びました。
入社は1987年です。バブル経済になりつつあった時期で、最初は業務機器に配属され放送局用の機材を設計しました。当時CDプレーヤーの売り上げがすごく、機種数も台数も増えていて、アナログからデジタルに移行してすぐに定着した時期です。デノンも増産体制に入り機種数が全世界的に増え人も増やそうということになり、私も2年目にCDプレーヤー設計に移りました。

大橋:初めて手がけた民生用の製品は何でしたか?
山内:CDプレーヤー生産が大車輪の時代で、白河工場でふだん流す台数の数倍の台数を作って世界中に供給しようという時期でした。それに忙殺される日々で次から次へ新製品を立ち上げていました。音質と直接関わるようになったのは、「DCD-1650GL」という1991年発売の製品が初めてです。その後90年代の“s1シリーズ”の立ち上げや音作りに関わっていきました。
「デノンのサウンドマスター」という仕事
大橋:サウンドマスターの仕事とは具体的にどういうものですか。
山内:人によってやり方は違いますが、私はユーザーが自宅で聴く状態を想定し、より良さが伝わり感動できるものを作り上げることに力を入れてきました。以前のサウンドマスター、サウンドマネージャーは最終的なジャッジが仕事でしたが、私は開発段階からどっぷり浸かって自分が中心になって仕上げていきます。
大橋:その時の手法は測定でなくヒアリングですね?
山内:その通りです。
大橋:音決めの舞台は川崎市日進町のデノン試聴室ですか?それとも山内さんのご自宅のシステムのエンドユーザー寄りの環境で、ですか?
山内:最近はほぼここ(デノン試聴室)でやっていますが、サウンドマスターになる前は自宅で検討することもありました。連休の時期には開発中の試作を持ち込んで、カンヅメになり何日間か、かかりっきりになった記憶があります。

大橋:例えば、山内さんが手がけた直近の製品に “3000番シリーズ” がありますが、どういうソース(音源)を聴いてチューニングしていくのですか? アンプの「PMA-3000NE」だったら、CD/SACDに加えて配信の音源とか。
山内:SACD/CDプレーヤーを長年担当してきた経緯があるので、ディスクメディアを使うことが多いです。ジャンルでいうとクラシック、ロック、ジャズ、電子系の音楽まで効率よく一枚に集めた物を使います。仕上がってくると、さらに色々な音源を足していきます。