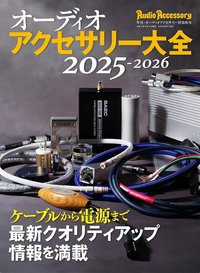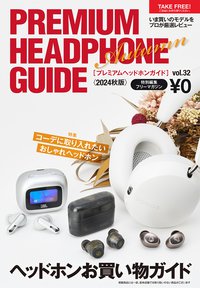タンノイ、銘機の血統ここにあり。数々の名曲を生んだスタジオモニター「SGMシリーズ」、最新サウンドを徹底レビュー
ここでは、そのデザインを踏襲した最新シリーズの概要と、ドライバー口径違いの「SGM 12」「SGM 15」の試聴レポートをお届けする。
■スタジオモニターとしての血脈を現代に継ぐ
1926年、ガイ・R・ファウンテンが創業したタンノイ。長い歴史のなかで、世を驚かせた一つは、67年の進化型のモニター・ゴールド・デュアル・コンセントリック・シリーズを展開したことで、70年代になるとプロフェショナル・スタジオなどで同社モニターがベンチマークとなった。
例えば、ロサンジェルスのA&Mスタジオ、バーニー・グランドマン・マスタリング・スタジオなど著名なスタジオで使われ、ダク・サックスやアル・シュミットなど著名エンジニアも愛用し、数々の著名アルバムが制作された。 そのヘリテージ・スタジオモデルが、今回、最新モデルとして登場。スーパー・ゴールド・モニター「SGM 10」「SGM12」「SGM 15」の3モデルだ。
ドライバー口径は、順に25.4cm、30cm、38cmとなる。 大きな特徴は、進化したデュアル・コンセトリック・ドライバーだ。その象徴は、Yellow Circle(黄金の環)という正面のフレーム・リングだ。中心には金色の3重の同心円状ディフューザー(拡散器)が見える。これがTW(テクノウェーブガイド)トゥイーターだ。
このウェーブガイドの奥に33mmアルミマグネシウム合金のドーム振動板を配置、強力な磁気回路により、高域を再生する。最新のコンピューター解析も行われ、正確な球面波を放出し、振動板からホーンエッジまで等距離になるように設計し、位相特性が格段に向上した。
ウーファー振動板はマルチファイバー・ペーパーコーン製だ。空気乾熱によって最終処理する工程を経て、分割振動を最小に抑え、優れたトランジェントとパワーハンドリングを実現。ボイスコイル周辺に特殊な薬剤を含浸させ、中域と低域の拡散性も向上した。
このドライバーではトゥイーターとウーファーの駆動軸が一致することが重要で、ウーファーエッジには、ロールエッジを2重にしたツインロールエッジを採用し、コーン形状は高域のテクノウェーブガイドと抵抗なくスムーズに動作する方式とした。
磁気回路はトゥイーターとウーファー独立のツイン・マグネットシステムで、高域のテクノウェーブガイドがウーファーのポールピースの役割を果たす。異方性バリウムフェライトマグネットを採用しオリジナルのアルニコ・マグネットを超える強力な磁気回路を構成。
ネットワーク回路では高音質パーツが吟味され、高域調整が行え、SGM15では音楽の臨場感を可変するプレゼンス・エナジーも搭載。このように、同社の最新技術が搭載されているのだ。
■内包する空間表現をストレートに再生
最初にSGM 12を試聴した。その音は、まさに音楽に内包する空間表現をストレートに再生し立体空間を作り出すことが特徴だ。85年発売のオリジナルSGMモデルではやや高域に硬さを感じたが、高域から中域まで繋がりがスムーズで滑らかだ。ヴォーカルの声質や声使いがリアルで、演奏の実在感を鮮明にする。
ピアノ・ジャズトリオでは、ピアノの立ち上がりが俊敏で、消え入る余韻に透明感がある。ドラムスでは高い音圧を示し、ドラム表面の質感までも再現。シンバルも素晴らしい。響きが噴出しスリリングだ。ベースでは弦の震えが見えるようで胴の響きも鮮明。音に厚みがあり高解像度だが、刺激感皆無で、高い音圧の、この音色に浸っていたくなる。
SGM15では、さらに音場は拡大され、まさにマッシブな音楽が聴ける。例えばパイプオルガンを聴くと、その響きと音圧に圧倒される。急峻に立ち上がる旋律では、演奏のエネルギーが全開となる。一方、音圧感度が高いので、弱音、繊細さ、柔らかさもよく引き出す。SGMシリーズは実にデザインもよく、音楽の躍動を鮮明にする。さすが、進化を遂げたスタジオモニターだ。
(提供:ティアック)
本記事は『季刊・Audio Accessory vol.194』からの転載です