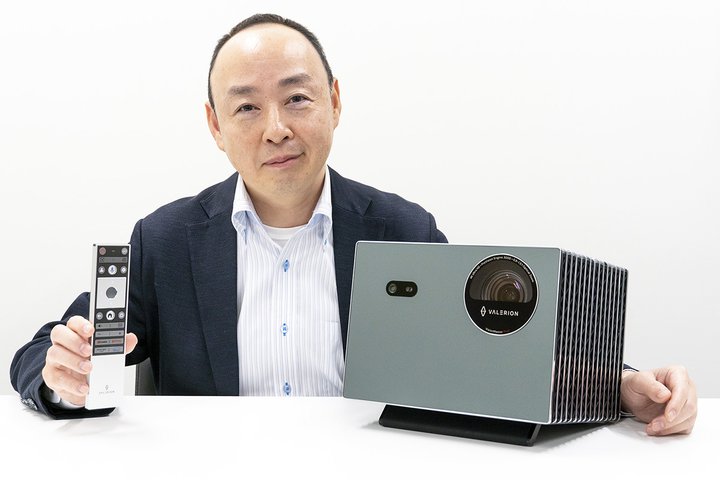公開日 2012/11/27 13:06
ピエガの魅惑に浸った5&1/2 Days(後編)− ショスタコーヴィチ『交響曲第5番』の音を読み解く
【連載】極 kiwami〜魅惑の響きを求めて

※前編はこちら
ショスタコーヴィチ『交響曲第5番』の音を読み解く
今回の試聴ディスクとして選んだのはSACDシングルレイヤー・ディスクの中でも特に高音質と言える1枚である。ニコライ・アレクセーエフ指揮/アーネム・フィルハーモニー管弦楽団の『ショスタコーヴィチ 交響曲第5番』(EXTON OVGL-00017)だ。これはハイブリッド盤でも発売されていたが、音質は全く違う次元にまで向上している。
この曲にはいわれがある。1930年代のロシアではあらゆる芸術的創造が〈社会主義リアリズム〉の範疇に入るものでなければならず、これを逸脱した芸術家たちには追放や投獄の危険が迫っていた。その矛先はすでに作曲家として活躍していたショスタコーヴィチにも向けられ、1933年に書かれた彼のオペラ『ムツェンスク郡のマクベス夫人』が「ブルジョワ的で荒唐無稽な作品」として批判の対象となった。彼は最終的に、生活のためにロシアで生きるていくことを決めるが、国家の規範の中での仕事に対し彼がいかに苦吟したかは想像に難くない。私はこの曲を聴きながら、当時ショスタコーヴィチが語った言葉の意味を探っていた。
この曲を初めて聴いた時感じたのは、作曲者の心の昂りと苦渋の相剋である。ショスタコーヴィチ自身の言葉によれば、この楽章の内容は「自己の人生への問いかけ」で、第1楽章冒頭の弦楽器のカノンはその端的な表現だという。そこでは低弦(チェロ/コントラバス)を高弦(第1/第2ヴァイオリン)が追っていくがその響きは「なぜ?」という問いかけに聴こえる。か細い弱音でスタートしたヴァイオリンの響きが次第にクレッシェンドしていくのは意識の高揚を表現していると受け取っていいだろう。
このように張りつめた弦の響きは、音の再生上で難しい問題を惹起しやすい。中・高音域が突っ張った弦楽器の響きはひとつ間違うと刺激的に聞こえたり、歪んで聞こえたりするからだ。特に強音で演奏する時にはそのことが言える。耳の特性上最も聞こえやすいのが中音域であることはよく知られているが、この帯域で刺激的な音が発生すると聴くに絶えない音となりがちなのだ。
Coax 90.2を中心としたシステムでは、この音域がリアルに美しく再現できている。ぎりぎりまで張りつめた中・高音だが、最強音でもそれが歪むことはなく、透明で滑らかな感触に満ちている。高弦が表現上で緊張感を極限まで高めながら違和感を感じさせないのは希有な体験であると言っていいだろう。緊張感を維持しながらしなやかなニュアンスの表出もできるのは、ピエガの同軸リボンユニットが持つ好ましい特質だと思っていい。
低弦が奏し始めるリズミックなメロディーは、低迷している心を表しているように受け取れる。これに続く展開部の冒頭では音楽的にもサウンド的にも大きな変化が表れる。オーケストラの一部として加えられたピアノと低弦が重々しく響くリズムを奏で、その中で4本のホルンが不気味な主要主題を吹奏し、2本のトランペットがそれを引き継いでいく。この部分では、オーディオ的に明確な音像定位の表出が要求される。ピアノの音像は左スピーカー寄りに定位し、ホルンはや右寄りに、トランペットは右寄りにくっきり定位していなければならない。Coax 90.2の音像定位は実にアキュレートで、各々の楽器の配置が正確に表出できている。
再生音として好ましいと思ったのは、中・高音と低音のエネルギーがバランスよく聴けたことだ。前回90.2の試聴では僅かではあるが中・高域のエネルギーが強く、低音域のエネルギーがやや弱く感じられたが、今回の試聴では高低のバランスが整った安定したサウンドになっており、前回の試聴で僅かに感じた違和感は消えていた。プリアンプ以外のシステム構成は変えていないし、スピーカー位置も前回と同じだから、この改変はプリアンプJubilee Preampによるところが大きいと思っていいだろう。
エネルギッシュな第2部に続く第3部では、テンポが上がり、行進曲のようなリズムが表れ演奏の活気が増してくる。第4部ではティンパニーとスネアのリズムに乗った行進曲でトランペット群が主題を吹奏する。第5部では弦と木管と金管の響きが複雑に積み重ねられクライマックスに達する。続く再現部ではゆったりとしたテンポで弦、木管、ホルンのユニゾンが響きわたる。この楽章の最後をしめるコーダでは、ピッコロとソロ・ヴァイオリンが前出の主題を反復し、そこにはチェレスタも加わっている。
展開部で活躍する多彩な楽器の音を聴きながら改めて感じたのは、このシステムの中・高域における解析力の高さだ。多彩な楽器の音をリアルな音色で聴き分けられる楽しみは実に魅惑的だ。音離れの良さと音の立ち上がり、立ち下がりのリアルな感触はリボンユニット独特の感触である。音の遅れが全くなく、位相のずれも感じられない。特に素軽く飛んでくる管楽器の音は爽快そのものだ。多彩な楽器の響きに忠実なサウンドはピエガの高級スピーカーに共通する大きな特長だと言っていい。
分解能の高さが細部のニュアンスまで感じさせてくれる
第2楽章の快活なスケルツォは諧謔に満ちている。まずチェロとコントラバスのユニゾンによる強奏が出るが、ここでの聴きどころは押し出しが強い瑞々しい低音弦の表現だ。チェロだけのユニゾンではこんな押し出しの強さは得られないし、コントラバスだけのユニゾンではこれだけ瑞々しいサウンドにはなり難い。チェロとコントラバスが同じ音を奏してこそ、ダイナミックでかつ魅惑的な響きが得られることが判るのだ。やがてこの低音弦の主題にホルンが応えるように楽しい響きを導入し、それに誘われるようにフルート、オーボエ、ピッコロクラリネットなどの木管が軽快なメロディを奏でる。ここで聴きたいのは切れのいい低弦のリズミカルな響きと、軽快に飛翔する管楽器の好ましい対比である。管楽器の音源が演奏空間の中に止まっているように感じられてはだめで、空間を素早く飛翔してリスナーの耳に到しなければいけない。Coax 90.2のリボントゥイタータは実に素軽くこの飛翔感覚を実現する。
やがて同じテーマをコンサート・マスターがヴァイオリン・ソロで弾き始める。この部分では時にグリッサンド(アクセントを付けずに滑るように弾く奏法)が用いられているが、その微細な音のニュアンスが克明に伝わってくるのが判る。
これに続くのはストリングスのピッチカートに乗ったフルートとファゴットのソロで途中ではハープのグリッサンドが聴ける。ここからは全奏とソロが交互に出てくるが、ピッコロ、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットなどが合奏し、ホルンと弦がそれを引き継ぐなど楽器の組み合わせも、奏法も多彩である。本来重い響きを奏でるチューバが軽やかに演奏したり、ファゴットとコントラファゴットがユニゾンで吹く箇所もあり、その上でピッコロが短い装飾を加えたりする。多彩な楽器の饗宴を楽しみつつ繰り返し聴いてみると、それぞれの楽器がどう使われ、どんな効果を表出しているかが判るようになる。
こうした箇所で問われるのが再生システムの解像度・分解能の高さである。演奏の細部のニュアンスや楽器の構成を探ることは、システムのクオリティを探ることにもなるのだ。ノイズの少ない《ボワ・ノワール》の中で聴くピエガを中心としたシステムは、その能力をフルに発揮したと言っていいだろう。再現部ではシロフォンを加えた変わった楽器編成で演奏され、ティンパニーの2小節だけのソロが印象的な打音を響かせ、それを追った短いコーダでこの楽章は終わる。90.2の低音ユニットは低音弦の芯の強さと引き締まった表情を充分に体感させてくれる。
「音の華」と言える魅惑を味わえた3楽章
第3楽章は最も美しい演奏が聴ける楽章だ。ここで気づくのは弦楽器の編成がユニークなこと。ヴァイオリンは一般的な2群編成ではなくて3群編成、普通は1群のみのビオラとチェロも2群編成を採用している(コントラバスは1群のみ)。作曲者の狙いが弦楽器の編成を細分化し繊細で微妙なニュアンスを漂わせることにあることは明らかだ。それは深い観念の思考、透徹した悲しみ、抑えられても燃え上がる情念など、人間の感情の複雑な表現でもある。
念のため言っておくと、弦の各群の音の定位を探ったりしてもはっきりとは聴き分けられない。ここで感受すべきは複雑で緻密な音の構成であって、音像の配置や動きではないからだ。この楽章は管楽器では木管のみが演奏し金管楽器はすべてお休みである。息の長い弦の演奏の後に、ハープの響きを背景にフルートのソロが印象的な旋律を奏でる。ここからの部分で印象に残ったのは、ヴァイオリンの緻密なトレモロの上でオーボエ、クラリネット、フルートなど木管のソロが叙情的なメロディーを吹いては消えていく部分で、まるで室内楽の美しいフレーズを聴いているような気分となる。ここは再生システムの解像度の高さがフルに活きるところだが、ピエガCoax 90.2のシステムはさらに「音の華」と言える魅惑を付け足してくれた。それだけ美しさが際立っているのだ。
“勝利の饗宴”を力強く歌い上げるための低音調整
第4楽章の冒頭では吹奏楽器が主題を最強音で吹ききり、ティンパニーが力強いリズムを打ち出す上に、トランペットとトロンボーンが輝かしいメロディを強奏する。この楽章は冒頭のテーマを中心にした行進曲風のフィナーレで、ティンパニーの強打が続き、金管の輝きに満ちた咆哮が聴ける。中間に流麗なメロディが聴ける部分はあるものの、全体の印象ではティンパニーを主軸とした力強い音の饗宴である。
曲の終わりには、ティンパニーと共にグランカッサ(大太鼓)の8つの強打音が聴く者の身体を直に揺すってくる。このフィナーレは圧倒的勝利を意味するユニゾンで曲を閉じる。音の饗宴は勝利の饗宴でもある。この曲は、この楽章あるがゆえに政府機関からも認められ、民衆にも歓迎された。外面的には「社会主義的リアリズム」の勝利を高鳴らせたのだろうが、ショスタコーヴィチの心の内を推測すると、そう簡単には言い切れぬものを感じる。
この楽章ではグランカッサの響きを聴いて最後のシステム調整を行なった。ここまでの演奏では全音域のエネルギー・バランスが整っていたが、グランカッサの量感が予想以上に大きく、その分重低音の響きが少し緩いと感じたからだ。ここで行なったのは低音を量的に弱める調整ではなく、重低音と低音の締まりを強くした調整だ。具体的にはCoax 90.2に付属のスパイクを取り付けたこと。これでこの楽章を聴き直すと、グランカッサやティンパニーの締まりが向上し、力感と強い音の芯が両立した理想的な低音表現が得られた。この調整後再び全楽章を聞き直したが、低音の違和感が全くなくなり真にパーフェクトと言えるエネルギー・バランスが得られるようになった。
別れを惜しむ
5日間同じディスクを聴き、必要に応じ微調を行なってきたCoax 90.2のサウンドは魅惑の塊であった。fレンジの広大なサウンドはクラシックの大オーケストラのスケールを余すところなく表出し、リボン同軸ユニットの緻密な細部の表現は、解像度の高さがあらゆる演奏の表情を克明に表出し、リアルな音の立ち上がりとスピード感を堪能させてくれた。全ての違和感が払拭されたサウンドは、試聴したショスタコーヴィチやマーラーの難曲から、これ以上リアルな表現はないという感触を導き出してくれた。
この曲とはスコア片手に5日半付き合ったが、いつの間にかぶつぶつとメロディを呟くようになっていた。似たことはスピーカーにも言える。ここまでじっくり付き合うと〔相手〕の疲れ体調が判るようになってくるのだ。疲れてきたなと思えばクロスでボディを拭きながら「寝ようか」と呟き、音が変わったと思えば、湿度計を持っていき指針を見せてやったりしていた。しかし時は無情である。別れがやってきたのだ。梱包される美しい後ろ身の曲線を見ながら私は心の中で囁いた。「こんどは何時逢える」、一瞬「待って」という答えが聞こえたと思いはっとしたが、それは積み荷を車に乗せていたスタッフの声であった。