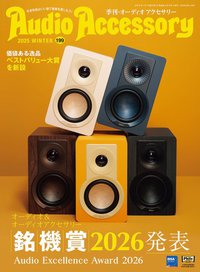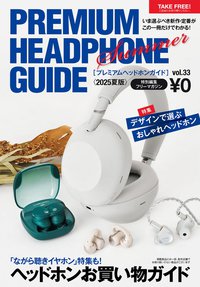公開日 2013/03/18 00:05
最上位機の思想を踏襲した完全バランス型プリ − エソテリック「C-03X」に触れる
設計思想を引き継ぎながらスリム化を図る
■フルバランス化と徹底したインピーダンス設計
エソテリックが昨秋投入したC-02は同社が掲げる「マスターサウンドワークス」のコンセプトを具現化した同社のプリアンプのトップモデルである。その設計思想を受け継ぎながら回路構成の一部を簡略化して筐体のスリム化を図ったのが本機C-03Xで、外見こそ前作のC-03によく似ているが、中身は別物と言っていい。本機はC-02と並行してほぼ同時に開発されているため、C-03よりもC-02との共通点が目を引くのだ。
前作から最大の変更点は入力バッファー以降に完全バランス構成のアンプ回路を採用したことで、シングルエンド構成の前作とは回路規模が大きく異なっている。フルバランス化と徹底した低インピーダンス設計の高価はS/Nの数値に顕著に表れており、C-03の100dBに対して本機は116dBを達成。この数値はC-02と同等であり、再生音を劇的に向上させる可能性が高い。
完全デュアルモノ設計は前作と同様で、4分割セミダブルデッキ構造によってセパレーションを確保するなど、シャーシのレイアウトは本機も凝りに凝っている。
電源部は左右チャンネルを独立させた2基のトロイダルトランスを投入したほか、コントロール部専用に独立したトランスを用いてノイズの混入を回避、3トランスの強力な構成で純度を高めている。
フルバランス化に伴ってボリューム回路はC-02と同様、左右および正負ごとに独立させた計4回路のゲイン可変回路を連動して操作する「ESOTERIC-QVCS」に変更された。チャンネルセパレーションと位相特性の改善が大きなテーマで、信号経路の短縮にも一役買っている。
QVCSを制御するコントロール基板とオーディオ回路の間にはフォトカプラを挿入して電気的に分離しているため、マイコンからのノイズ混入を心配する必要はない。もちろん、ボリューム操作時以外はマイコンを完全に停止させるシステムを今回お投入しているので、その意味でもノイズ対策にはまったく隙がないと言っていい。
出力バッファー回路はC-03も強力な内容を誇っていたが、今回はC-02と同様、「ESOTERIC-HCLD」回路を搭載し、パワーアンプの駆動能力を高めることに成功したという。
独立基板で構成される出力バッファー回路にスルーレート2000V/μsという桁違いの応答速度を持つ素子を導入していることが特徴で、電流出力の性能を格段に向上させることが期待できる。同回路はRCA出力は各端子ごと、XLR出力にはホット/コールドそれぞれに1回路ずつ積んでおり、贅沢極まりない構成が目を引く。
さて、ここまでC-02との共通点、C-03からの変更点を中心に紹介してきたが、それではC-02と本機の間にはどんな違いがあるのだろうか。
外見上から分かるようにC-02は本機よりも約30mm背が高く、奥行きも8cmほど大きい。重さにいたってはちょうど10kgの違いがある。本機も22kgとプリアンプとしては重量級だが、C-02の質量はなんと32kgもある。
C-02がパワーアンプ並みの重さになった最大の理由は電源トランスの数の違いにある。L、Rそれぞれ入力アンプと出力アンプの電源トランスを独立させ、さらにコントロール回路用にてっとトランスを追加した計5トランス構成を採用しているのだ。そのトランスの高さの分だけC-02は背が高くなっていると考えていい。
また、整流回路のショットキーバリアダイオードにシリコンカーバイドタイプの素子を使っている点にも違いがあるが、これは電源回路の低ノイズ化とハイスピード化につながるという。物量という尺度でみたとき、C-02の余裕はさらに一段階上をいくということだ。
■音に触れる − CDからハイレゾ音源に切り替えたような変化
エソテリックの試聴室で本機の音をじっくり聴くことができたので、C-03やC-02との比較も含めて、再生音の特徴を紹介することにしよう。G-01を接続したP-02/D-02から本機のXLR入力に接続し、A-02でタンノイのDC10Aを駆動するというシステムだ。
C-03とC-03Xで同一音源を聴き比べると、今回の進化の大きさをはっきり聴き取ることができる。ソル・ガベッタが独奏を弾くエルガーのチェロ協奏曲の冒頭、弓を弦に乗せて重音の深い響きが立ち上がる瞬間、C-03Xで聴くチェロはアタックのエネルギーが非常に大きく、音が出ると同時に周囲の空気が一変する感覚が驚くほどリアルに実感できた。
旋律が動き出した後はC-03との違いはそれほど極端ではないが、立ち上がりの速さとアタックの力感に生まれる差はオケの木管や金管からも確実に聴き取ることができた。
アタックが速く力強いとは言え、それはいわゆる輪郭を強調した音とは本質的な違いがある。例えばベースの伴奏で歌うバーブ・ジュンガーのヴォーカルは子音の感触が強まることがなく、ベースのピチカートに乾いた感触はない。
輪郭を強めにすると、きつくドライなタッチになりやすいのだが、C-03Xはそれとは逆に声とベースの音色が滑らかで、スーッと浸透していく感触が心地よい。CDからハイレゾ音源に切り替えたときのような変化と言えば分かりやすいだろうか。C-03も音色自体は硬くないのだが、不思議なことに、立ち上がりが速くなると声の滑らかさがかえって際立つ高価があるようだ。
S/Nの改善は全ての試聴ソースから聴き取ることができるが、なかでも室内楽では著しい効果を確認することができた。田部京子とカルミナ四重奏団のシューベルト≪ます≫を聴くと、5人のブレスに続いて最初の和音が立ち上がった瞬間、澄み切った見通しの良い音場がフワッと広がり、清澄なハーモニーが部屋を満たす。
その響きから私が連想したのは、遠くまで見通せる真冬の屋外の風景であり、霧が晴れた瞬間の山頂からの眺めであった。どの音域にも音像のにじみがなく、風通しの良さは申し分ない。
ピアノは低音から高音までくもりがなく、旋律が軽快な足取りで前に進み、ヴァイオリンは動きの速い装飾音符が一音一音クリアに浮かび、奏者のたしかな技巧が際立つ。
最後に、C-02の音も参考までに聴いてみた。本機とC-02の基本的な音調はかなり近く、特に立ち上がりの速さや細部まで見通せる静寂感はほぼ同じ次元にあると言っていい。一方、コントラバスとピアノの基音の深さ、余韻の広がりはC-02の余裕が一歩上回る印象が伝わってきた。
予想した方向で両機種に違いが存在することは確認できたが、C-03Xの音がレファレンス機にここまで肉薄していることまでは粗造できなかった。
エソテリックが昨秋投入したC-02は同社が掲げる「マスターサウンドワークス」のコンセプトを具現化した同社のプリアンプのトップモデルである。その設計思想を受け継ぎながら回路構成の一部を簡略化して筐体のスリム化を図ったのが本機C-03Xで、外見こそ前作のC-03によく似ているが、中身は別物と言っていい。本機はC-02と並行してほぼ同時に開発されているため、C-03よりもC-02との共通点が目を引くのだ。
前作から最大の変更点は入力バッファー以降に完全バランス構成のアンプ回路を採用したことで、シングルエンド構成の前作とは回路規模が大きく異なっている。フルバランス化と徹底した低インピーダンス設計の高価はS/Nの数値に顕著に表れており、C-03の100dBに対して本機は116dBを達成。この数値はC-02と同等であり、再生音を劇的に向上させる可能性が高い。
完全デュアルモノ設計は前作と同様で、4分割セミダブルデッキ構造によってセパレーションを確保するなど、シャーシのレイアウトは本機も凝りに凝っている。
電源部は左右チャンネルを独立させた2基のトロイダルトランスを投入したほか、コントロール部専用に独立したトランスを用いてノイズの混入を回避、3トランスの強力な構成で純度を高めている。
フルバランス化に伴ってボリューム回路はC-02と同様、左右および正負ごとに独立させた計4回路のゲイン可変回路を連動して操作する「ESOTERIC-QVCS」に変更された。チャンネルセパレーションと位相特性の改善が大きなテーマで、信号経路の短縮にも一役買っている。
QVCSを制御するコントロール基板とオーディオ回路の間にはフォトカプラを挿入して電気的に分離しているため、マイコンからのノイズ混入を心配する必要はない。もちろん、ボリューム操作時以外はマイコンを完全に停止させるシステムを今回お投入しているので、その意味でもノイズ対策にはまったく隙がないと言っていい。
出力バッファー回路はC-03も強力な内容を誇っていたが、今回はC-02と同様、「ESOTERIC-HCLD」回路を搭載し、パワーアンプの駆動能力を高めることに成功したという。
独立基板で構成される出力バッファー回路にスルーレート2000V/μsという桁違いの応答速度を持つ素子を導入していることが特徴で、電流出力の性能を格段に向上させることが期待できる。同回路はRCA出力は各端子ごと、XLR出力にはホット/コールドそれぞれに1回路ずつ積んでおり、贅沢極まりない構成が目を引く。
さて、ここまでC-02との共通点、C-03からの変更点を中心に紹介してきたが、それではC-02と本機の間にはどんな違いがあるのだろうか。
外見上から分かるようにC-02は本機よりも約30mm背が高く、奥行きも8cmほど大きい。重さにいたってはちょうど10kgの違いがある。本機も22kgとプリアンプとしては重量級だが、C-02の質量はなんと32kgもある。
C-02がパワーアンプ並みの重さになった最大の理由は電源トランスの数の違いにある。L、Rそれぞれ入力アンプと出力アンプの電源トランスを独立させ、さらにコントロール回路用にてっとトランスを追加した計5トランス構成を採用しているのだ。そのトランスの高さの分だけC-02は背が高くなっていると考えていい。
また、整流回路のショットキーバリアダイオードにシリコンカーバイドタイプの素子を使っている点にも違いがあるが、これは電源回路の低ノイズ化とハイスピード化につながるという。物量という尺度でみたとき、C-02の余裕はさらに一段階上をいくということだ。
■音に触れる − CDからハイレゾ音源に切り替えたような変化
エソテリックの試聴室で本機の音をじっくり聴くことができたので、C-03やC-02との比較も含めて、再生音の特徴を紹介することにしよう。G-01を接続したP-02/D-02から本機のXLR入力に接続し、A-02でタンノイのDC10Aを駆動するというシステムだ。
C-03とC-03Xで同一音源を聴き比べると、今回の進化の大きさをはっきり聴き取ることができる。ソル・ガベッタが独奏を弾くエルガーのチェロ協奏曲の冒頭、弓を弦に乗せて重音の深い響きが立ち上がる瞬間、C-03Xで聴くチェロはアタックのエネルギーが非常に大きく、音が出ると同時に周囲の空気が一変する感覚が驚くほどリアルに実感できた。
旋律が動き出した後はC-03との違いはそれほど極端ではないが、立ち上がりの速さとアタックの力感に生まれる差はオケの木管や金管からも確実に聴き取ることができた。
アタックが速く力強いとは言え、それはいわゆる輪郭を強調した音とは本質的な違いがある。例えばベースの伴奏で歌うバーブ・ジュンガーのヴォーカルは子音の感触が強まることがなく、ベースのピチカートに乾いた感触はない。
輪郭を強めにすると、きつくドライなタッチになりやすいのだが、C-03Xはそれとは逆に声とベースの音色が滑らかで、スーッと浸透していく感触が心地よい。CDからハイレゾ音源に切り替えたときのような変化と言えば分かりやすいだろうか。C-03も音色自体は硬くないのだが、不思議なことに、立ち上がりが速くなると声の滑らかさがかえって際立つ高価があるようだ。
S/Nの改善は全ての試聴ソースから聴き取ることができるが、なかでも室内楽では著しい効果を確認することができた。田部京子とカルミナ四重奏団のシューベルト≪ます≫を聴くと、5人のブレスに続いて最初の和音が立ち上がった瞬間、澄み切った見通しの良い音場がフワッと広がり、清澄なハーモニーが部屋を満たす。
その響きから私が連想したのは、遠くまで見通せる真冬の屋外の風景であり、霧が晴れた瞬間の山頂からの眺めであった。どの音域にも音像のにじみがなく、風通しの良さは申し分ない。
ピアノは低音から高音までくもりがなく、旋律が軽快な足取りで前に進み、ヴァイオリンは動きの速い装飾音符が一音一音クリアに浮かび、奏者のたしかな技巧が際立つ。
最後に、C-02の音も参考までに聴いてみた。本機とC-02の基本的な音調はかなり近く、特に立ち上がりの速さや細部まで見通せる静寂感はほぼ同じ次元にあると言っていい。一方、コントラバスとピアノの基音の深さ、余韻の広がりはC-02の余裕が一歩上回る印象が伝わってきた。
予想した方向で両機種に違いが存在することは確認できたが、C-03Xの音がレファレンス機にここまで肉薄していることまでは粗造できなかった。