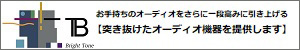25タイトルが順次発売!
ユニバーサル「ハイレゾCD」にオフコースとイージー・リスニングの名盤達が登場。愛聴盤がもう1枚欲しくなる“ハイレゾの旨味”を聴いた
全盛期から現在まで、進化してきた「音」を堪能できる
その後ベスト盤を挟みつつ、『SONG IS LOVE』『JUNKTION』『FAIRWAY』とアルバムが進むに連れ、音はどんどん音像がどっしりと安定し、存在感が太く濃厚になってくる。これは推測だが、収録機材の品位が上がったなど時代を経るに従っての録音環境の進化も大きく関係しているのではないか。楽器の編成も徐々にアコースティックの率が減り、全盛期のエレクトリックなサウンドに近付いていく。少々下世話な物言いとなってしまうが、レコーディングからキャスティングまでコストをかけた作りになっていく印象だ。
そして、5人編成の『バンド』として新生した『Three and Two』で、彼らのサウンドはまた大きく羽ばたく。何より、それまでどこか折れそうな細さ、繊細さを感じさせた小田のヴォーカルが一気に全盛期のそれに近い力強さを備え、独特の節回しも完成された感がある。まさに激変である。メガヒットこそ後年に譲るが、この時点でもう彼らは音楽界を制覇する準備を整えていた、といっても過言ではないのだろう。
彼らにとって2枚目のライヴ盤、その名も『LIVE』は、何よりオープニングの観客の歓声に驚く。1枚目とノリが全然違うのだ。演奏も前作とは全然違い、もうまるでジャンルの違うグループである。フォーク・デュオのコンサートだった前作に対し、本作はまさにロックバンドのライヴである。録音もそれに応じ、音場感よりもより音像の実体感を重視しているようなイメージがある。どちらも良い録音だが、ここまで対照的な作品が残るのも珍しいのではないか。ひょっとすると、70年代フォーク・ミュージックから80年代ニュー・ミュージックへの進化の過程を、オフコースというグループが体現しているのかもしれないな、などとも感じた。
そして彼らの代表作『We are』が登場する。曲想はまさに全盛期の彼らそのもので、ややメロウなロックバンドのサウンドである。非常にクールでクリーンなエコーを伴った、ヴォーカルやエレキギターが耳をくすぐる。やや意外な事実ではあるが、ここまでの10枚はオリコン・チャートのアルバム1位を獲得しておらず、『We are』から鈴木脱退後の『Back Streets of Tokyo』まで、7作連続1位という快挙を成し遂げることになる。楽曲、演奏、録音とも、それにふさわしい完成度というほかない。文字通りの脱帽ものである。