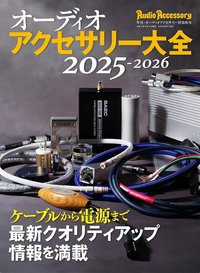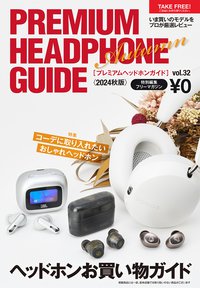鬼才ロバート・ワッツ氏が語る、CHORD「Hugo」がレファレンスである理由

英CHORD Electronics社にとって、初めてのポータブルヘッドホンアンプとなる「Hugo」が発表された。同社初のDAコンバーターである「DAC64」が発売されてからおよそ15年経過するが、汎用のチップを使わずに独自のアルゴリズムをプログラミングすることで、高品位なDA変換を実現するというアプローチを採り続けているのが、同社の最大の特徴だ。
その先進性は未だ色褪せることなく、それどころか新製品「Hugo」ではまた一層の進化を遂げた。今回「Hugo」の国内発表会の開催に合わせて、CHORDのデジタル関連のアルゴリズム開発に携わるロバート・ワッツ氏が初めて来日し、「Hugo」への思いを語った。
■フランクス氏とワッツ氏が出会い、CHORDのDAコンバーターが誕生した
そのフランクス氏の元に、オーディオのデジタル周りのアルゴリズム開発を手がけるエンジニア、ロバート・ワッツ氏が合流したのはいまから20年ほど前のことだったという。学生時代に自身のオーディオブランドを立ち上げ、その後オーディオメーカーでDACやCDプレーヤー、アンプの製品開発にも携わってきたというワッツ氏は、デジタルとアナログ双方でオーディオに関連する深い見識を持つ人物だ。
フランクス氏は二人が初めて出会い、CHORD初のDAコンバーター「DAC64」の開発が起ち上がった経緯を振り返る。
■前人未踏の高音質を追求するために「FPGA」は不可欠だった
ワッツ氏はCHORDと出会う以前から、カスタムメイドのFPGAを駆使したオーディオDACの開発にはすでに着手していたが、DAC64が生まれようとしていた1998年頃にFPGAの技術自体が進化して、アルゴリズム開発の自由度が高まってきたのだという。
「現在、CHORDの製品にはXilinx(ザイリンクス)のFPGAを使っていますが、当初はゲートアレイの巨大さと複雑さ、不安定さを乗りこなすのに一苦労でした。ザイリンクスのFPGAではS-RAMフラッシュにプログラムを書き変えながら使えるようになったことから、開発の利便性が飛躍的に向上し、スピードアップが図れました」(ワッツ氏)
ワッツ氏がこのザイリンクスのFPGAを選ぶ理由は、64bitの演算を9.6ナノ秒で処理できるという演算能力の高さゆえという。ザイリンクスの前にワッツ氏が使っていた別ブランドのFPGAは同条件の処理速度が100ナノ秒だったというから、その差は歴然だ。
FPGAが進化すればキャパシティが広がり、より複雑で高度なプログラミングを描けるようになる。「絵画に例えるならば、より大きなキャンパスで画が描けるような感覚に近いと思います。オーディオの処理も高音質化へとつながるような、ディテールに及ぶプログラムを組み込むことができます」(フランクス氏)
ただ当然ながら、FPGAのキャパシティが拡大するということは、ワッツ氏にとって「できること」と「やらなければならないこと」が増え、プログラミングの内容も複雑化するはずなのだが、実際には開発環境も平行して進化を遂げているため、ワッツ氏にとっては大きな負担要素ではないという。「現在の開発環境ではソフトウェアによるシュミレーションツールも発達しているので、先に検証を行いながら問題をつぶして、プログラミングの完成度を効率よく高めていくことができます」(ワッツ氏)
次ページ徹底したリスニング評価により練り上げられるCHORDのアルゴリズム