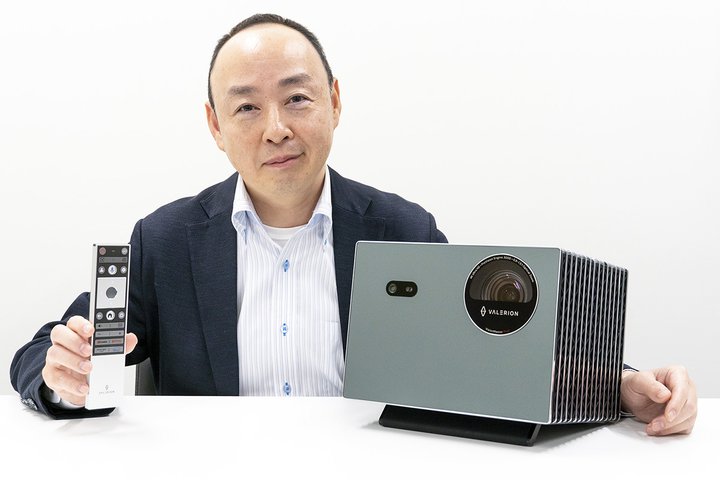公開日 2009/07/13 21:29
TAD-CR1/TAD-M600開発担当者が語る、音作りにかけた思いとは
開発者緊急インタビュー
既にお伝えしているとおり、(株)テクニカル オーディオ デバイセズ ラボラトリーズからハイエンドコンパクトスピーカー「TAD-CR1」とモノパワーアンプ「TAD-M600」が発表された。その音を「特別な存在」と評する山之内 正氏が、新製品開発者に緊急インタビューを行った。インタビューの詳細な内容は8月21日発売の「季刊 オーディオアクセサリー」に掲載予定だが、本項では読者のみなさまが気になる「製品の音」を想像できるよう、開発陣の「音作り」にかけた思いを先駆けてお伝えしよう。
■CSTユニットの可能性を追求したい ー TAD-CR1にかけた理想とは
「CR-1は、コンパクトサイズでしか出せないCSTユニットの良さが発揮されたスピーカーです」と語るのは、開発に携わったエンジニアのひとり、長谷 徹氏だ。
「Coherent Source Transducer」の頭文字をとった「CSTユニット」。ベリリウム振動板を採用し、250Hz〜100kHzという広いレンジをカバーする、TADの代名詞とも言える存在だ。2003年のTAD-M1、そして、採算を度外視し、TADラボの理想と技術を結晶化させたフラグシップスピーカー「TAD-R1」(2007年)にも搭載されている。
「CSTユニット開発当初、その音を聴いて『なんてエネルギッシュなんだろう』と驚いたのを覚えています。本当に、今まで聴いたことのない音でした。いくつかサイズ違いのキャビネットに入れ替えたところ、聞こえてくる音がまた全く違う。CSTというユニットが持つポテンシャルの高さを感じました」。
そんなCSTユニットを使って、R1とは違う表現ができるはずだ − コンパクトモデルの開発は2004年からスタートした。
「キャビネットをコンパクト化した以外に、音作りの部分で『何か変えよう』と思った部分はありません。CSTユニットはもう“完成”している。ですから、その可能性を発揮させるシステムのまとめ方がキーだと考えました」と言う長谷氏。TAD-CR1のキャビネット製作にあたっては、定在波の影響などについて、解析ソフトを用いた綿密なシミュレーションを行った。R1にも携わったアンドリュー・ジョーンズ氏、バート・ロカンシー氏らとともに作り上げたという。「アンドリューの感性とTADエンジニアの理論を合わせ、“世界で通用する音”を生み出すことを目指しました」。
「TAD-CR1は新しいスピーカーの表現を聴かせてくれた」と評する山之内氏。「単なるR1の小型モデルではない、このサイズならではの魅力がある。ボディは小さいけれど、その持つ意義は大きいスピーカーだと感じました」と語った。
ただシンプルに、良いものを作るために − 理想に忠実に作った「TAD-M600」
TAD-M600の開発コード名は「XC」。これは「Cross Century」を意味するという。「20世紀にできなかったことを21世紀に実現しよう、そして、世紀を超え将来に残せるものを作ろう…そんな思いが込められています」と、エンジニアの川村克明氏は語る。
M600の原型が登場した当初の姿は、今回発表されたものとだいぶ構成が異なっていた。CES2008でレポートした際には、ねずみ鋳鉄ではなく「ダクタイル鋳鉄」のシャーシだったし、動作も300W/4ΩのA級アンプから、最終的には600W/4Ωのバランス構成になった。
「当初は技術者の性として、テクニックに走ってしまった部分があったかも知れません」と川村氏は振り返る。「ある程度まとまった段階で音を聴いてみて、これはこれで良いかも知れないが、『R1を鳴らしきる』というコンセプトから外れてしまうなと感じたのです。思い切ってアプローチを変え、『もっとシンプルに、良い音を目指そう』と出直して約1年。M600は現在の姿になりました」。
仕切り直しをしてからは「今までできなかったことを全部やってみよう」としたのだという。「たとえばシャーシに採用したねずみ鋳鉄。磁性体を使うことはこれまでタブーのようにされていましたが、低重心で安定した筐体のためには必要だ、と思ったので採用しました。素材や手段は、良いものを作るために必要だから選んだ。そういった心づもりが反映されているのではと自負しています」
山之内氏も「音を聴いて、圧倒されます。作り手が何を目指しているかがよく分かる。素材選びなども、目指すものがあるからそれを選んだ『必然』だったことが分かります。掲げた思想をここまで徹底して追い込んだ製品はそうそうないでしょう」と評する。
「『迷ったら音を聴け』と言っています」と語るのは宮川社長。「判断基準はやはりそこなんです。迷うことも、もちろんある。でもそんな時、音をじっと聴いていると、製品が『ここをこうして欲しい』と語りかけてくる時がある。そういうものをくみ取って製品に還元していくかが大切だと思うのです」
長谷・川村両氏とも「まだまだ手を加えたい部分がある」と、その目指すところの高さを語る。発売日に向け、TADの新製品はまだまだ進化を遂げそうだ。
■CSTユニットの可能性を追求したい ー TAD-CR1にかけた理想とは
「CR-1は、コンパクトサイズでしか出せないCSTユニットの良さが発揮されたスピーカーです」と語るのは、開発に携わったエンジニアのひとり、長谷 徹氏だ。
「Coherent Source Transducer」の頭文字をとった「CSTユニット」。ベリリウム振動板を採用し、250Hz〜100kHzという広いレンジをカバーする、TADの代名詞とも言える存在だ。2003年のTAD-M1、そして、採算を度外視し、TADラボの理想と技術を結晶化させたフラグシップスピーカー「TAD-R1」(2007年)にも搭載されている。
「CSTユニット開発当初、その音を聴いて『なんてエネルギッシュなんだろう』と驚いたのを覚えています。本当に、今まで聴いたことのない音でした。いくつかサイズ違いのキャビネットに入れ替えたところ、聞こえてくる音がまた全く違う。CSTというユニットが持つポテンシャルの高さを感じました」。
そんなCSTユニットを使って、R1とは違う表現ができるはずだ − コンパクトモデルの開発は2004年からスタートした。
「キャビネットをコンパクト化した以外に、音作りの部分で『何か変えよう』と思った部分はありません。CSTユニットはもう“完成”している。ですから、その可能性を発揮させるシステムのまとめ方がキーだと考えました」と言う長谷氏。TAD-CR1のキャビネット製作にあたっては、定在波の影響などについて、解析ソフトを用いた綿密なシミュレーションを行った。R1にも携わったアンドリュー・ジョーンズ氏、バート・ロカンシー氏らとともに作り上げたという。「アンドリューの感性とTADエンジニアの理論を合わせ、“世界で通用する音”を生み出すことを目指しました」。
「TAD-CR1は新しいスピーカーの表現を聴かせてくれた」と評する山之内氏。「単なるR1の小型モデルではない、このサイズならではの魅力がある。ボディは小さいけれど、その持つ意義は大きいスピーカーだと感じました」と語った。
ただシンプルに、良いものを作るために − 理想に忠実に作った「TAD-M600」
TAD-M600の開発コード名は「XC」。これは「Cross Century」を意味するという。「20世紀にできなかったことを21世紀に実現しよう、そして、世紀を超え将来に残せるものを作ろう…そんな思いが込められています」と、エンジニアの川村克明氏は語る。
M600の原型が登場した当初の姿は、今回発表されたものとだいぶ構成が異なっていた。CES2008でレポートした際には、ねずみ鋳鉄ではなく「ダクタイル鋳鉄」のシャーシだったし、動作も300W/4ΩのA級アンプから、最終的には600W/4Ωのバランス構成になった。
「当初は技術者の性として、テクニックに走ってしまった部分があったかも知れません」と川村氏は振り返る。「ある程度まとまった段階で音を聴いてみて、これはこれで良いかも知れないが、『R1を鳴らしきる』というコンセプトから外れてしまうなと感じたのです。思い切ってアプローチを変え、『もっとシンプルに、良い音を目指そう』と出直して約1年。M600は現在の姿になりました」。
仕切り直しをしてからは「今までできなかったことを全部やってみよう」としたのだという。「たとえばシャーシに採用したねずみ鋳鉄。磁性体を使うことはこれまでタブーのようにされていましたが、低重心で安定した筐体のためには必要だ、と思ったので採用しました。素材や手段は、良いものを作るために必要だから選んだ。そういった心づもりが反映されているのではと自負しています」
山之内氏も「音を聴いて、圧倒されます。作り手が何を目指しているかがよく分かる。素材選びなども、目指すものがあるからそれを選んだ『必然』だったことが分かります。掲げた思想をここまで徹底して追い込んだ製品はそうそうないでしょう」と評する。
「『迷ったら音を聴け』と言っています」と語るのは宮川社長。「判断基準はやはりそこなんです。迷うことも、もちろんある。でもそんな時、音をじっと聴いていると、製品が『ここをこうして欲しい』と語りかけてくる時がある。そういうものをくみ取って製品に還元していくかが大切だと思うのです」
長谷・川村両氏とも「まだまだ手を加えたい部分がある」と、その目指すところの高さを語る。発売日に向け、TADの新製品はまだまだ進化を遂げそうだ。