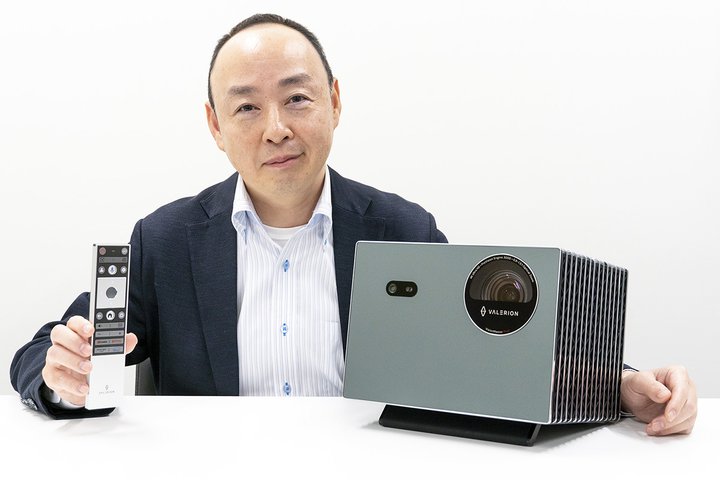公開日 2021/09/03 06:30
小さくとも驚きの満足感、JBLの新スタジオモニター「4309」はファンだけが楽しむのはもったいない
【PR】特筆すべき対応力の高さ
JBLのスタジオモニターに新モデル「4309」が加わった。伝統を引き継ぎながら、シリーズの開発で培われた技術を惜しみなく投入。憧れのJBLを “置けるサイズ” に凝縮した、ファンならずとも注目のアイテムだ。では実際、価格とサイズを抑えながら、どこまでJBLサウンドを実現しているのか? 自身も長きに渡りJBLを愛する土方久明氏が確認した。
■モニタースピーカーシリーズのDNAを受け継ぐ2モデルを聴く
ジェームス・B・ランシングが設立した名門スピーカーブランド JBLは、今年で設立75周年を迎えた。
「Hartsfield(ハーツフィールド)」「Paragon(パラゴン)」「Olympus(オリンパス)」「Everest(エベレスト)」…、同社を代表する製品を挙げろと言われたら枚挙にいとまがないが、中でも多くのオーディオファイルから支持され、JBLの人気を支えてきたのが、「4300シリーズ」のスタジオモニターだ。1970年代に登場した初代「4310」を始め、一斉を風靡した大型の「4343」や「4344」、そして現在も「4367」「4349」「4312G」などラインナップは多い。
そして忘れてはいけないのが、JBLのモニタースピーカーシリーズの中でもう1つの人気シリーズとなっている、小型のスタジオモニターである。古くは「4305」、そして現在もロングセラーを続ける「4306」などがあって、これらは大型モデルを精巧にミニチュア化したような外観とホーンを採用し、小さくともJBLモニタースピーカーのDNAをしっかり保有しているのが人気の理由である。
今回は、7月に発売されたばかりの小型のスタジオモニタースピーカー「4309」を、ハイレゾ、ストリーミング、アナログという幅広いソースでスクランブル試聴するチャンスに恵まれた。しかも、昨年10月に発売されたミドルクラス最新モデル4349にも登場してもらい、果たして4309がJBLのスタジオモニターシリーズらしさが実際に出ているのか確かめながら、試聴したのである。
■所有欲をくすぐるデザイン、ブランドが積み重ねた技術を満載
まずは今回の主役である4309からご紹介しよう。本機は2ウェイ・ホーン型を採用する同社スタジオモニターシリーズの末弟モデルだ。キャビネットサイズは260W×419H×227Dmm、質量は11.0kgと、4367、4349などと比べると大変コンパクト。しかし両モデルが採用する伝統のブルーバッフルとウォールナット仕上げのエンクロージャーデザインをしっかり踏襲している点には、一人のオーディオファイルとして心が高鳴る。
もちろん内部にはV字型ブレーシングを使い、前後左右のエンクロージャーパネルを強固に固定するとともに、底面部にボトムベース・ボードを追加することで、スピーカーから設置面へ伝わる振動を低減させている。
中高域を担当するトゥイーターには、上位モデルで採用されるD2テクノロジーを元にしたリングラジエーター型コンプレッションドライバー「D2410H-2」を搭載。同ドライバーに採用される振動板は25mm径で、アルミダイキャスト製センターコーンとアウターリングを12.5mm径の開口部へ集中させるリングラジエーター型コンプレッション構造と、大変軽量なTeonex製ダイアフラムを高剛性のV断面のリング形状に成形した「Vシェイプ・リングダイアフラム」を搭載しており、30kHz超の高音域特性を可能とする。それを大径ボイスコイルと強力なネオジム・リングマグネットで駆動する設計だ。
ホーン部は「HDI-Xウェーブガイド」技術を用いる新世代の定指向型を採用し、高域から中域まで広い周波数帯域で水平100°/垂直80°の指向性パターンを持ち、独自のウェーブガイド・パターンにより、広範囲のリスニングポイントで良好なサウンドステージと音像表現を実現する。
低域を対応するウーファー部も強力で、新開発の165mm径ユニット「JW165P-4」をJBL伝統のスクエアクル形状によるアルミダイキャストフレームを介して搭載。同ユニットは、同心円状の強化リブを採用した「ブラック・ピュアパルプ・コーン」をSFG磁気回路で駆動し、高耐久性と柔軟性を両立したNBRハーフロールエッジを採用することで、低域表現のリアリティを大きく向上させたという。
ネットワーク周りも抜かりがなく、高域用コンデンサーにLow-ESR(静電抵抗)のメタライズドフィルムキャパシターおよび太ゲージ銅線を用いた空芯コイルを採用したインダクターを採用。歪みを大きく低減させたプレシジョン・ネットワークを搭載する。
フロントバッフルにはトゥイーターの高域レベルを微調整できるスイッチが搭載され、8 - 20kHz間を±0.5dBでコントロールできる。また、バスレフポートはツインポートとなっており、ウーファーが大きく動いた場合でも、エアの流入出をスムーズに行えるスリップストリーム設計が施されている。
■モニタースピーカーシリーズのDNAを受け継ぐ2モデルを聴く
ジェームス・B・ランシングが設立した名門スピーカーブランド JBLは、今年で設立75周年を迎えた。
「Hartsfield(ハーツフィールド)」「Paragon(パラゴン)」「Olympus(オリンパス)」「Everest(エベレスト)」…、同社を代表する製品を挙げろと言われたら枚挙にいとまがないが、中でも多くのオーディオファイルから支持され、JBLの人気を支えてきたのが、「4300シリーズ」のスタジオモニターだ。1970年代に登場した初代「4310」を始め、一斉を風靡した大型の「4343」や「4344」、そして現在も「4367」「4349」「4312G」などラインナップは多い。
そして忘れてはいけないのが、JBLのモニタースピーカーシリーズの中でもう1つの人気シリーズとなっている、小型のスタジオモニターである。古くは「4305」、そして現在もロングセラーを続ける「4306」などがあって、これらは大型モデルを精巧にミニチュア化したような外観とホーンを採用し、小さくともJBLモニタースピーカーのDNAをしっかり保有しているのが人気の理由である。
今回は、7月に発売されたばかりの小型のスタジオモニタースピーカー「4309」を、ハイレゾ、ストリーミング、アナログという幅広いソースでスクランブル試聴するチャンスに恵まれた。しかも、昨年10月に発売されたミドルクラス最新モデル4349にも登場してもらい、果たして4309がJBLのスタジオモニターシリーズらしさが実際に出ているのか確かめながら、試聴したのである。
■所有欲をくすぐるデザイン、ブランドが積み重ねた技術を満載
まずは今回の主役である4309からご紹介しよう。本機は2ウェイ・ホーン型を採用する同社スタジオモニターシリーズの末弟モデルだ。キャビネットサイズは260W×419H×227Dmm、質量は11.0kgと、4367、4349などと比べると大変コンパクト。しかし両モデルが採用する伝統のブルーバッフルとウォールナット仕上げのエンクロージャーデザインをしっかり踏襲している点には、一人のオーディオファイルとして心が高鳴る。
もちろん内部にはV字型ブレーシングを使い、前後左右のエンクロージャーパネルを強固に固定するとともに、底面部にボトムベース・ボードを追加することで、スピーカーから設置面へ伝わる振動を低減させている。
中高域を担当するトゥイーターには、上位モデルで採用されるD2テクノロジーを元にしたリングラジエーター型コンプレッションドライバー「D2410H-2」を搭載。同ドライバーに採用される振動板は25mm径で、アルミダイキャスト製センターコーンとアウターリングを12.5mm径の開口部へ集中させるリングラジエーター型コンプレッション構造と、大変軽量なTeonex製ダイアフラムを高剛性のV断面のリング形状に成形した「Vシェイプ・リングダイアフラム」を搭載しており、30kHz超の高音域特性を可能とする。それを大径ボイスコイルと強力なネオジム・リングマグネットで駆動する設計だ。
ホーン部は「HDI-Xウェーブガイド」技術を用いる新世代の定指向型を採用し、高域から中域まで広い周波数帯域で水平100°/垂直80°の指向性パターンを持ち、独自のウェーブガイド・パターンにより、広範囲のリスニングポイントで良好なサウンドステージと音像表現を実現する。
低域を対応するウーファー部も強力で、新開発の165mm径ユニット「JW165P-4」をJBL伝統のスクエアクル形状によるアルミダイキャストフレームを介して搭載。同ユニットは、同心円状の強化リブを採用した「ブラック・ピュアパルプ・コーン」をSFG磁気回路で駆動し、高耐久性と柔軟性を両立したNBRハーフロールエッジを採用することで、低域表現のリアリティを大きく向上させたという。
ネットワーク周りも抜かりがなく、高域用コンデンサーにLow-ESR(静電抵抗)のメタライズドフィルムキャパシターおよび太ゲージ銅線を用いた空芯コイルを採用したインダクターを採用。歪みを大きく低減させたプレシジョン・ネットワークを搭載する。
フロントバッフルにはトゥイーターの高域レベルを微調整できるスイッチが搭載され、8 - 20kHz間を±0.5dBでコントロールできる。また、バスレフポートはツインポートとなっており、ウーファーが大きく動いた場合でも、エアの流入出をスムーズに行えるスリップストリーム設計が施されている。