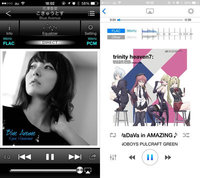[連載]高橋敦のオーディオ絶対領域
【第132回】高橋敦の“オーディオ金属”大全 − 音と密接に関わる「金属」を知る
●内部損失
ざっくりと言うと、振動エネルギーを受けた際にそれを素早く吸収して振動を素早く収める金属は「内部損失が大きい」、逆に振動エネルギーを受けた際にそれをあまり吸収せず長く持続させる金属は「内部損失が小さい」という感じだ。もっとざっくりと言えば「内部損失が大きい=響かない」「内部損失が小さい=響く」素材という感じ。吸収されたエネルギーはもちろん消えて無くなるわけではなく、原子とか分子とかそういうレベルでの「内部摩擦」で微小な熱に変換されている。
例えばスピーカーやイヤホンの振動板や筐体だとそれ自体は響かない方がより正確な駆動、音の再現性を期待できるため、内部損失の大きな素材が好まれやすい。代表的な例はマグネシウム振動板だろうか。純マグネシウムは金属としてはトップレベルに内部損失の大きな素材だ。
一方、オーディオで金属を使う場合で響かせることが狙いというのはあまり多くはない。「このスピーカーのエンクロージャーはアルミ製だが金属的な音はしない」というような表現が褒め言葉として多く使われるように、オーディオにおいて金属の響きはあまり好まれないのだ。だが「楽器でもよく利用されている真鍮(ブラス)を採用してその響きを云々」のようにその響きを積極的に利用した音作りが売りになっている製品もある。
●熱伝導率
これは言葉そのまんまの意味でわかりやすいだろう。例えば金属板の一部に熱を加えた際にその熱が板の全体に素早く効率的に伝わる金属は「熱伝導率が高い」、そうでない金属は「熱伝導率が低い」わけだ。
オーディオやPC等では例えば「放熱板」「ヒートシンク」という部分で使う場合には熱伝導率が高い金属が好都合。CPUやDSPなどのチップは高集積であるために小さい面積から大きな熱が発せられる。熱エネルギーは膨大なのに放熱できる面積が小さいわけで、何の対策もしないと自身のその熱で動作に不具合を起こしかねない。そこでCPUやDSP等に接してそこから熱を吸収してより大きな面積で放熱をしようというのが放熱板・ヒートシンクだ。熱を効率良く素早く受け取るためには熱伝導率が高い方が良い。そこで使われる代表的な金属としては銅とアルミが挙げられる。
またポータブル機器のアルミ合金筐体の全体が熱を持つ場合があるが、あれはその分だけ筐体を通しての放熱もしっかり行われているとも考えられる。
●導電性(導電率、電気伝導率、電気抵抗率)
この記事の始めの方で述べた「エレクトロニック(電気的な)」要素において重要な特性がこれ。アコースティックな面での「内部損失」と対となるエレクトロニックな特性と言えるかもしれない。つまり物理的な振動ではなく電気を与えられたときのそれに対しての損失の大小が「導電性」だ。
例えば金属製の導線の一端から流される電気を100%とした場合、それがもう片方の端でも90%を維持できる素材と80%にまで落ちてしまう素材では、前者の方が「導電性が高い」「抵抗が小さい」となるし、後者は「導電性が低い」「抵抗が大きい」といったような表現になる。
この導電性はもちろん基本的には、高ければ高いほど電気回路的には理想的。電力の損失は少なくなるし、音声信号として見た場合でも波形の崩れが少なくなる。つまり入力された音声信号の大小も波形もより正確にそのままに近い形で伝達できることを期待できる。いわゆる「入力と出力の忠実度が高い」みたいな感じだ。
ただし現実的には忠実=自然で好ましいとも言い切れないのが難しい。例えば導電性の高さで言えば純銀がトップクラス。しかしイヤホンのリケーブル等で経験のある方も多いと思うが一般に、純銀ケーブルを使うと音調はブライト、高域の輝きを強めたように感じられるものになりがちだ。もちろんそれが狙いの場合はそれでよいのだが、それを不自然と感じる方もいるだろう。
これは価格や入手性、加工性からケーブル等の素材としては過去から現在まで銅が一般的で、「銅の音が基準になっている」からと思われる。それぞれのオーディオ機器やオーディオシステム全体が銅を基準にチューニングされていてユーザーもそれに慣れているとなれば、その一部だけを後から銀に代えたときにはそのチューニングが崩れたり、ユーザーも違和感を覚えたりということがありえるわけだ。
しかしさらに逆に言えば、「崩せる」「違えられる」ということはそれを狙って使うのであれば大きな利点でもあり、純銀等を好んでチューニングに活用するメーカーやユーザーの方もいる。
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 次へ