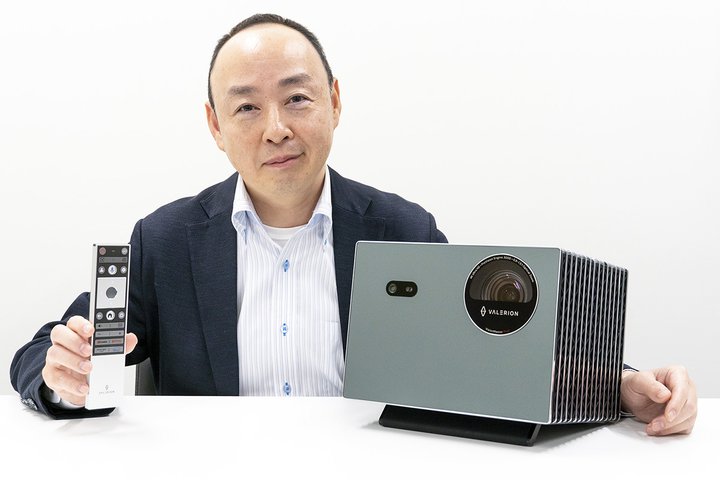HOME > ニュース > AV&ホームシアターニュース
公開日 2007/02/06 18:59
話題のソフトを“Wooo”で観る − 第5回『X-MEN:ファイナル デシジョン』 (Blu-ray Disc)
この連載「話題のソフトを“Wooo”で観る」では、AV評論家・大橋伸太郎氏が旬のソフトの見どころや内容をご紹介するとともに、“Wooo”薄型テレビで視聴した際の映像調整のコツなどについてもお伝えします。DVDソフトに限らず、放送や次世代光ディスクなど、様々なコンテンツをご紹介していく予定です。第5回はBlu-ray Discソフト『X-MEN:ファイナル デシジョン』をお届けします。
『仮面ライダー』や『サイボーグ009』で有名な石森章太郎のマンガに、『ミュータントサブ』(1965~1966)という作品がある。短期間で少年誌での連載を終えた比較的地味な作品なのだが、その中に「白い少年」という筆者の大変好きな一話がある。特殊能力を持つ少女マリはある冬の朝、誰かの名を呼び続ける声をテレパシーで感じて、同じ運命を分かち合うサブを伴い、たぐり寄せられるように郊外の村にたどり着く。村のはずれに人間に顧みられない竪穴があり声はそこから聞こえていた。
ふたりが降りていくと暗黒の地下世界に通じていて、声の強くなる奥へと進んでいくと何かに取りすがる少年がいた。言葉を持たずテレパシーで会話をしていた太古の人類の生き残りだった。最後のもう一人だった娘が死に、悲嘆のあまり心で呼び続けていたのだった。そこにテレパシーに答えるマリが現われ、少年は娘が帰ってきたものと思い込む…。
この続きはコミックスでお読みいただきたいのだが、「特殊能力を持つこと」イコール「スーパーマン」であることだった時代に、人は聴こえないもの見えないものを感じてしまうことがいかに孤独で悲哀に満ちたものであるかを描き、少年だった筆者の心を揺さぶったのである。
●アウトサイダーである苦悩をクローズアップ
『X-MEN』は1963年からマーベルコミックスで刊行が始まったミュータントを主人公にしたコミックで、『X-MEN:ファイナル デシジョン』は、2000年に第一作が製作された実写映画化の三作目である。何しろ売れっ子になる前、トキワ荘に住んでいた時代に、出版社から前借りをしてシアトルの世界漫画大会に勇躍駆けつけたほどの石森章太郎だから、その昔X-MENを他の日本人に先駆けて読んでいたかも、と想像は膨らむ。
筆者は1960年代のマーベルコミックを読んでいないので断定的にはいえないが、初期のX-MENはキャラクターの奇抜さが中心のアクションコミックである。現代の映画版は人気キャラクターの活躍をSFXで描いたものだが、そのトーンを異にしているのではないか。
『X-MEN』は有名俳優が出演しSFXに金をかけた準大作である。しかし、レトロなキャラクターの脳天気なアクションを実写化しただけでは現代の映画として成功しなかったろう。特殊な能力を持つことでアウトサイダーたちが背負う孤独を描くことをクローズアップし、テレパスたちが互いに畏れを抱きあい肩を寄せ合うように潜む闇の輝きを映画のトーンに設定したことで、古きよき時代のコミックに新しい命が吹き込まれたのである。
アメリカでのヒットを引っさげて『X-MEN』第一作が日本で封切られた時、都内の劇場の公開第一週の興行成績は惨憺たるものだった。ほとんどの日本人にとってコミックの『X-MEN』は馴染みが薄いのだから当然である。筆者は国際線の機内で見て、なんて暗い映画なんだろうと思った。しかし、第2作、第3作とシリーズを重ねて行く内に日本でも人気は定着した。日本ではDVDで映画を見ることの多い男性映画ファンが次第に『X-MEN』の魅力を知ったからである。
超人を描く映画が最近とみに増えている。アメリカだったら格差社会の閉塞感の現われという分析も出来るだろうが、日本での受容のされ方はたぶん違う。『X-MEN』のキャラクターたちの特殊能力は彼らの心の奥に隠されていて、善にも役立てば悪をも為す双面性に彼ら自身苦しんでいる。私たち現実の人間の心の奥にも得体の知れないものが住んでいて、それがよい方向に働けば実り多い創作活動や誰かを愛する原動力にもなるが、悪くすると怪物に成長しかねないことを、今では多くの者が知っている。
幸か不幸か、私たちは超能力を持たないが(もし、ファイル・ウェブ読者の方に、テレパスやサイコキネシストがいたらゴメンナサイ)、誰しも無意識の欲望に抗う見えない戦いがあって、その点では映画『X-MEN』のミュータントたちと似ていなくもない。彼らは特異な能力ゆえに親しみを感じさせるという逆説を生んだ。1960年代の荒唐無稽なアクションコミックに現代的でボーダーレスな「心」を吹き込み、『X-MEN』は他の超人映画の群れから抜け出し現代的なルックスを持つヒューマンな映画になったのである。
しかし、そこはアメリカで生まれた物語、石森章太郎の小品と大いに違うのは、ミュータントたちが一派を形成し社会的に無視できないパワーとなり政府まで巻き込んでしまう。しかもミュータントの間で穏健派と過激派に分かれて内部抗争を始めてしまうのだから始末が悪い。そのネアカな事大主義が映画的に面白く、ストーリー展開上もエンターテインメントとしての骨格になっている。映画『X-MEN』は様々な要素を取り入れてコミックから格段のパワーアップを果たしているが、キャラクター達が痛快に立ち回るコミックの初心を忘れていない。何よりスタッフがコミック『X-MEN』の世界を愛して楽しんで作った映画であることが伝わってくる。娯楽映画がいかにして観客を獲得するか、成功のコツを教えてくれる作品である。
●MPEG-4 AVCでエンコードされた高画質ソフト
映画第三作目の『X-MENファイナルデシジョン』(原題はTHE LAST STAND)のパッケージソフトは、DVDとBlu-ray Discの二方式で発売された。筆者は迷わずハイビジョン映像で収録されたブルーレイディスクのほうを購入されることを薦める。理由は、このディスクがMPEG-4 AVCでエンコードされているからだ。H.264とも称されるこの方式は、現時点の最も優れた映像の圧縮形式と言っても良い。すでに発売されたBDビデオの大半はMPEG2(MP@HL)でエンコードされているが、MPEG4 AVCは圧縮アルゴリズムが格段に進化しており、ノイズの抑圧を始めとした設定を非常に緻密に行うことができる。実際、この方式で収録されたディスクは画質の優秀なものが多い。20世紀フォックス ホームエンターテインメントはMPEG4 AVCの採用に積極的なメーカーで、中でも『X-MEN:ファイナル デシジョン』は、ハイビジョン映画ソフトの中で一、二を争う素晴らしい画質に仕上がった。それでは、ソフトの魅力と見どころについて紹介していこう。
ストーリーを簡単に紹介すると、ミュータントたちの存在が公然と知られるようになった近い未来、超能力を持つ子供たちに正しい使い道を教える穏健派のエグゼピア(パトリック・スチュワート)と、そこから袂を分かち「ブラザーフッド」を率いる過激派のマグニートー(イアン・マッケラン)は、深層意識下にレベル5の強大な人格フェニックスを持つジーン(ファムケ・ヤンセン)の争奪を始める。折しも、ミュータントのパワーを脅威に感じた合衆国政府がパワーの源である細胞の特殊活動を絶つ抗体「キュア」を幼い少年の培養体から生成し、ミュータントたちの強制治療を開始する。少女時代にパワー・バリアで持てる能力を封殺したエグゼピアを憎むジーンは彼を殺害、総決起したブラザーフッドに加わりアルカトラズ島に隔離された少年の抹殺に向かう。ジーンのかつての恋人で映画の主人公・ウルヴァリン(ヒュー・ジャックマン)は苦しんだ末、ブラザーフッドを阻止するためにストーム(ハル・ベリー)らとアルカトラズ島へ向かう…。
このシリーズの映像のトーンを「アウトサイダーたちが才能を潜ませる闇の輝き」と先に表現したが、実は第2作、第3作とスケールアップしていくにつれて暗さは薄れてしまう。『X-MEN:ファイナル デシジョン』は完結編だけに後半はミュータント同士による政府を巻き込んでの戦争映画であり、前二作に比べ白昼の描写が多い。シリーズの特徴は後退したものの、CGやSFXを使いながらしっとりとしたトーンで魅せるビジュアルの優れた映画である。前作での、金属を自由自在に操る能力を持つマグニートーが巨大な戦闘機を指先で静止させる素晴らしいシーンが忘れられない。こうしたサイキックな映像の魅力は今回もちゃんと盛り込まれている。
その最たるものは、マグニートーがベイブリッジをサイコキネシスで移動しアルカトラズ島に着岸させるクライマックス。しかし、筆者が好きなのは、総決起したブラザーフッドが森の奥に集結、そこに加わったジーンとマグニートーが対話するシーン(CH12)である。ここでの一連のカットの撮影は非常に美しい。ジーンがもう一つの怒れる人格フェニックスに変わると超常現象が起き顔も醜く変わる。その特殊メイクへの変化をハイビジョンでは克明に描き出す。キュアを仕込んだ銃が浮かんで静止した時のフォーカス移動はハイビジョンでないと気付かないほど微妙だが、こうした撮影のこだわりに感心させられる。超能力者の光と影、いいかえれば人間の双面性を表現したイアン・マッケランの半分溶暗した表情に刻まれた深い皺もまた、ハイビジョンならではの表現である。
●日立“Wooo”「W42P-HR9000」で本ソフトを視聴

視聴には「W42P-HR9000」を使用したプレイステーション3を日立のプラズマテレビ「W42P-HR9000」にHDMIで接続した筆者宅の二階仕事場で『X-MEN:ファイナル デシジョン』を視聴し、映画の入念なこだわりの隅々まで味わいつくすことが出来た。W42P-HR9000は良質な映像を入力するほど持ち味を発揮する、鮮鋭度となめらかさを兼ね備えた優れたハイビジョンテレビだ。MPEG4 AVCの特長はノイズの抑圧に優れ、階調の微妙なコントロールなど映像に即したきめ細かな設定ができることにある。例に挙げた森の中のジーンとマグニートーの対話シーンをW42P-HR9000で見ると、今にも発動せんとする封印された怒りを象徴する赤紫のドレスをまとったジーンが背景からクッキリと浮き上がる。背景に発生しやすいランダムノイズによる妨害がよく抑えられてざわつきがなく、対比的にフォーカスした近景の人物においては俳優の表情などの階調表現が優れているからこの立体表現が生まれる。W42P-HR9000が持てる特長を発揮し、MPEG4 AVCの優れた映像を引き出し的確に伝えていることを実感させる。
●画質調整したあとの変化など
一本の映画を通してみる場合の基本は色温度の設定であるが、『X-MEN:ファイナル デシジョン』の場合、映像ポジションは「シネマティック」、色温度は迷ったが「低」を選択した。この方がミュータントたちの表情に人間的な懊悩が生まれる。前二作との世界観上の連続性も生まれる。
オーディオでも何でもそうだが、素性のいいものはセットアップに手間取らない。DVDに比べBDビデオでは映像調整の必要はむしろ少ない。ディスプレイがW42-HR9000なら別段調整に煩わされずに全編を楽しく見ることができるのだが、よりよく見るために先に挙げた森の中のマグニートーのクローズアップを例に、作中で多用されている超能力者の光と影のライティングをより効果的なものに変えてみよう。
色温度を低にした分、黒レベル(ブライトネス)を+3に上げた。「ディテール」は比較的小振幅の映像信号のエッジを急峻にする機能で、オンにすると見かけ上の鮮鋭度は上がるが、俳優の表情が硬くなる。引きのシーンで背景がざわついた感じになり、遠近差が薄れて映像の魅力が後退する。これは鮮鋭度の足りないソースを補強する機能で本作のような高画質ソフトに使うべきでない。同様の機能と思われるが、LTI(ルミネセンス信号の鮮鋭度を高める)を中にした方が好結果を得られた。
■大橋伸太郎の設定値
・映像モード:シネマティック
・明るさ:-20
・黒レベル:+3
・色の濃さ:-22
・色合い:+8
・画質:-15
・色温度:低
・ディテール:切
・コントラスト:リニア
・黒補正:切
・LTI:中
・CTI:切
・YNR:切
・CNR:切
・RGBドライブ、カットオフ:すべて0
上記の設定でW42-HR9000は『X-MEN:ファイナルデシジョン』を遺憾なく表現しきる最高のディスプレイになる。アップ・トゥ・デートな息吹を吹き込まれたコミックヒーローたちの活躍に、しばし時間が経つのを忘れてほしい。
(大橋伸太郎)
大橋伸太郎 プロフィール
1956 年神奈川県鎌倉市生まれ。早稲田大学第一文学部卒。フジサンケイグループにて、美術書、児童書を企画編集後、(株)音元出版に入社、1990年『AV REVIEW』編集長、1998年には日本初にして現在も唯一の定期刊行ホームシアター専門誌『ホームシアターファイル』を刊行した。ホームシアターのオーソリティとして講演多数2006年に評論家に転身。趣味はウィーン、ミラノなど海外都市訪問をふくむコンサート鑑賞、アスレチックジム、ボルドーワイン。
バックナンバー
・第1回『ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女』
・第2回『アンダーワールド2 エボリューション』
・第3回『ダ・ヴィンチ・コード』
・第4回『イノセンス』 (Blu-ray Disc)
『仮面ライダー』や『サイボーグ009』で有名な石森章太郎のマンガに、『ミュータントサブ』(1965~1966)という作品がある。短期間で少年誌での連載を終えた比較的地味な作品なのだが、その中に「白い少年」という筆者の大変好きな一話がある。特殊能力を持つ少女マリはある冬の朝、誰かの名を呼び続ける声をテレパシーで感じて、同じ運命を分かち合うサブを伴い、たぐり寄せられるように郊外の村にたどり着く。村のはずれに人間に顧みられない竪穴があり声はそこから聞こえていた。
ふたりが降りていくと暗黒の地下世界に通じていて、声の強くなる奥へと進んでいくと何かに取りすがる少年がいた。言葉を持たずテレパシーで会話をしていた太古の人類の生き残りだった。最後のもう一人だった娘が死に、悲嘆のあまり心で呼び続けていたのだった。そこにテレパシーに答えるマリが現われ、少年は娘が帰ってきたものと思い込む…。
この続きはコミックスでお読みいただきたいのだが、「特殊能力を持つこと」イコール「スーパーマン」であることだった時代に、人は聴こえないもの見えないものを感じてしまうことがいかに孤独で悲哀に満ちたものであるかを描き、少年だった筆者の心を揺さぶったのである。
●アウトサイダーである苦悩をクローズアップ
『X-MEN』は1963年からマーベルコミックスで刊行が始まったミュータントを主人公にしたコミックで、『X-MEN:ファイナル デシジョン』は、2000年に第一作が製作された実写映画化の三作目である。何しろ売れっ子になる前、トキワ荘に住んでいた時代に、出版社から前借りをしてシアトルの世界漫画大会に勇躍駆けつけたほどの石森章太郎だから、その昔X-MENを他の日本人に先駆けて読んでいたかも、と想像は膨らむ。
筆者は1960年代のマーベルコミックを読んでいないので断定的にはいえないが、初期のX-MENはキャラクターの奇抜さが中心のアクションコミックである。現代の映画版は人気キャラクターの活躍をSFXで描いたものだが、そのトーンを異にしているのではないか。
『X-MEN』は有名俳優が出演しSFXに金をかけた準大作である。しかし、レトロなキャラクターの脳天気なアクションを実写化しただけでは現代の映画として成功しなかったろう。特殊な能力を持つことでアウトサイダーたちが背負う孤独を描くことをクローズアップし、テレパスたちが互いに畏れを抱きあい肩を寄せ合うように潜む闇の輝きを映画のトーンに設定したことで、古きよき時代のコミックに新しい命が吹き込まれたのである。
アメリカでのヒットを引っさげて『X-MEN』第一作が日本で封切られた時、都内の劇場の公開第一週の興行成績は惨憺たるものだった。ほとんどの日本人にとってコミックの『X-MEN』は馴染みが薄いのだから当然である。筆者は国際線の機内で見て、なんて暗い映画なんだろうと思った。しかし、第2作、第3作とシリーズを重ねて行く内に日本でも人気は定着した。日本ではDVDで映画を見ることの多い男性映画ファンが次第に『X-MEN』の魅力を知ったからである。
超人を描く映画が最近とみに増えている。アメリカだったら格差社会の閉塞感の現われという分析も出来るだろうが、日本での受容のされ方はたぶん違う。『X-MEN』のキャラクターたちの特殊能力は彼らの心の奥に隠されていて、善にも役立てば悪をも為す双面性に彼ら自身苦しんでいる。私たち現実の人間の心の奥にも得体の知れないものが住んでいて、それがよい方向に働けば実り多い創作活動や誰かを愛する原動力にもなるが、悪くすると怪物に成長しかねないことを、今では多くの者が知っている。
幸か不幸か、私たちは超能力を持たないが(もし、ファイル・ウェブ読者の方に、テレパスやサイコキネシストがいたらゴメンナサイ)、誰しも無意識の欲望に抗う見えない戦いがあって、その点では映画『X-MEN』のミュータントたちと似ていなくもない。彼らは特異な能力ゆえに親しみを感じさせるという逆説を生んだ。1960年代の荒唐無稽なアクションコミックに現代的でボーダーレスな「心」を吹き込み、『X-MEN』は他の超人映画の群れから抜け出し現代的なルックスを持つヒューマンな映画になったのである。
しかし、そこはアメリカで生まれた物語、石森章太郎の小品と大いに違うのは、ミュータントたちが一派を形成し社会的に無視できないパワーとなり政府まで巻き込んでしまう。しかもミュータントの間で穏健派と過激派に分かれて内部抗争を始めてしまうのだから始末が悪い。そのネアカな事大主義が映画的に面白く、ストーリー展開上もエンターテインメントとしての骨格になっている。映画『X-MEN』は様々な要素を取り入れてコミックから格段のパワーアップを果たしているが、キャラクター達が痛快に立ち回るコミックの初心を忘れていない。何よりスタッフがコミック『X-MEN』の世界を愛して楽しんで作った映画であることが伝わってくる。娯楽映画がいかにして観客を獲得するか、成功のコツを教えてくれる作品である。
●MPEG-4 AVCでエンコードされた高画質ソフト
映画第三作目の『X-MENファイナルデシジョン』(原題はTHE LAST STAND)のパッケージソフトは、DVDとBlu-ray Discの二方式で発売された。筆者は迷わずハイビジョン映像で収録されたブルーレイディスクのほうを購入されることを薦める。理由は、このディスクがMPEG-4 AVCでエンコードされているからだ。H.264とも称されるこの方式は、現時点の最も優れた映像の圧縮形式と言っても良い。すでに発売されたBDビデオの大半はMPEG2(MP@HL)でエンコードされているが、MPEG4 AVCは圧縮アルゴリズムが格段に進化しており、ノイズの抑圧を始めとした設定を非常に緻密に行うことができる。実際、この方式で収録されたディスクは画質の優秀なものが多い。20世紀フォックス ホームエンターテインメントはMPEG4 AVCの採用に積極的なメーカーで、中でも『X-MEN:ファイナル デシジョン』は、ハイビジョン映画ソフトの中で一、二を争う素晴らしい画質に仕上がった。それでは、ソフトの魅力と見どころについて紹介していこう。
ストーリーを簡単に紹介すると、ミュータントたちの存在が公然と知られるようになった近い未来、超能力を持つ子供たちに正しい使い道を教える穏健派のエグゼピア(パトリック・スチュワート)と、そこから袂を分かち「ブラザーフッド」を率いる過激派のマグニートー(イアン・マッケラン)は、深層意識下にレベル5の強大な人格フェニックスを持つジーン(ファムケ・ヤンセン)の争奪を始める。折しも、ミュータントのパワーを脅威に感じた合衆国政府がパワーの源である細胞の特殊活動を絶つ抗体「キュア」を幼い少年の培養体から生成し、ミュータントたちの強制治療を開始する。少女時代にパワー・バリアで持てる能力を封殺したエグゼピアを憎むジーンは彼を殺害、総決起したブラザーフッドに加わりアルカトラズ島に隔離された少年の抹殺に向かう。ジーンのかつての恋人で映画の主人公・ウルヴァリン(ヒュー・ジャックマン)は苦しんだ末、ブラザーフッドを阻止するためにストーム(ハル・ベリー)らとアルカトラズ島へ向かう…。
このシリーズの映像のトーンを「アウトサイダーたちが才能を潜ませる闇の輝き」と先に表現したが、実は第2作、第3作とスケールアップしていくにつれて暗さは薄れてしまう。『X-MEN:ファイナル デシジョン』は完結編だけに後半はミュータント同士による政府を巻き込んでの戦争映画であり、前二作に比べ白昼の描写が多い。シリーズの特徴は後退したものの、CGやSFXを使いながらしっとりとしたトーンで魅せるビジュアルの優れた映画である。前作での、金属を自由自在に操る能力を持つマグニートーが巨大な戦闘機を指先で静止させる素晴らしいシーンが忘れられない。こうしたサイキックな映像の魅力は今回もちゃんと盛り込まれている。
その最たるものは、マグニートーがベイブリッジをサイコキネシスで移動しアルカトラズ島に着岸させるクライマックス。しかし、筆者が好きなのは、総決起したブラザーフッドが森の奥に集結、そこに加わったジーンとマグニートーが対話するシーン(CH12)である。ここでの一連のカットの撮影は非常に美しい。ジーンがもう一つの怒れる人格フェニックスに変わると超常現象が起き顔も醜く変わる。その特殊メイクへの変化をハイビジョンでは克明に描き出す。キュアを仕込んだ銃が浮かんで静止した時のフォーカス移動はハイビジョンでないと気付かないほど微妙だが、こうした撮影のこだわりに感心させられる。超能力者の光と影、いいかえれば人間の双面性を表現したイアン・マッケランの半分溶暗した表情に刻まれた深い皺もまた、ハイビジョンならではの表現である。
●日立“Wooo”「W42P-HR9000」で本ソフトを視聴

視聴には「W42P-HR9000」を使用した
●画質調整したあとの変化など
一本の映画を通してみる場合の基本は色温度の設定であるが、『X-MEN:ファイナル デシジョン』の場合、映像ポジションは「シネマティック」、色温度は迷ったが「低」を選択した。この方がミュータントたちの表情に人間的な懊悩が生まれる。前二作との世界観上の連続性も生まれる。
オーディオでも何でもそうだが、素性のいいものはセットアップに手間取らない。DVDに比べBDビデオでは映像調整の必要はむしろ少ない。ディスプレイがW42-HR9000なら別段調整に煩わされずに全編を楽しく見ることができるのだが、よりよく見るために先に挙げた森の中のマグニートーのクローズアップを例に、作中で多用されている超能力者の光と影のライティングをより効果的なものに変えてみよう。
色温度を低にした分、黒レベル(ブライトネス)を+3に上げた。「ディテール」は比較的小振幅の映像信号のエッジを急峻にする機能で、オンにすると見かけ上の鮮鋭度は上がるが、俳優の表情が硬くなる。引きのシーンで背景がざわついた感じになり、遠近差が薄れて映像の魅力が後退する。これは鮮鋭度の足りないソースを補強する機能で本作のような高画質ソフトに使うべきでない。同様の機能と思われるが、LTI(ルミネセンス信号の鮮鋭度を高める)を中にした方が好結果を得られた。
■大橋伸太郎の設定値
・映像モード:シネマティック
・明るさ:-20
・黒レベル:+3
・色の濃さ:-22
・色合い:+8
・画質:-15
・色温度:低
・ディテール:切
・コントラスト:リニア
・黒補正:切
・LTI:中
・CTI:切
・YNR:切
・CNR:切
・RGBドライブ、カットオフ:すべて0
上記の設定でW42-HR9000は『X-MEN:ファイナルデシジョン』を遺憾なく表現しきる最高のディスプレイになる。アップ・トゥ・デートな息吹を吹き込まれたコミックヒーローたちの活躍に、しばし時間が経つのを忘れてほしい。
(大橋伸太郎)
大橋伸太郎 プロフィール
1956 年神奈川県鎌倉市生まれ。早稲田大学第一文学部卒。フジサンケイグループにて、美術書、児童書を企画編集後、(株)音元出版に入社、1990年『AV REVIEW』編集長、1998年には日本初にして現在も唯一の定期刊行ホームシアター専門誌『ホームシアターファイル』を刊行した。ホームシアターのオーソリティとして講演多数2006年に評論家に転身。趣味はウィーン、ミラノなど海外都市訪問をふくむコンサート鑑賞、アスレチックジム、ボルドーワイン。
バックナンバー
・第1回『ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女』
・第2回『アンダーワールド2 エボリューション』
・第3回『ダ・ヴィンチ・コード』
・第4回『イノセンス』 (Blu-ray Disc)